「人事評価システム」の製品比較表
※税込と表記されている場合を除き、全て税抜価格を記載しています
-
- 製品名
- 料金プラン
- プラン名金額
- 無料トライアル
- 最低利用期間
- 基本的な機能
-
- 日報共有機能
- 勤怠管理システム連携
- 資格取得申請機能
- 目標管理機能
- 評価シートのテンプレートあり
- ハイパフォーマンス分析
- 評価傾向分析
- 評価分布表示
- MBO評価対応
- 行動特性評価
- 帳票自動作成
- 人事給与システム連携
- 大規模企業向け
- PDF出力
- 小中規模企業向け
- csv出力
- Excel出力
- 組織図作成
- アンケート機能
- サービス資料
- 無料ダウンロード
- ソフト種別
- 推奨環境
- サポート
-
-
-
- 初期費用 100,000円
- プラン 16,000円/月額 備考
- 無料デモのご利用や
貴社の企業規模に合わせたお見積もりも承っております。また、お見積依頼と同時に、他社サービスとの比較やラフールサーベイに関するご質問などございましたら、併せてお問い合わせいただけます。
- 12か月
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期設定費用 要相談
- 月額費用 要相談
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ Windowsアプリ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 料金プラン 要相談
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 無料 備考
- アカウント設定などの導入支援費用を含む
- 基本料金 350円 / アカウント
- ボーナス費用 ボーナス交換の金額 備考
- 従業員がボーナスポイント(Sushi)をギフト券やその他の商品と交換する際、その交換にかかる費用はお客様が負担することになります。
- なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円
- 少人数プラン 月額10,000円~ 備考
- 10名以下
- ライトプラン 月額30,000円~ 備考
- 30名以下
- ビジネスプラン 要相談 備考
- 50名以上
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- プラン料金 プランに応じて3段階で変動 備考
- 初回のみ発生
- ご利用料金 ユーザーID数に応じて変動 備考
- 利用料金が発生するのはフィードバックを実施した1ヶ月間のみです。管理画面はそれ以外の期間も自由にご利用いただけます
- 更新料金 利用しているプランに 応じて変動 備考
- 2年目以降毎年発生
- 1ヶ月
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 150,000円
- 50名プラン 30,000円/月額 備考
- システム内登録が50名までの従業員数のプランです。
- 200名プラン 80,000円/月額 備考
- システム内登録が51名~200名までの従業員数のプランです。
- 500名プラン 150,000円/月額 備考
- システム内登録が201名~500名までの従業員数のプランです。
- 1年
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- 制限なし
-
-
-
- オンプレミス型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- スタートプラン 10,000円~/月額 備考
- 採用管理機能と人材DB機能で人事情報をスムーズに管理。人事情報を一元管理したい方向けプランです。
- スタンダードプラン 60,000円~/月額 備考
- 採用管理機能と人材DB機能に加え、人材情報の分析機能を追加したプラン。人材情報を可視化します
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- プラン 40,000円~/月額
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 400,000円
- システム利用料 18,000円~/月額 備考
- 導入月の利用費は免除となります。導入翌月からシステム利用料が発生します。システム利用料に加え1,000円のシステムメンテナンス費用が加算されますが、100名以下の場合のシステム利用費は一律18,000円です。
- 2年
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談 備考
- 問合わせ後にヒアリング
- 利用料金 要相談
- なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談 備考
- 問合わせの後デモンストレーション
- 利用料金 要相談
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 200,000円 備考
- 従業員数により変動
- ⽉額費⽤ 10,000円/月額 備考
- 30名まで
31名~ 300円(月額)/1名が追加
- 1ヵ月
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談 備考
- 問合わせ後にヒアリング
- 利用料金 要相談
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト オンプレミス型ソフト
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 110,000円(税込)
- 2機能プラン 月額5,500円(税込)~ 備考
- ・目標評価
・行動評価 or 職務評価 - 3機能プラン 月額8,250円(税込)~ 備考
- ・目標評価
・行動評価
・職務評価
- 6か月間
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談 備考
- 問合わせの後ヒアリング
- 利用料金 要相談
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談 備考
- 問合わせ後にお見積り
- 利用料金 要相談
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談 備考
- 問合わせの後ヒアリング
- 利用料金 要相談
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 従業員データベース 無料
- 料金 月額500円〜/人
- 12か月~
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
価格や製品機能など、見やすい一覧表から、気になる製品をまとめてチェック!












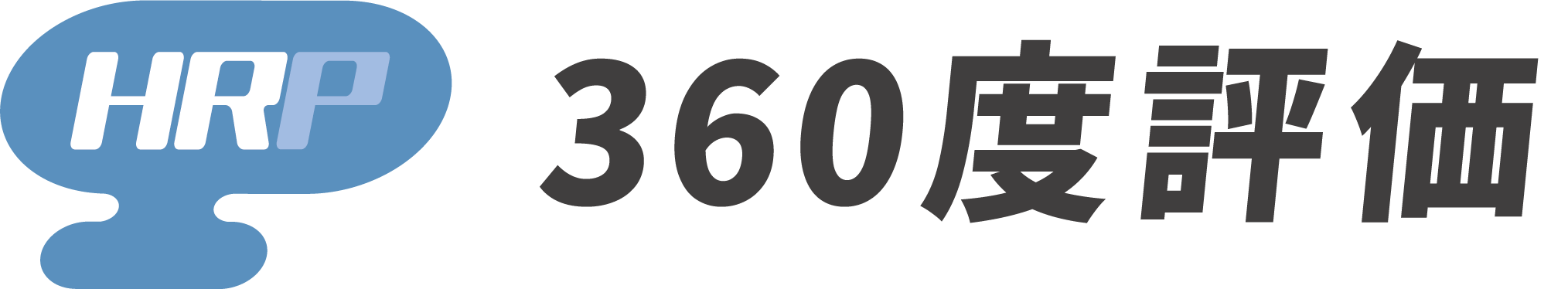





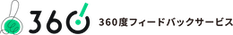





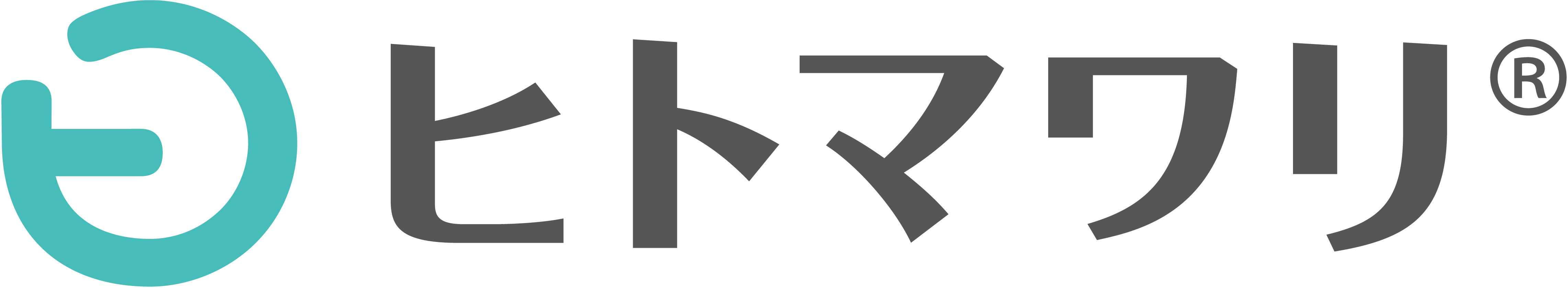












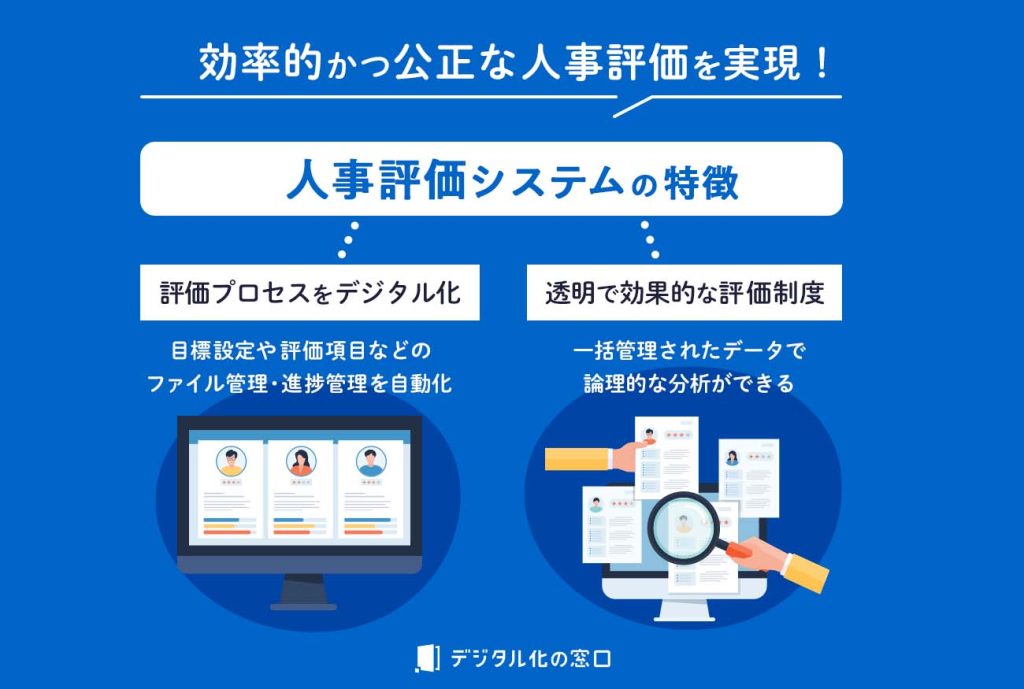

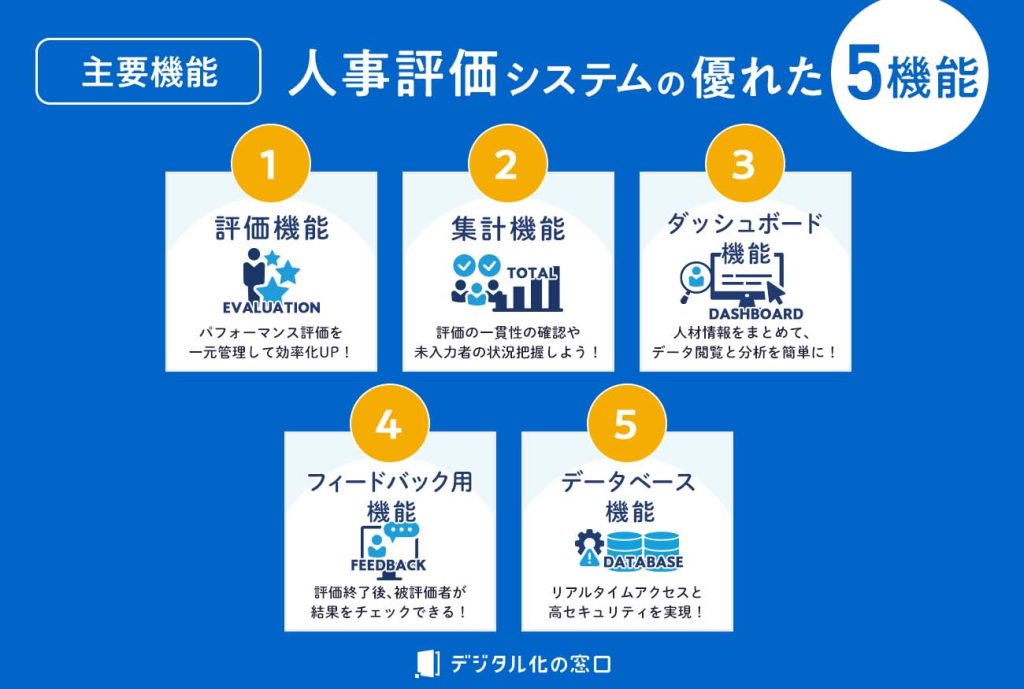

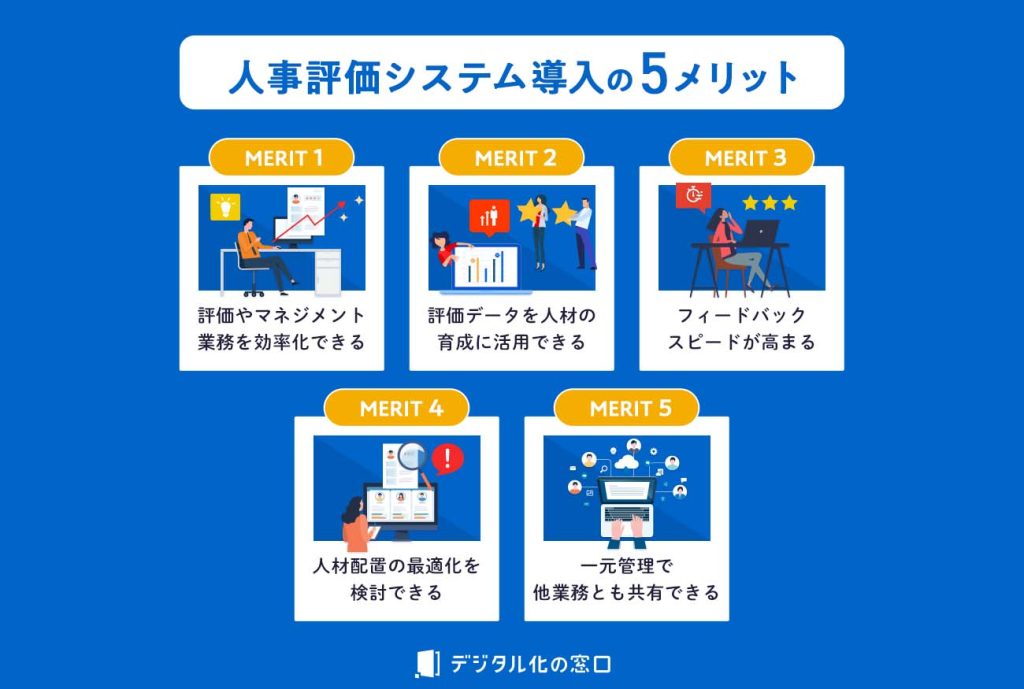
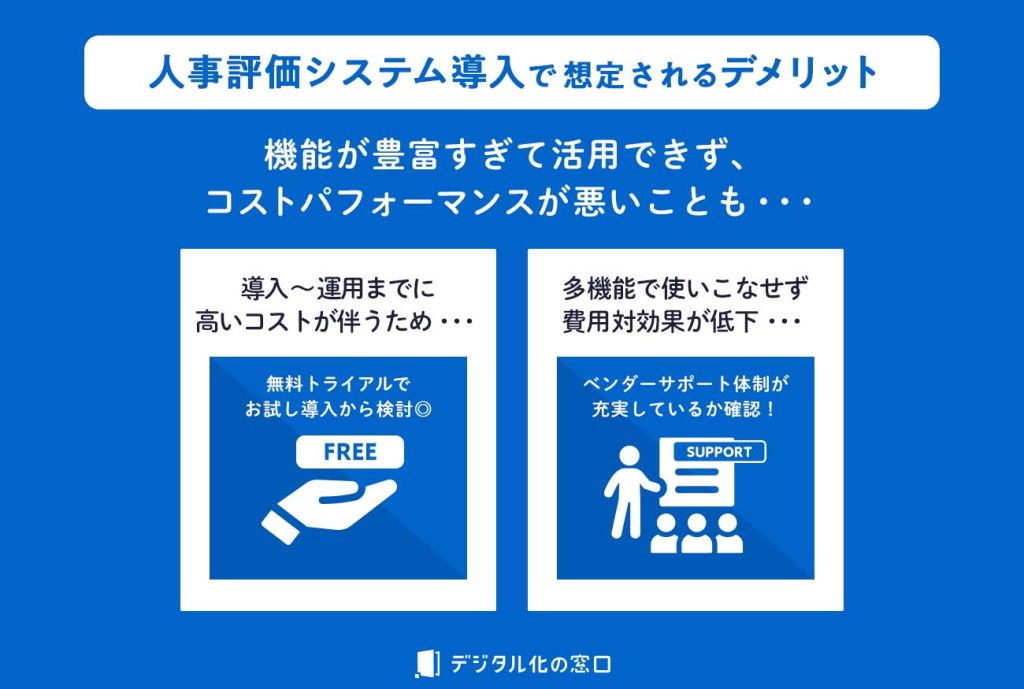







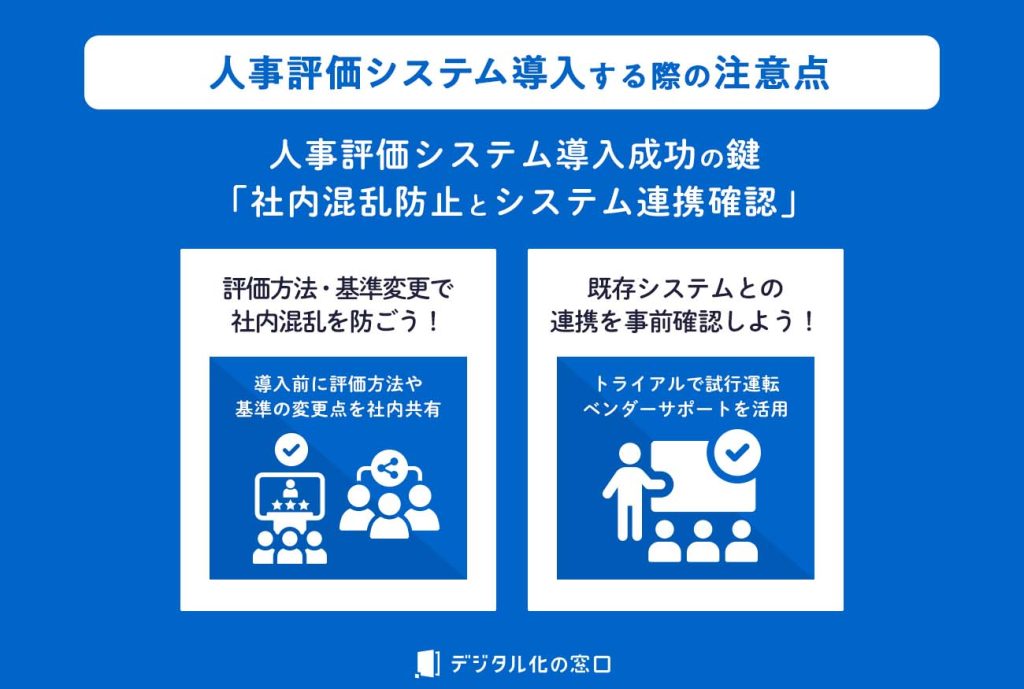
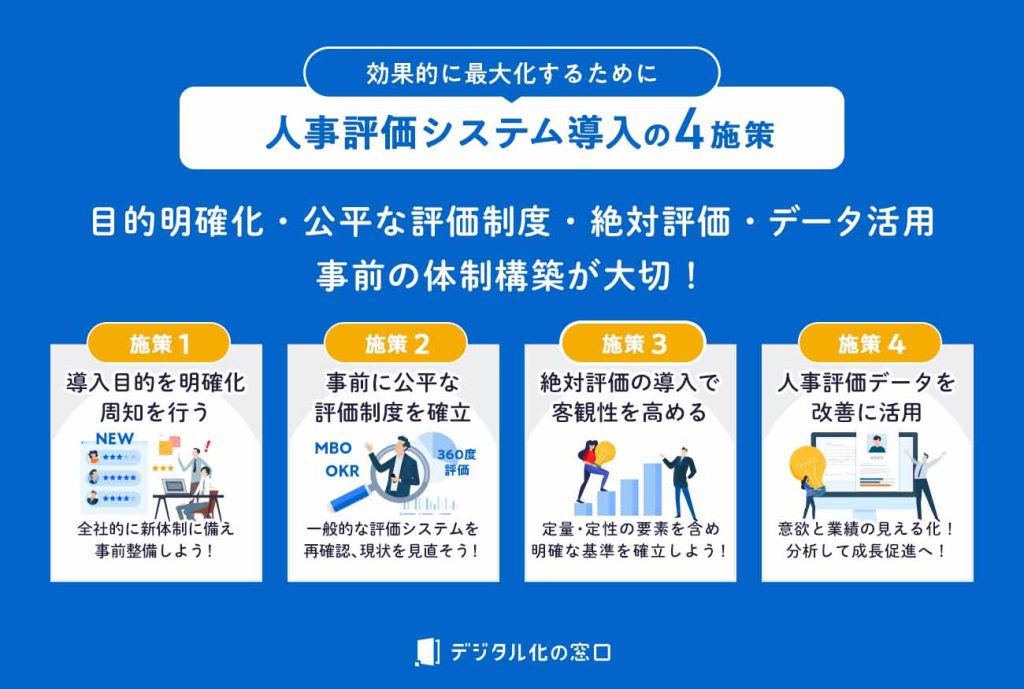









シート内の細かいデータ制御やアクセス制限が難しく、セキュリティの3要素である「可用性」 「機密性」「完全性」を遵守するのが困難な点もデメリットとなります。