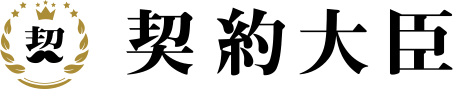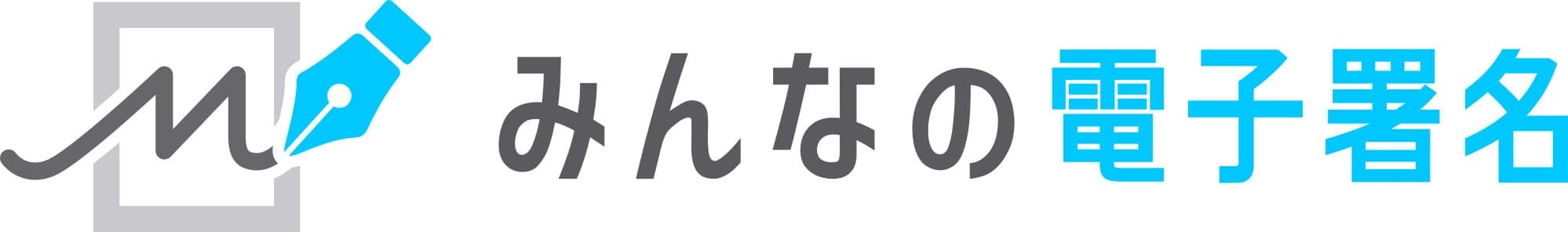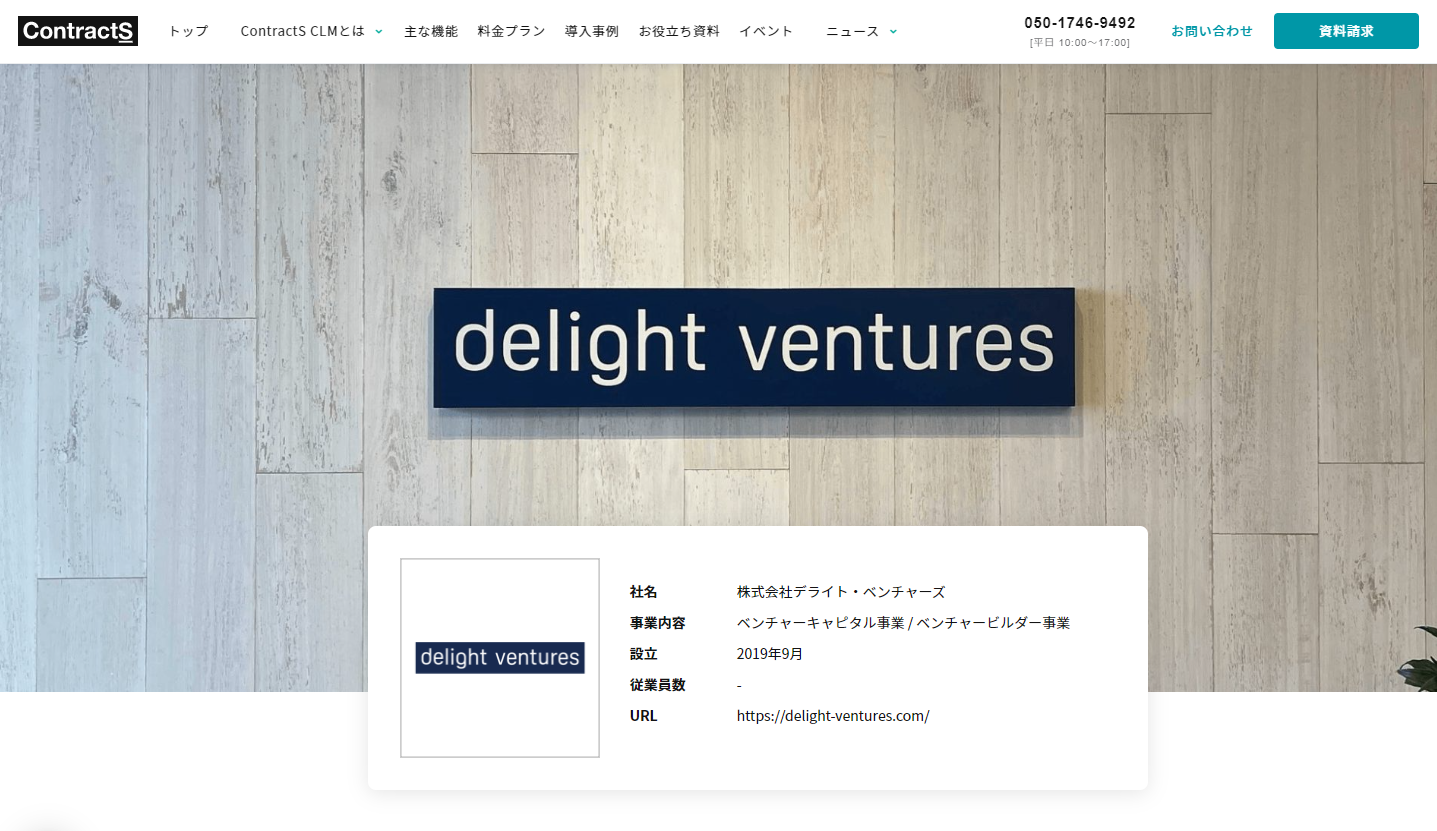「電子契約書」の製品比較表
※税込と表記されている場合を除き、全て税抜価格を記載しています
-
- 製品名
- 料金プラン
- プラン名金額
- 無料トライアル
- 最低利用期間
- 基本的な機能
-
- 法務相談
- 手書きサイン機能
- 外国語対応
- アクセス・参照制限
- ワークフロー設定
- マルチデバイス対応
- 印影登録
- 一括承認
- コメント機能
- 押印機能
- シングルサインオン(SSO)
- SMS送信機能
- 2段階認証
- 一括アップロード
- 操作ログ
- 書類自動入力
- テンプレート登録
- 期限通知
- 差戻し機能
- 外部連携
- サービス資料
- 無料ダウンロード
- ソフト種別
- 推奨環境
- サポート
-
-
-
- 初期費用 要相談 備考
- ご利用人数に応じて金額が変動します。
- 利用料金 要相談 備考
- ご利用人数に応じて金額が変動します。
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 料金 要相談
- 制限なし
-
-
-
-

- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- Free 0円 備考
- 小規模事業所向けのプランです。アカウント数は1名に限定。まずはお試しならこちらがお薦めなプランです。
- Normal 8,800円(税込)/月額 備考
- 電子契約で良く使われる基本機能はすべて標準装備、アカウントも送信も無制限に利用可能なプランです。
- Enterprise 55,000円~(税込)/月額 備考
- 高度な電子契約サービスを利用したい場合や拡張機能を求める場合にお薦めのプランです。
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- スタータープラン 2,200円(税込)/月額 備考
- 送信件数 10 件/月、ユーザー数 1 名のプランです。
- ベーシックプラン 6,600円(税込)/月額 備考
- 送信件数 50 件/月、ユーザー数無制限のプランです。
利用数No.1でおすすめのプランです。 - プレミアムプラン 9,900円(税込)/月額 備考
- 送信件数 100 件/月、ユーザー数無制限のプランです。
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 料金 要相談
- 12か月~
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 要相談 要相談
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- 無料プラン 0円 備考
- 本格導入に向けて使いやすさを体感したい方におすすめのプランです。毎月の送信数は1通までで、アカウント数は1です。
- Lightプラン 4,980円/月額 備考
- 毎月の送信数が50通までの方におすすめのプランです。アカウント数は1です。
- Light Plusプラン 19,800円/月額 備考
- 文書の一括作成・送信ができ、送信数に上限がないプランです。アカウント数は6です。
- Pro/Pro Plusプラン 50,000円~/月額 備考
- ワークフローで内部統制もしっかりしたプランです。アカウント数は要相談です。
- 1年
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- プラン1 300円/締結1件 備考
- 当事者型【実印版】締結料です。3件/月まで無料です。別途、電子証明書発行料が発生します。
- プラン2 100円/送信1件 備考
- 立会人型・事業者署名型【認印版】送信料です。10件/月まで無料です。
- プラン3 10,000円/月額 備考
- PDFが添付された文書データ管理料です。左記は5,000件ごとの料金です。累計10件まで無料です。
- 最低利用期間の設定はありません
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円
- 月額基本料金 22,000円(税込)/月額
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- 月額基本料 0円
- 文書保管 11円(税込)/1文書 備考
- 1年以上経過した文書の保管料金です。50文書単位でのご利用となります。
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談 備考
- プランによって変動いたします。
- Standard 100 要相談 備考
- アカウント数は100、年間契約数は300件までとなっております。
- Standard 300 要相談 備考
- アカウント数は300、年間契約数は600件までとなっております。
- Standard 500 要相談 備考
- アカウント数は500、年間契約数は900件までとなっております。
- Professional 要相談 備考
- アカウント数、年間契約数は要お見積りです。
- 1年
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- Acrobat Standard (個人版) 1,518円(税込)/月額 備考
- 電子サインと基本的なPDFツールでシンプルな文書管理を実現します。
- Acrobat Pro (個人版) 1,980円(税込)/月額 備考
- すべての変換・編集機能、高度な保護、強力な電子サイン機能を備えた包括的なPDFソリューションです。
- Acrobat Standard (法人版) 1,848円(税込)/月額 備考
- 電子サインと基本的なPDFツールでシンプルな文書管理を実現します。
- Acrobat Pro (法人版) 2,380円(税込)/月額 備考
- すべての変換・編集機能、高度な保護、強力な電子サイン機能を備えた包括的なPDFソリューションです。
- Acrobat Sign Solutions (法人版) 要相談 備考
- アプリケーション連携、APIなどを利用してビジネスの拡大を目指すチームに最適なプランです。
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ iOSアプリ Androidアプリ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- お試しフリープラン 0円
- 契約印&実印プラン (立会人型&当事者型) 9,680円(税込)円/月 備考
- 契約印タイプ(立会人型)110円 / 件、実印タイプ(当事者型)330円 / 件で利用できます。セキュリティパックは55,000円(税込) / 月額です。
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ iOSアプリ Androidアプリ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- パーソナルミニ 800円/月額 備考
- 個人向けのプランです。
副業などで確定申告をする必要のある方におすすめです。 - パーソナル 980円/月額 備考
- 個人向けのプランです。
自営業、個人事業主として
確定申告をする必要のある方におすすめです。
1か月無料となっております。 - パーソナルプラス 2,980円/月額 備考
- 個人向けのプランです。
確定申告の操作が不安で
電話サポートを受けたい方におすすめです。 - 小規模事業者向け スモールビジネス 2,980円/月額 備考
- 法人向け(30名以下の方)のプランです。
部門管理が不要な企業や、請求業務の少ない小規模事業者向けプランです。 - 中小企業向け ビジネス 4,980円/月額 備考
- 法人向け(30名以下の方)のプランです。
バックオフィス業務全般を効率化したい、中小企業向けプランです。 - IPO準備・中堅〜上場企業向け 要相談 備考
- 法人向け(30名以下の方)のプランです。
別途ご案内いたします。 - 小規模〜中小企業向け 機能制限版 2,980円~/月額 備考
- 法人向け(31名以上の方)のプランです。
お得に電子契約に対応したプランです。 - IPO準備・中堅〜上場企業向け フル機能版 要相談 備考
- 法人向け(31名以上の方)のプランです。
書類の一元管理・システム連携に対応プランです。
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- Light 11,000円(税込)/月額 備考
- 個人事業主や少人数の企業向けプランです。
送信件数ごとに別途220円(税込)かかります。 - Corporate 30,800円(税込)/月額 備考
- 電子契約・書類管理の機能を備えた一般企業向け標準プランです。
送信件数ごとに別途220円(税込)かかります。 - Business 要相談 備考
- 内部統制・セキュリティを強化する機能を備えたプランです。
送信件数ごとの料金は要相談です。 - Enterprise 要相談 備考
- 全社利用を想定された企業向けの書類管理機能を備えたプランです。
送信件数ごとの料金は要相談です。
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- Personal (個人向け) 1,100円/月額
- Standard (企業向け) 2,800円/月額
- Business Pro (企業向け) 4,400円/月額
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- フリープラン 0円 備考
- まずはお試しを希望される方向けのプランです。
- シルバープラン 10,000円~/月額 備考
- 電子契約機能のみでスタートしたい方向けのプランです。
- ゴールドプラン 30,000円~/月額 備考
- 電子契約機能だけでなく
保管機能を利用したい方向けのプランです。
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
価格や製品機能など、見やすい一覧表から、気になる製品をまとめてチェック!