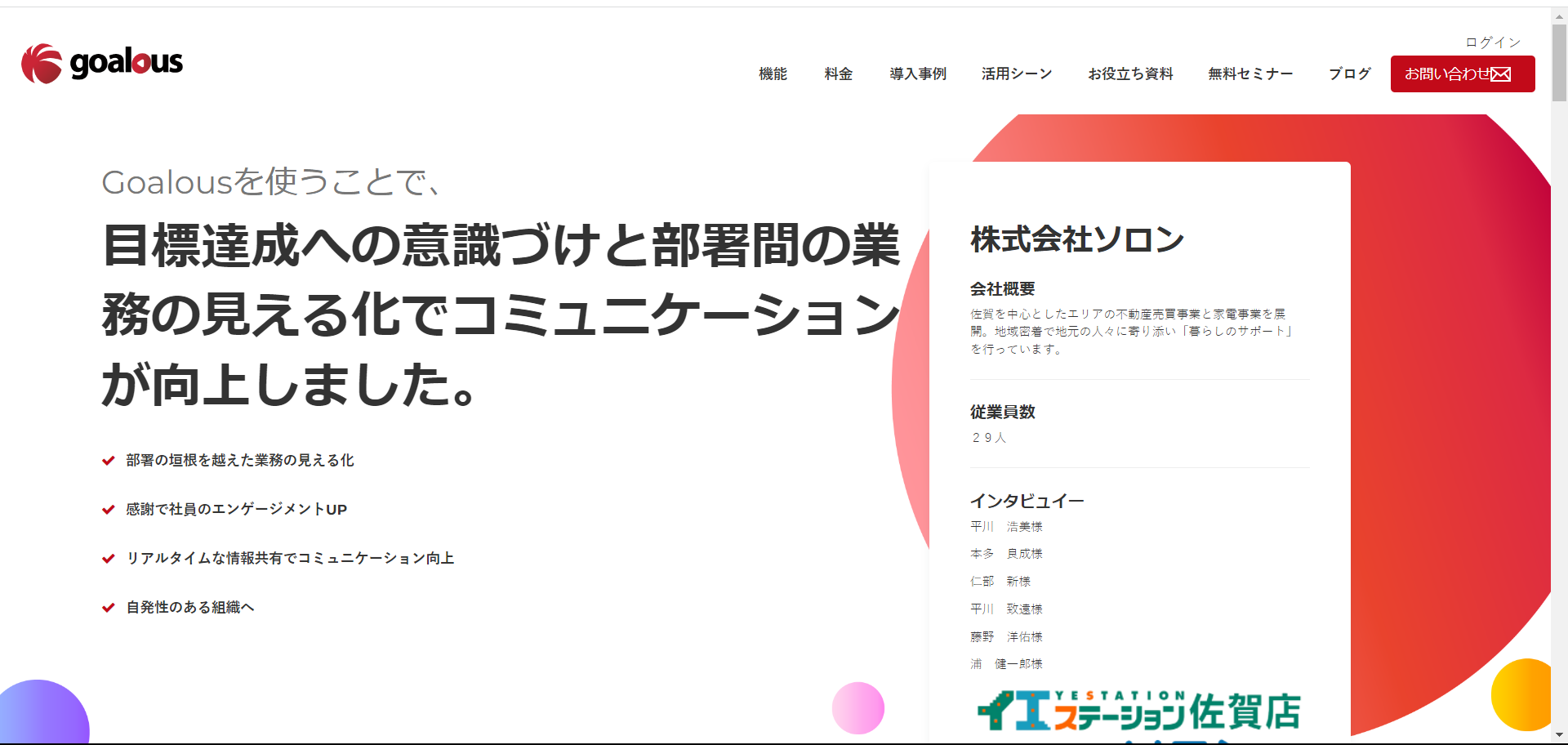「OKRツール」の製品比較表
※税込と表記されている場合を除き、全て税抜価格を記載しています
-
- 製品名
- 料金プラン
- プラン名金額
- 無料トライアル
- 最低利用期間
- 基本的な機能
-
- 無料プランあり
- 称賛機能
- 国内メーカー
- slack連携
- 昇格判定機能
- 昇給・賞与算定機能
- ニュースフィード
- チャットボット自動質問
- スマホから日報可
- 1on1
- シングルサインオン
- Gmail連携
- 関連業務抽出
- 動画投稿
- 人事・給与システム連携
- ランキング表示
- 基幹システム連携
- 業務の結び付き表示
- Microsoft Teams連携
- 導入サポートあり
- Chatwork連携
- サービス資料
- 無料ダウンロード
- ソフト種別
- 推奨環境
- サポート
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- 1on1プラン 700円/月額/1人 備考
- 1on1機能・データ分析/伴走支援・導入支援をご利用できます。
- フルパッケージプラン 1,500円/月額/1人 備考
- 1on1プランの機能に加えて、目標管理機能・フィードバック(評価)機能をご利用できます。
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- スタンダードプラン 1,500円/月額 備考
- 中小規模の組織やチームのOKRをクラウドで運用することができます。
- 運用サポートプラン 要相談 備考
- 100名以上での大規模な組織での運用を専門スタッフがサポートいたします。
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- 1~3人 無料
- 4人~ 要相談 備考
- ユーザー数によって価格は変動いたします。
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト パッケージ型ソフト
- Windowsアプリ iOSアプリ Androidアプリ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 基本利用料金 30,000円~/月額
- フィードバック機能 500円/ユーザー/月額
- サークル機能 500円/ユーザー/月額
- メッセージ機能 300円/ユーザー/月額
- 翻訳機能 300円/ユーザー/月額
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- スイートプラン 1,500円/ユーザー/月額 備考
- スイートプランは人事施策が決まっており、運用していく中でツールとして、HiManagerを利用したい企業様に適切です。
- コンサルティングプラン 2,000円/ユーザー/月額 備考
- コンサルティングプランはOKRや1on1を実施したことがなく組織の風土や文化を変えていきたいと考えている企業様に適切です。
- プレミアムプラン 3,000円/ユーザー/月額 備考
- プレミアムプランはコンサルティングプランで実施する内容に加えて、評価制度を変えていきたい企業様に適切です。
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
価格や製品機能など、見やすい一覧表から、気になる製品をまとめてチェック!