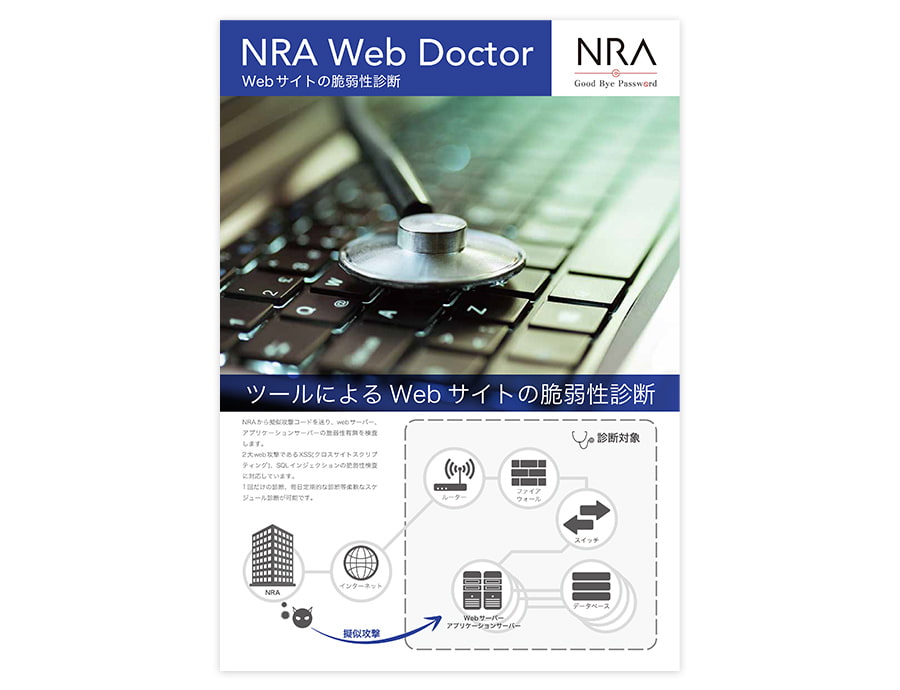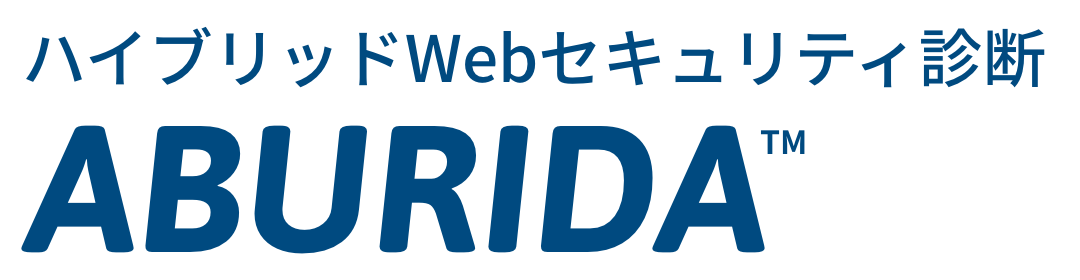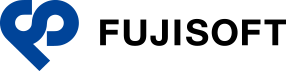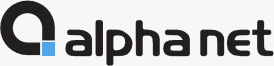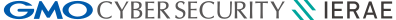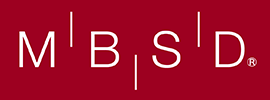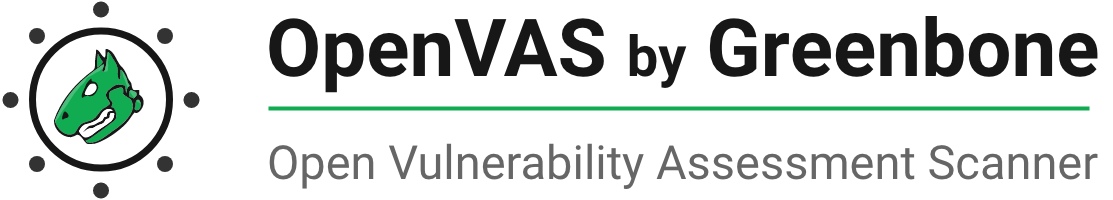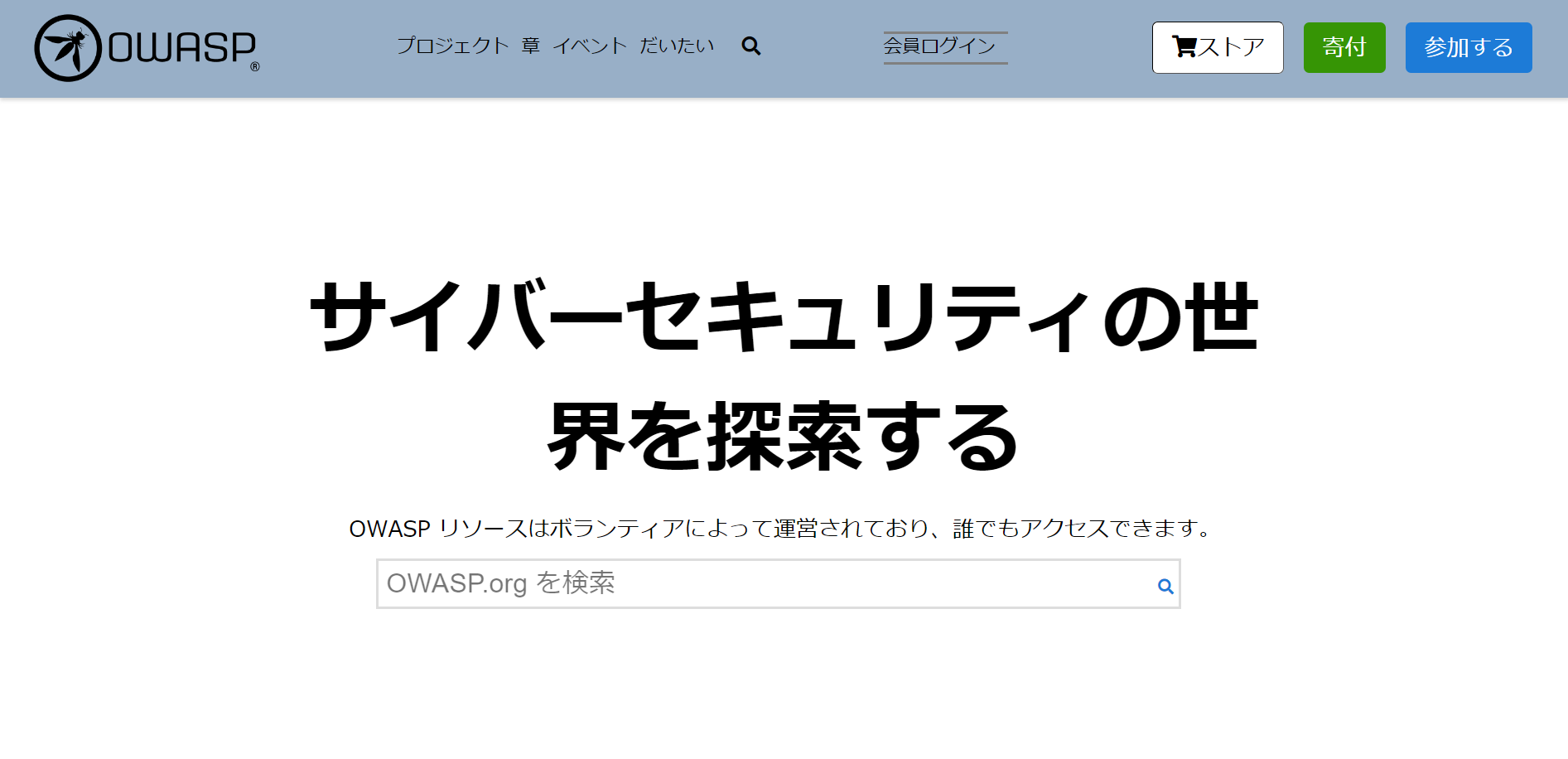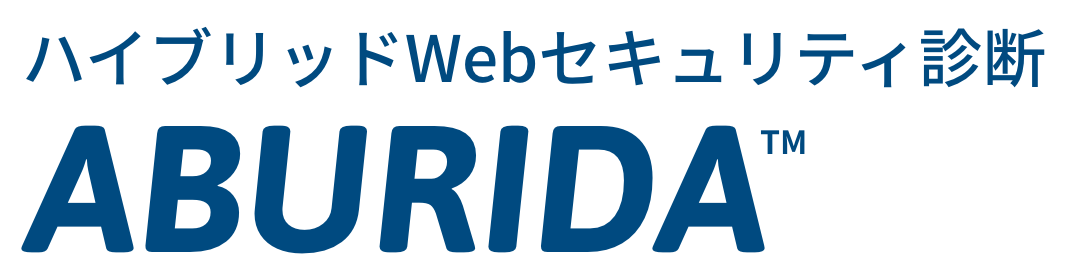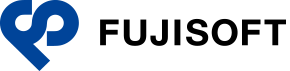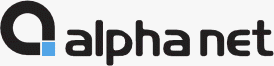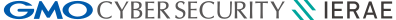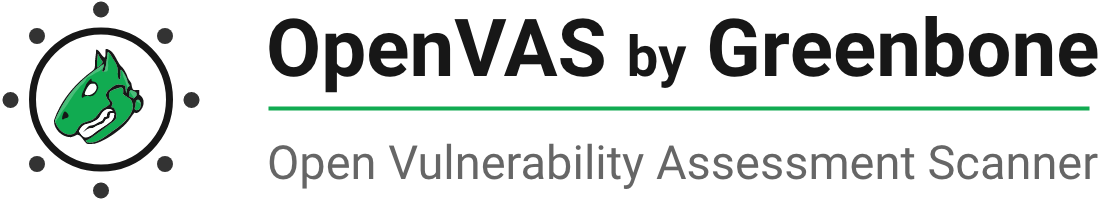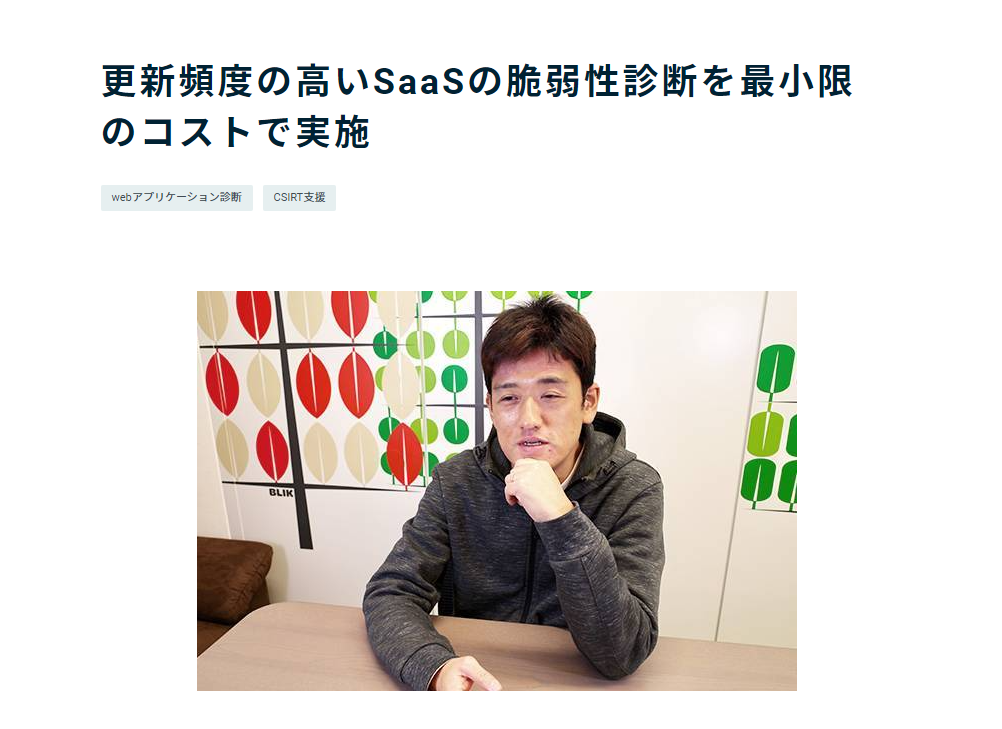「脆弱性診断ツール/サービス」の製品比較表
※税込と表記されている場合を除き、全て税抜価格を記載しています
-
- 製品名
- 料金プラン
- プラン名金額
- 無料トライアル
- 最低利用期間
- 基本的な機能
-
- クロスサイトスクリプティング
- ドメイン設定
- クラウド診断
- プラットフォーム診断
- スマホアプリ(iOS・Android)診断
- Webアプリケーション診断
- デスクトップアプリ診断
- SSL設定
- HttpOnly属性が付与されていないCookieの利用
- X-Frame-Optionsヘッダの未設定
- SQLインジェクション
- サーバ設定
- X-Content-Type-Optionsヘッダの未設定
- URL設定
- アプリケーションエラーの開示
- オートコンプリート機能有効化
- ヘッダインジェクション
- オープンリダイレクタ
- グラスボックス診断
- サービス資料
- 無料ダウンロード
- ソフト種別
- 推奨環境
- サポート
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- 制限なし
-
-
-
- なし
- なし
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談 備考
- 予算に応じてLight・Standard・Advancedの3つのコースがあります。
- 制限なし
-
-
-
- なし
- なし
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- 制限なし
-
-
-
- なし
- PCブラウザ Windowsアプリ Macアプリ iOSアプリ Androidアプリ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- 制限なし
-
-
-
- なし
- なし
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- One Shotプラン お見積り 備考
- まずは1サイト診断したい方
- Businessプラン お見積り 備考
- 診断を内製化したい方
- 15日
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- プロフェッショナル 85,000円 備考
- ドメイン数:1~9個
- プロフェッショナル 118,400円 備考
- ドメイン数:100~199個
- プロフェッショナル 160,000円 備考
- ドメイン数:1000~2000個
- エキスパート 85,000円 備考
- ドメイン数:1~9個
- エキスパート 118,400円 備考
- ドメイン数:100~199個
- エキスパート 160,000円 備考
- ドメイン数:1000~2000個
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- 利用料金 0円 備考
- オープンソースのソフトウェアです。
- 制限なし
-
-
-
- パッケージ型ソフト
- なし
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- お試しプラン 90,000円(税込) 備考
- 1社1回限りです。3リクエストまで。無料の再診断がありますが、診断結果が「危険度Medium」以上の項目のみとなります。
- スタンダードプラン 440,000円(税込) 備考
- 10リクエストまで。無料の再診断がありますが、診断結果が「危険度Medium」以上の項目のみとなります。
- ボリュームプラン 1,408,000円(税込) 備考
- 50リクエストまで。無料の再診断がありますが、診断結果が「危険度Medium」以上の項目のみとなります。
- 制限なし
-
-
-
- なし
- なし
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- エクスプレス診断 400,000円 備考
- Webアプリケーション診断は、10リクエストまたは6APIまでです。報告会実施の場合別途10万円/回が必要です。再診断は無償です。
- エキスパート診断 1,280,000円 備考
- Webアプリケーション診断は、50リクエストまたは25APIまでです。報告会実施の場合別途15万円/回が必要です。再診断は無償です。
- プラットフォーム診断 250,000円 備考
- プラットフォーム診断は、3 IPまたは3FQDNまでです。報告会実施の場合別途15万円/回が必要です。再診断は無償です。
- エクスプレス診断 +プラットフォーム診断 550,000円 備考
- Webアプリケーション診断は、10リクエストまたは6APIまでです。プラットフォーム診断は、3 IPまたは3FQDNまでです。報告会実施の場合別途10万円/回が必要です。再診断は無償です。
- エキスパート診断 +プラットフォーム診断 1,430,000円 備考
- Webアプリケーション診断は、50リクエストまたは25APIまでです。プラットフォーム診断は、3 IPまたは3FQDNまでです。報告会実施の場合別途15万円/回が必要です。再診断は無償です。
- ペネトレーションテスト 要相談
- 制限なし
-
-
-
- なし
- なし
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- デベロッパーライセンス 要相談 備考
- 自社で開発もしくは運営するWebアプリケーションの診断に利用する場合のライセンスです。各販売代理店から購入できます。
- オーディターライセンス 要相談 備考
- Vexを利用した脆弱性検査サービスを提供する場合には、こちらの契約が必要です。
- 制限なし
-
-
-
- パッケージ型ソフト
- なし
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- 新規 300,000円 備考
- 期間限定で99,000円~にて提供の場合もあります。診断方法は遠隔で、診断対象は25ページまでです。
- フォローアップ診断 80,000円 備考
- 再診断メニューです。本診断のレポート提出後、20日以内までの依頼を対象とします。診断方法は遠隔で、診断対象は該当箇所だけです。
- 個別対応(ReCoVASプロ) 500,000円~ 備考
- 内容は要相談です。
- 制限なし
-
-
-
- なし
- なし
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- プラン 要相談
- 制限なし
-
-
-
- なし
- なし
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- プラン 要相談
- 制限なし
-
-
-
- なし
- なし
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- Webアプリケーション診断(手動) 240,000円~ 備考
- 1リクエストで、報告書を含みます。
- スマホWebAPI診断 250,000円~ 備考
- 1リクエスト当たりの料金で、(報告書を含みます。Androidのみの対応となります。
- おまかせプラン 要相談 備考
- 予算等に合わせて対象数を決定いただき、その数を上限にエンジニアが診断対象を選定し、診断を行うサービスです。
- 制限なし
-
-
-
- なし
- なし
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- nessus essentials $0 備考
- 教育関係者や、サイバーセキュリティのキャリアを始めようとしている学生、個人に理想的なサービスです。 IP アドレスを 16 個までスキャン可能です。
- nessus professional $3,729/年額 備考
- コンサルタント、ペンテスター、セキュリティ担当者向けのサービスです。サブスクリプションでスキャナー単位のライセンスです。
- 1年
-
-
-
- パッケージ型ソフト
- なし
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- プラン1 $6,995/年額 備考
- Burp Suite Enterprise EditionのStarterプラン。自動化されたスケーラブルなWeb脆弱性スキャンを可能にします。5の同時スキャンができます。
- プラン2 $ 14,480/年額 備考
- Burp Suite Enterprise EditionのGrowプラン。自動化されたスケーラブルなWeb脆弱性スキャンを可能にします。20の同時スキャンができます。
- プラン3 $ 29,450~/年額 備考
- Burp Suite Enterprise EditionのAccelerateプラン。自動化されたスケーラブルなWeb脆弱性スキャンを可能にします。50以上の同時スキャンができます。
- プラン4 $ 399/年額 備考
- Burp Suite Professionalです。主要なWebセキュリティおよび侵入テストツールキットです。
- 1年
-
-
-
- パッケージ型ソフト
- なし
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- 無料診断 0円 備考
- 診断回数1回、リスク件数のみ表示です。
- ライトプラン 10,000円/月額 備考
- 1ドメインあたりの料金で、診断ページ数 は500ページ以下です。毎日診断実施可能で、リスク件数、発生している脆弱性の内容・対策方法の案内があります。
- スタンダードプラン 17,000円/月額 備考
- 1ドメインあたりの料金で、診断ページ数 は1,000ページ以下です。毎日診断実施可能で、リスク件数、発生している脆弱性の内容・対策方法の案内があります。
- ビジネスプラン 24,000円/月額 備考
- 1ドメインあたりの料金で、診断ページ数 は1,500ページ以下です。毎日診断実施可能で、リスク件数、発生している脆弱性の内容・対策方法の案内があります。
- エンタープライズプラン 要相談 備考
- 診断ページ数 は1,501ページ以上です。毎日診断実施可能で、リスク件数、発生している脆弱性の内容・対策方法の案内があります。
- 最低利用期間は1年間(有料版)
-
-
-
- パッケージ型ソフト
- なし
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- プラン 要相談
- 制限なし
-
-
-
- なし
- なし
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- 要相談 要相談
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- なし
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 料金 要相談
- 制限なし
-
-
-
- なし
- なし
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 要相談 要相談
- 制限なし
-
-
-
- なし
- なし
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- ベーシックプラン 49,800円/月額 備考
- 1アプリケーションあたりの料金。手軽に続けられる高コストパフォーマンスプランです。
- 1年
-
-
-
- クラウド型ソフト
- なし
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- Vuls OSS 0円 備考
- 脆弱性をスキャンします。
- FutureVuls standard 4,000円/月額 備考
- 脆弱性を管理します。1台の料金です。
- 複数システムの脆弱性を横断管理 要相談 備考
- 複数システムの脆弱性を横断管理します。最小100台からのプランです。
- 1ヵ月
-
-
-
- パッケージ型ソフト
- なし
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- プラン 0円 備考
- オープンソースのソフトウェアです。Greenboneのクラウドサービスなどの料金はお問い合わせください。
- 制限なし
-
-
-
- パッケージ型ソフト
- なし
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談 備考
- 問合わせの後個別見積
- 制限なし
-
-
-
- なし
- なし
- 電話 / メール / チャット /
-
価格や製品機能など、見やすい一覧表から、気になる製品をまとめてチェック!