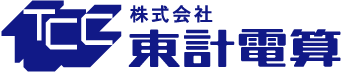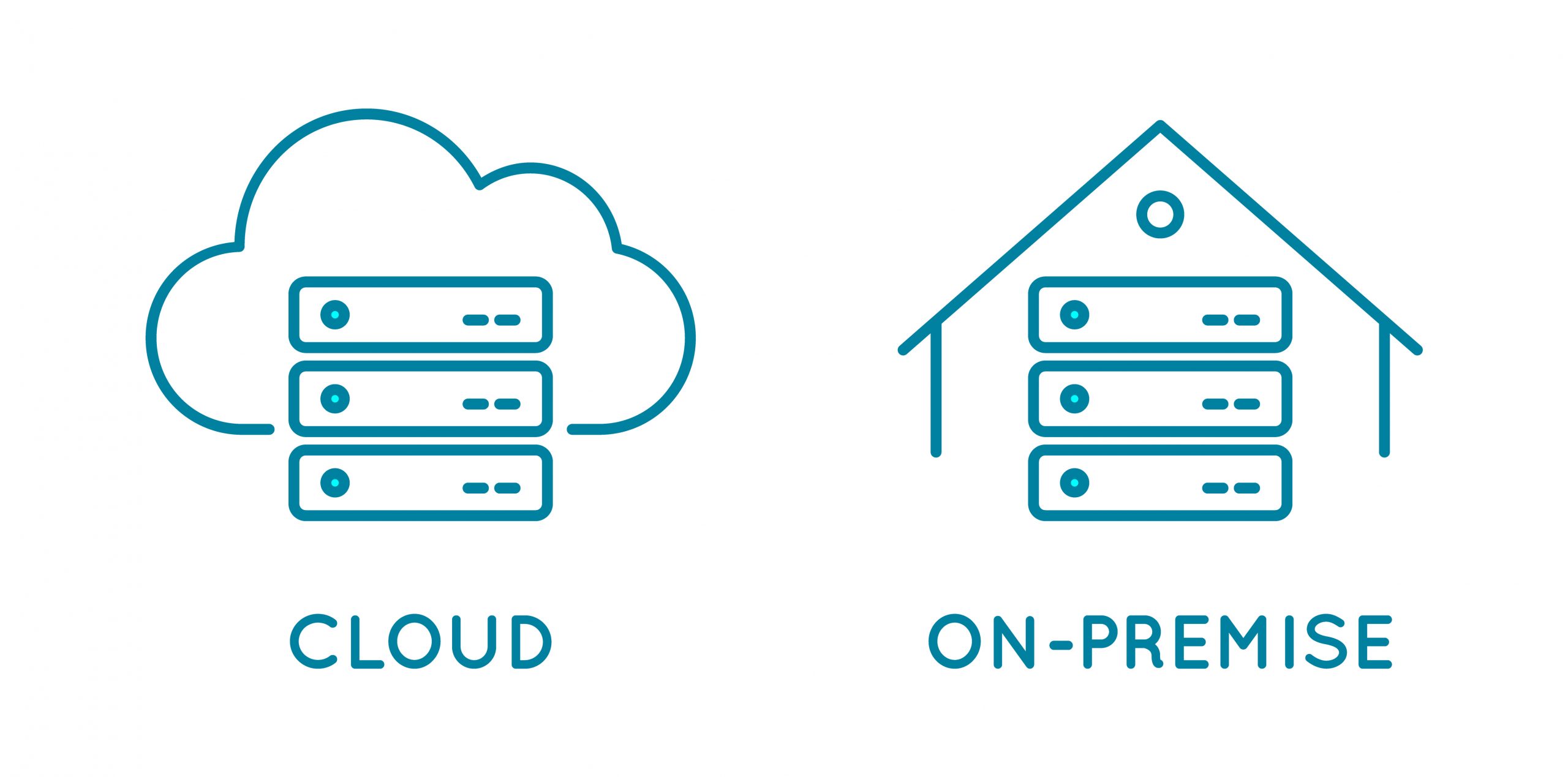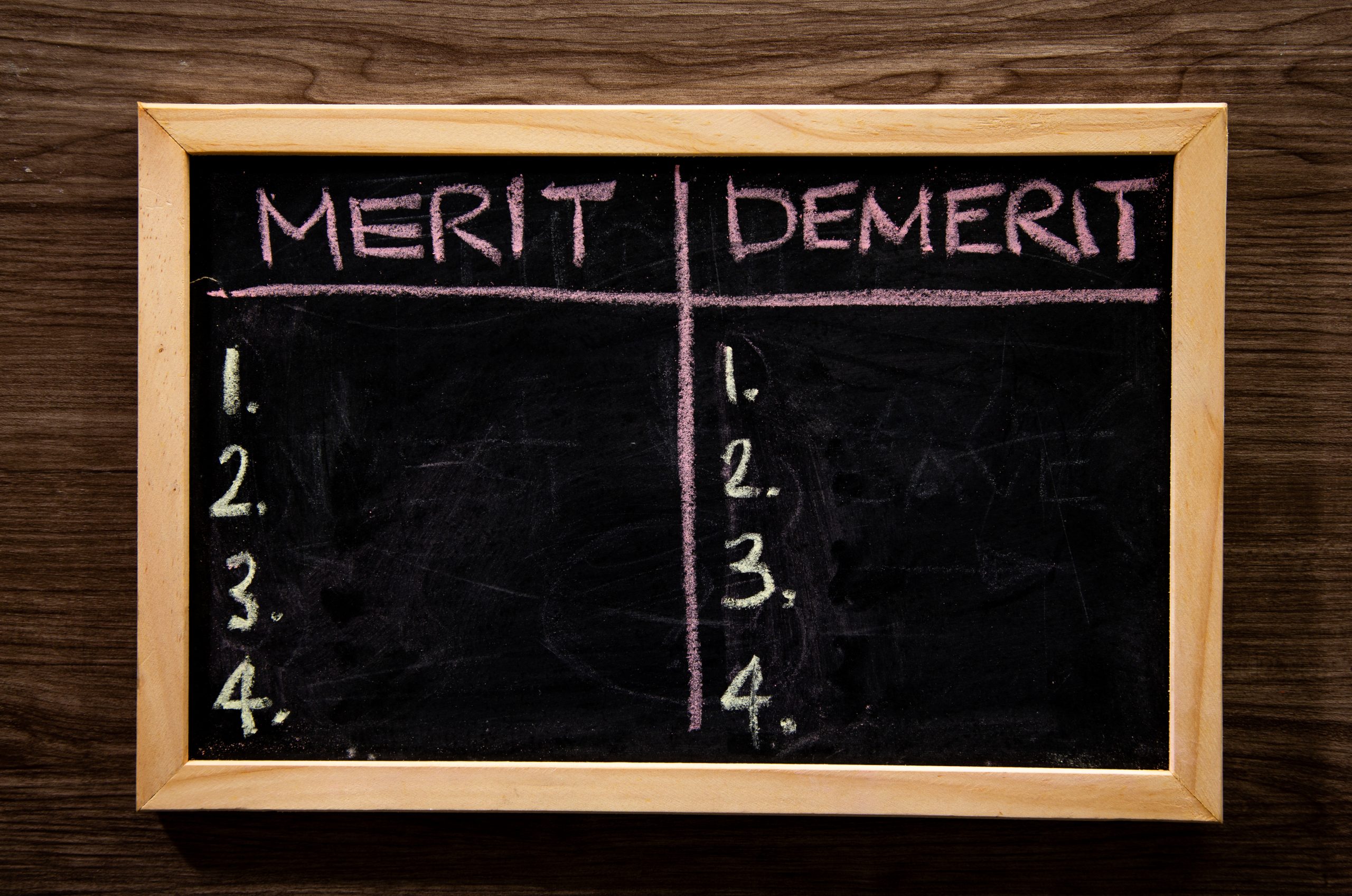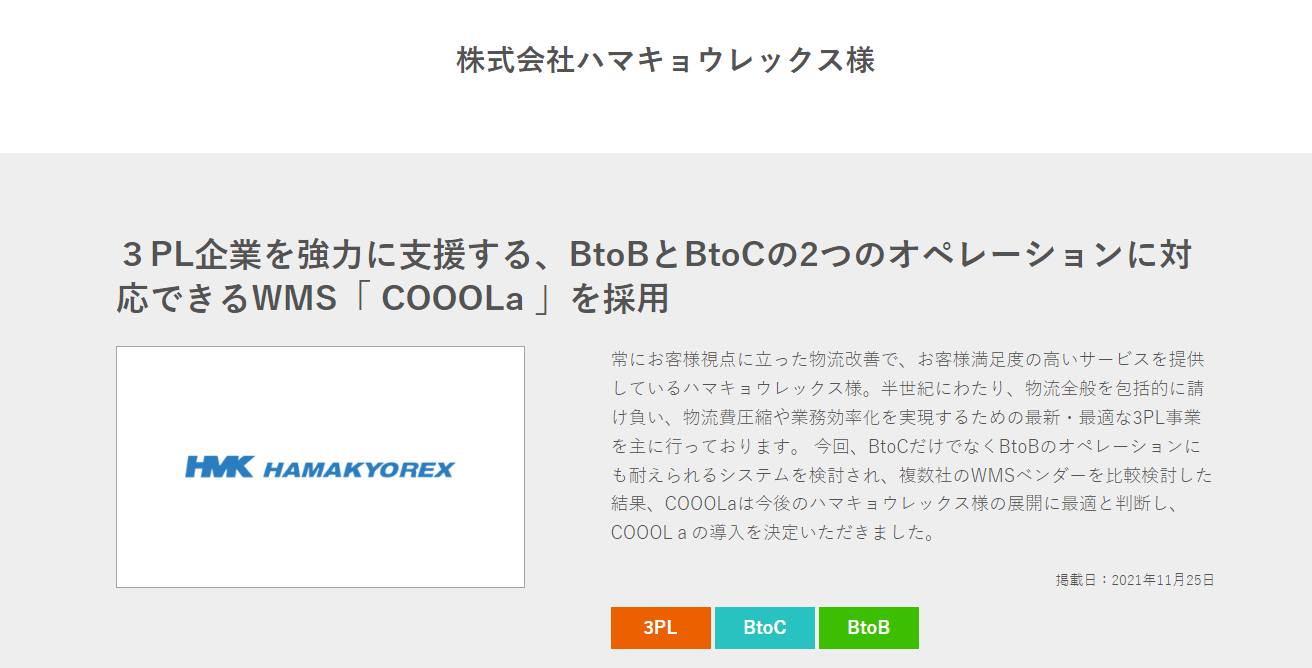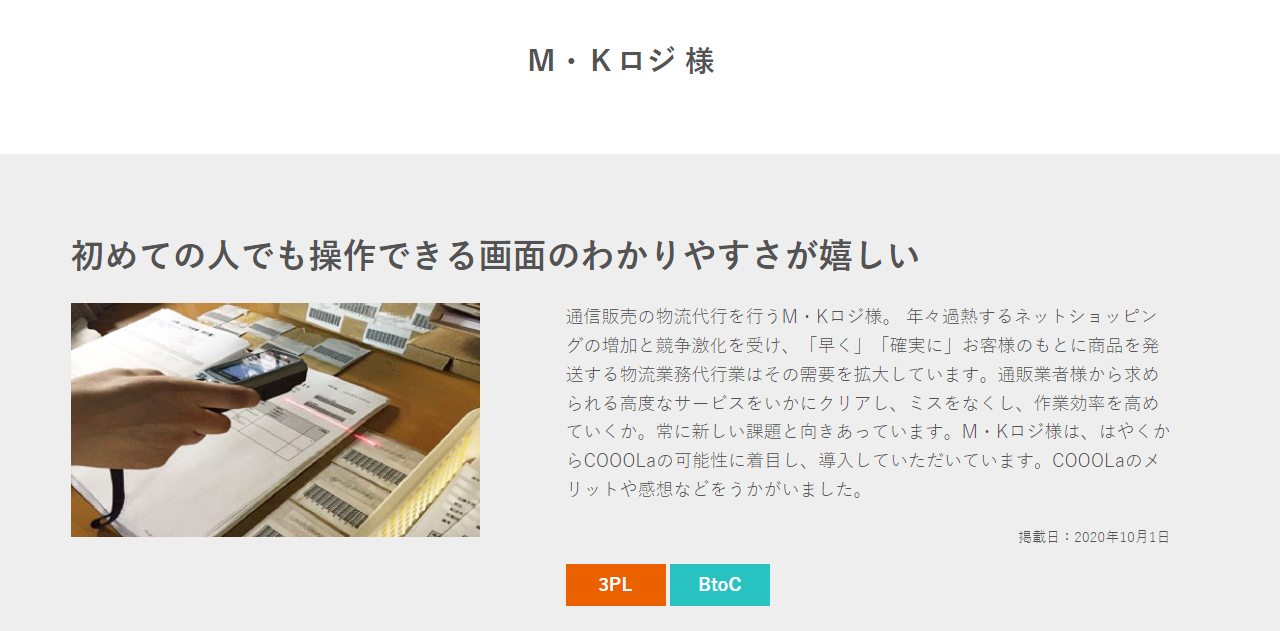「物流管理システム」の製品比較表
※税込と表記されている場合を除き、全て税抜価格を記載しています
-
- 製品名
- 料金プラン
- プラン名金額
- 無料トライアル
- 最低利用期間
- 基本的な機能
-
- マルチデバイス
- 外国語表示
- 入荷管理
- 棚卸管理
- 在庫管理
- 出荷管理
- 配車管理
- 作業帳票出力
- 運賃管理
- 進捗管理
- 実績管理
- マスタ管理
- サービス資料
- 無料ダウンロード
- ソフト種別
- 推奨環境
- サポート
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- 不明
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- 不明
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト オンプレミス型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト オンプレミス型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- 基本利用料 90,000円~/月額 備考
- 1~5アカウントまでの料金です。追加アカウント料金は1アカウントにつき5,000円/月額です。追加ショップ・荷主料は50,000円/月額です。
- 1ヵ月
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ iOSアプリ Androidアプリ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 要相談 要相談
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 別途お問い合わせ 別途お問い合わせ
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト オンプレミス型ソフト パッケージ型ソフト
- Windowsアプリ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 別途お問い合わせ 別途お問い合わせ
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
価格や製品機能など、見やすい一覧表から、気になる製品をまとめてチェック!