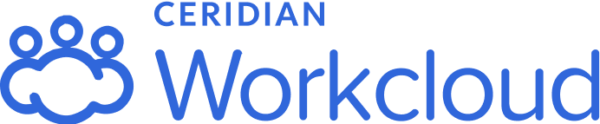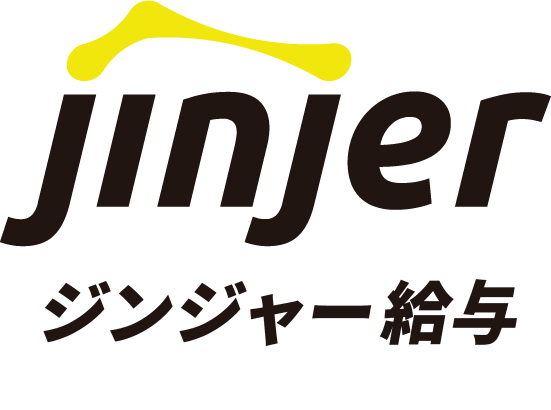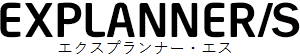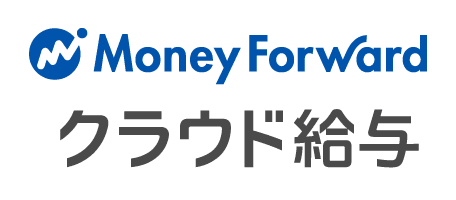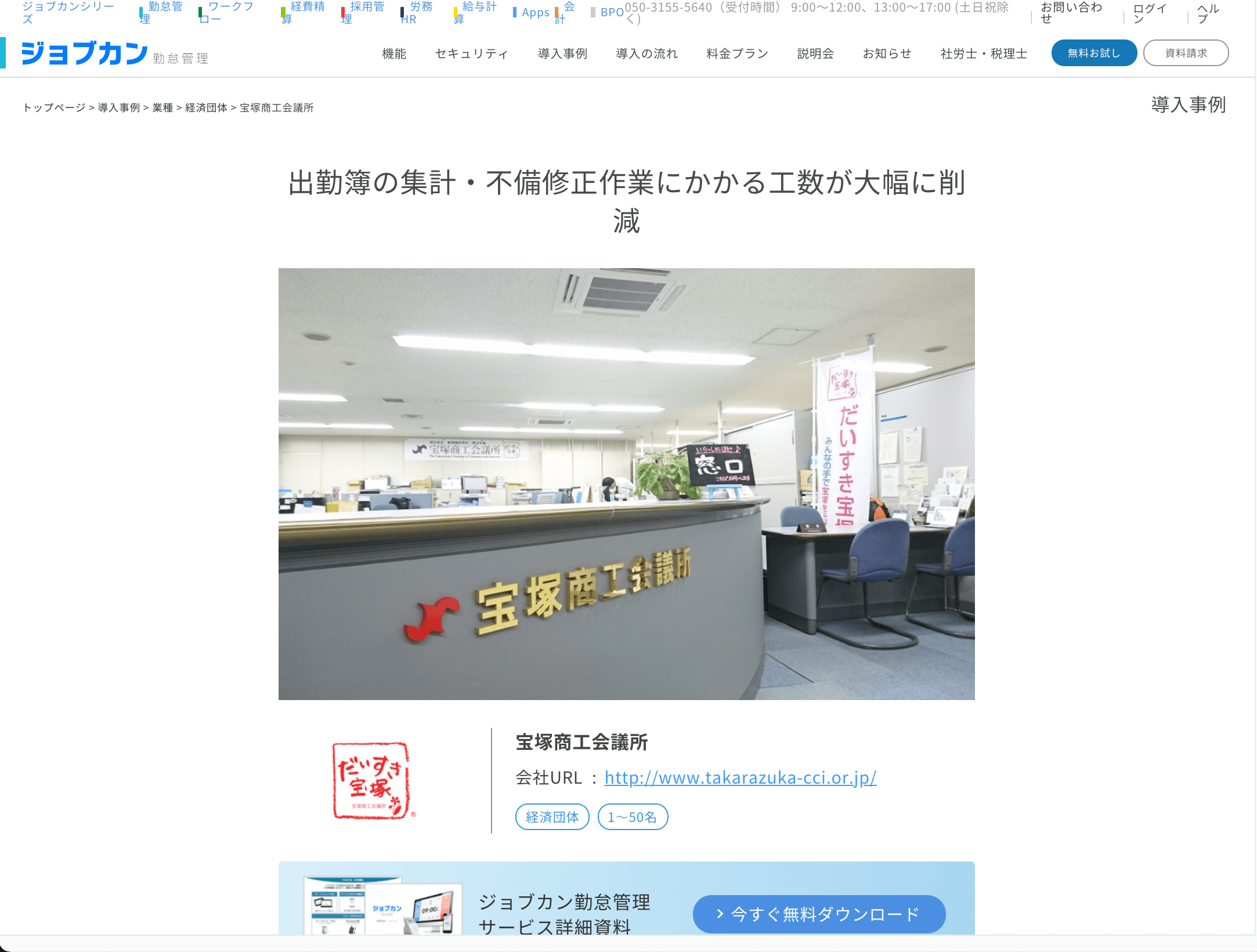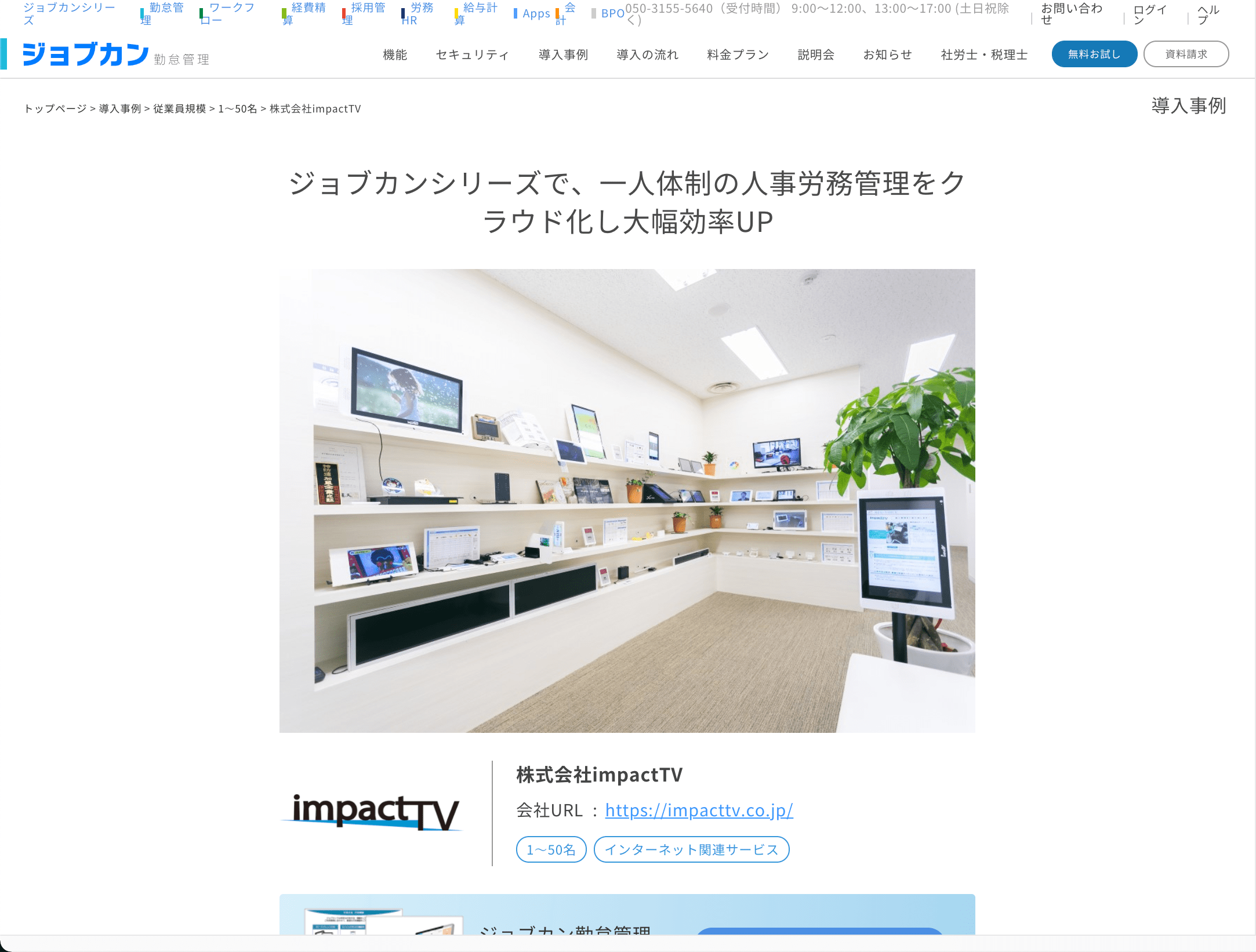「給与計算ソフト」の製品比較表
※税込と表記されている場合を除き、全て税抜価格を記載しています
-
- 製品名
- 料金プラン
- プラン名金額
- 無料トライアル
- 最低利用期間
- 基本的な機能
-
- office連携
- 自動計算
- 年末調整
- 源泉徴収票
- 社会保険対応
- マイナンバー管理
- 給与明細
- 賞与明細
- 有給計算
- 勤怠データ入力
- タイムレコーダー連携
- 会計データ連携
- office連携
- ワークフロー管理
- 自動アップデート
- サービス資料
- 無料ダウンロード
- ソフト種別
- 推奨環境
- サポート
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ iOSアプリ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 基本サービス 12,000円/月額 備考
- 管理者1ID、利用者1ID付の料金です。1会社の管理付きで、対応従業員数は50名です。
利用者追加オプション、従業員追加オプション、その他さまざまなオプションがあります。
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 30,000円
- e-Tax・eLTAX・e-Gov対応! 給与ワークス 10,000円~/月額 備考
- 勤怠管理・給与計算・賞与計算・年末調整・賃金台帳・社会保険に対応しています。
給与のオプション(月額):限定ユーザ(給与明細) 300円/1ID
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 利用料金 要相談
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 従業員データベース 無料
- 料金 月額500円〜/人
- 12か月~
-
-
-
-

- クラウド型ソフト
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 要相談 要相談 備考
- 料金プランにつきましては、公式サイト https://www.works-hi.co.jp/products/payroll からお問い合わせください。
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 要相談 要相談 備考
- 利用者の状況、給与支給対象者数や導入サービス内容により金額が異なります。詳細は公式サイトのお問い合わせフォームよりご相談ください。
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- パッケージ価格 20万円~ 備考
- 最低価格は、1ユーザライセンス利用時です。パッケージ価格はご利用者数により「追加ユーザライセンス」分の価格追加が必要となります。利用形態により製品構成が異なるので詳細はお問い合わせが必要です。
- 制限なし
-
-
-
- パッケージ型ソフト
- Windowsアプリ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- 有料版 1,980円/月額
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- セルフプラン 20,000円 備考
- 最初の1年間は無料でご利用できます。
- ベーシックプラン 27,000円 備考
- 最初の1年間は無料でご利用できます。
- トータルプラン 36,700円 備考
- 最初の1年間は半額でご利用できます。
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- パッケージ 27,500円(税込)
- 制限なし
-
-
-
- パッケージ型ソフト
- Windowsアプリ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- PCAクラウド給与 13,860円~(税込)/月額 備考
- 給与計算クラウドサービスを、月額の「利用ソフトとサーバーのライセンス費用」にて利用するプランです。
- PCAサブスク給与 9,900円~(税込)/月額 備考
- 給与計算ソフトをオンプレミスで、月額料金にて利用するプランです。設備を自社構築・運用する場合に最適です。
- PCA給与DX 224,400円~(税込) 備考
- 給与計算ソフトをパッケージソフトとして購入するプランです。設備を自社構築・運用する場合に最適です。
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト オンプレミス型ソフト パッケージ型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- 利用料金 要相談
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト オンプレミス型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- iEシステム 月額 5,500円 (年額 66,000円) 備考
- 初期費用(初年度のみ):0円
従業員数:20 名まで - iAシステム 月額 9,000円 (年額 108,000円) 備考
- 初期費用(初年度のみ):50,000円
従業員数:50 名まで - iBシステム 月額 17,000円 (年額 204,000円) 備考
- 初期費用(初年度のみ):60,000円
従業員数:100 名まで - iSシステム 月額 23,000円 (年額 276,000円) 備考
- 初期費用(初年度のみ):70,000円
従業員数:300 名まで - iSシステム(+社員数拡張) 月額 93,000円 (年額 1,116,000円) 備考
- 初期費用(初年度のみ):70,000円
従業員数:1,000 名まで
- 1年
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- ミニマム 2,000円~/月額 備考
- 表示価格は最小の5名分料金で、6名以降は1名ごとに400円(月額)追加されます。
- スターター 3,000円~/月額 備考
- 表示価格は最小の5名分料金で、6名以降は1名ごとに600円(月額)追加されます。
- スタンダード 4,000円~/月額 備考
- 表示価格は最小の5名分料金で、6名以降は1名ごとに800円(月額)追加されます。
- アドバンス 5,500円~/月額 備考
- 表示価格は最小の5名分料金で、6名以降は1名ごとに1,100円(月額)追加されます。
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- 個人向け 800円~/月額
- 法人向け(50名以下の方) 2,980円~/月額
- 法人向け(51名以上の方) 要相談
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- 無料プラン 0円 備考
- 従業員数5名までです。
- 有料プラン 400円/月額 備考
- 表示価格はユーザー1名あたりの価格です。
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- Windowsアプリ iOSアプリ
- 電話 / メール / チャット /
-
価格や製品機能など、見やすい一覧表から、気になる製品をまとめてチェック!