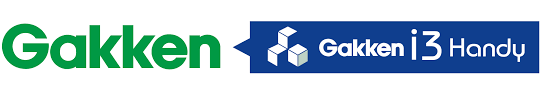「ピッキングシステム」の製品比較表
※税込と表記されている場合を除き、全て税抜価格を記載しています
-
- 製品名
- 料金プラン
- プラン名金額
- 無料トライアル
- 最低利用期間
- 基本的な機能
-
- ボール・バラ同時検品
- プロジェクションマッピング表示
- ハンディタイプ
- カートタイプ
- 導入支援あり
- ネットワーク接続不要
- 個口数決定処理
- ヒートマップ
- デジタル表示器対応
- DAS/DPS両対応
- 作業再生機能
- モチベーション向上機能
- サービス資料
- 無料ダウンロード
- ソフト種別
- 推奨環境
- サポート
価格や製品機能など、見やすい一覧表から、気になる製品をまとめてチェック!