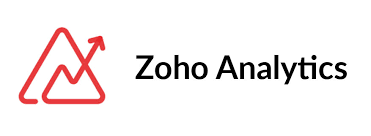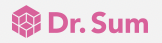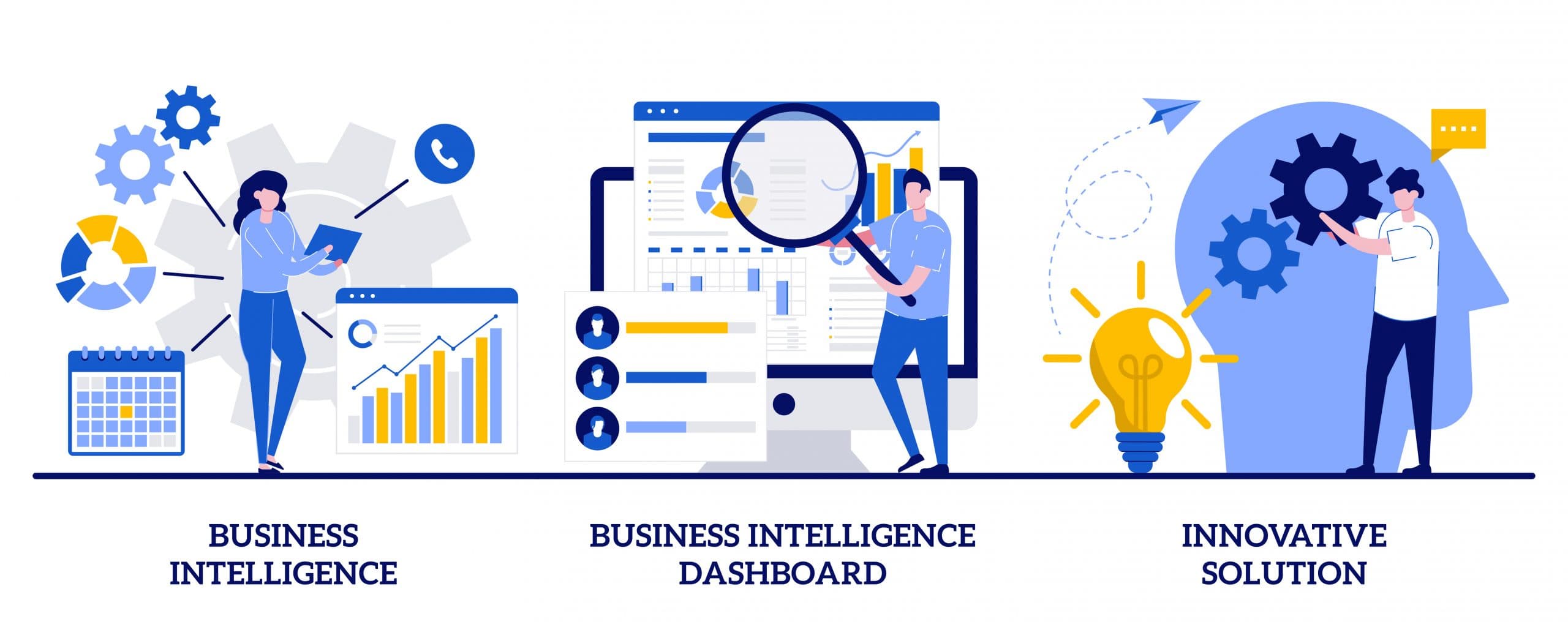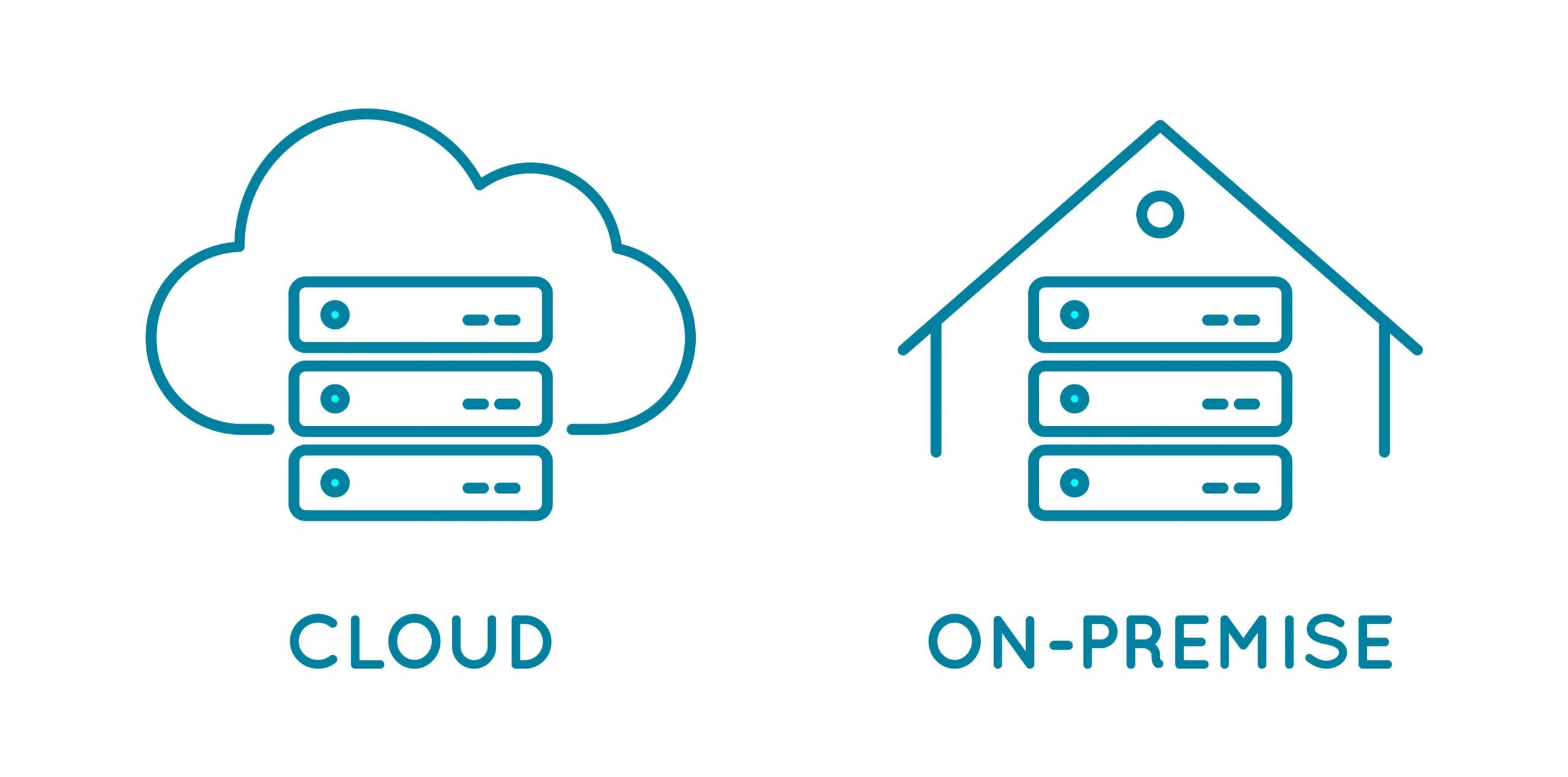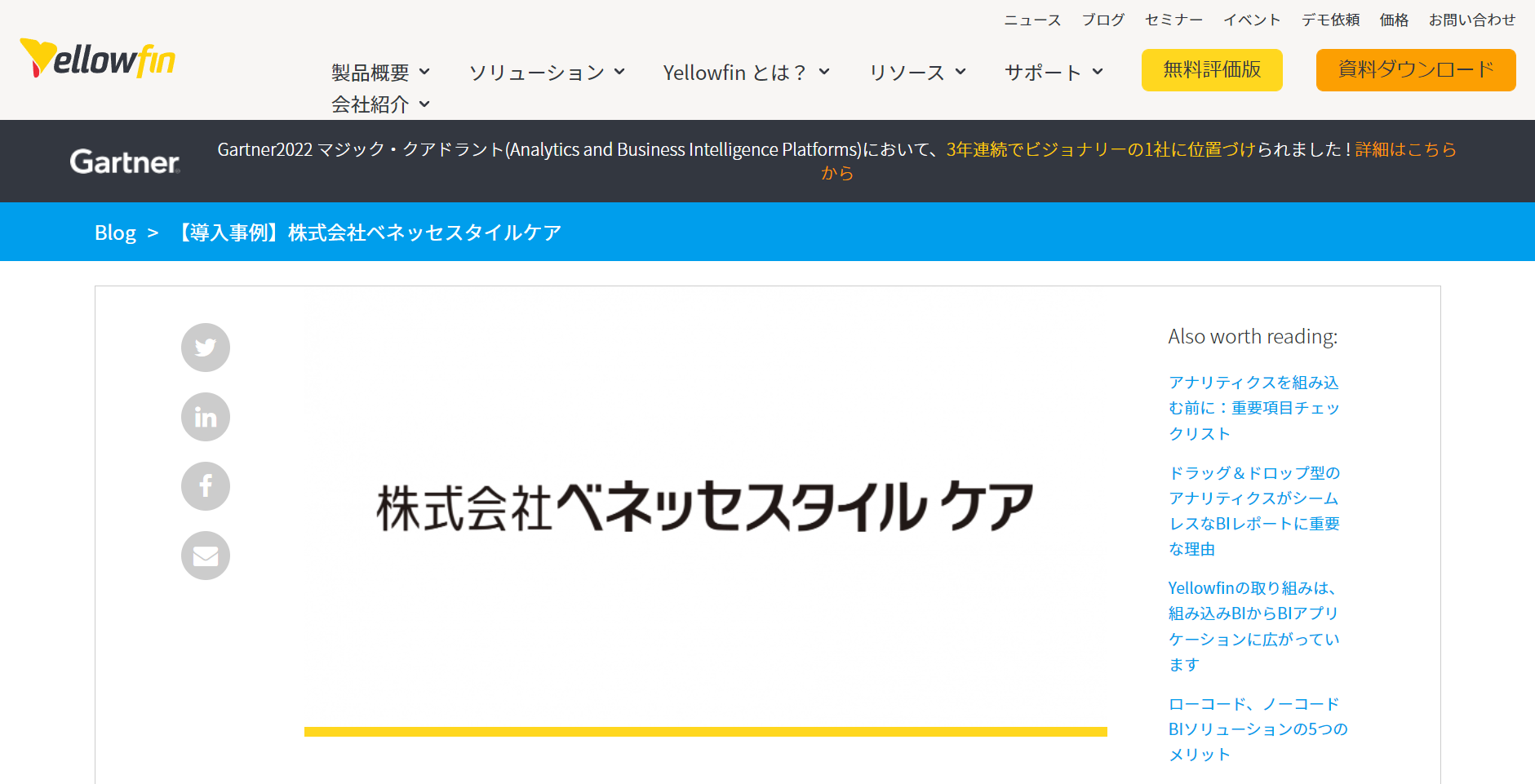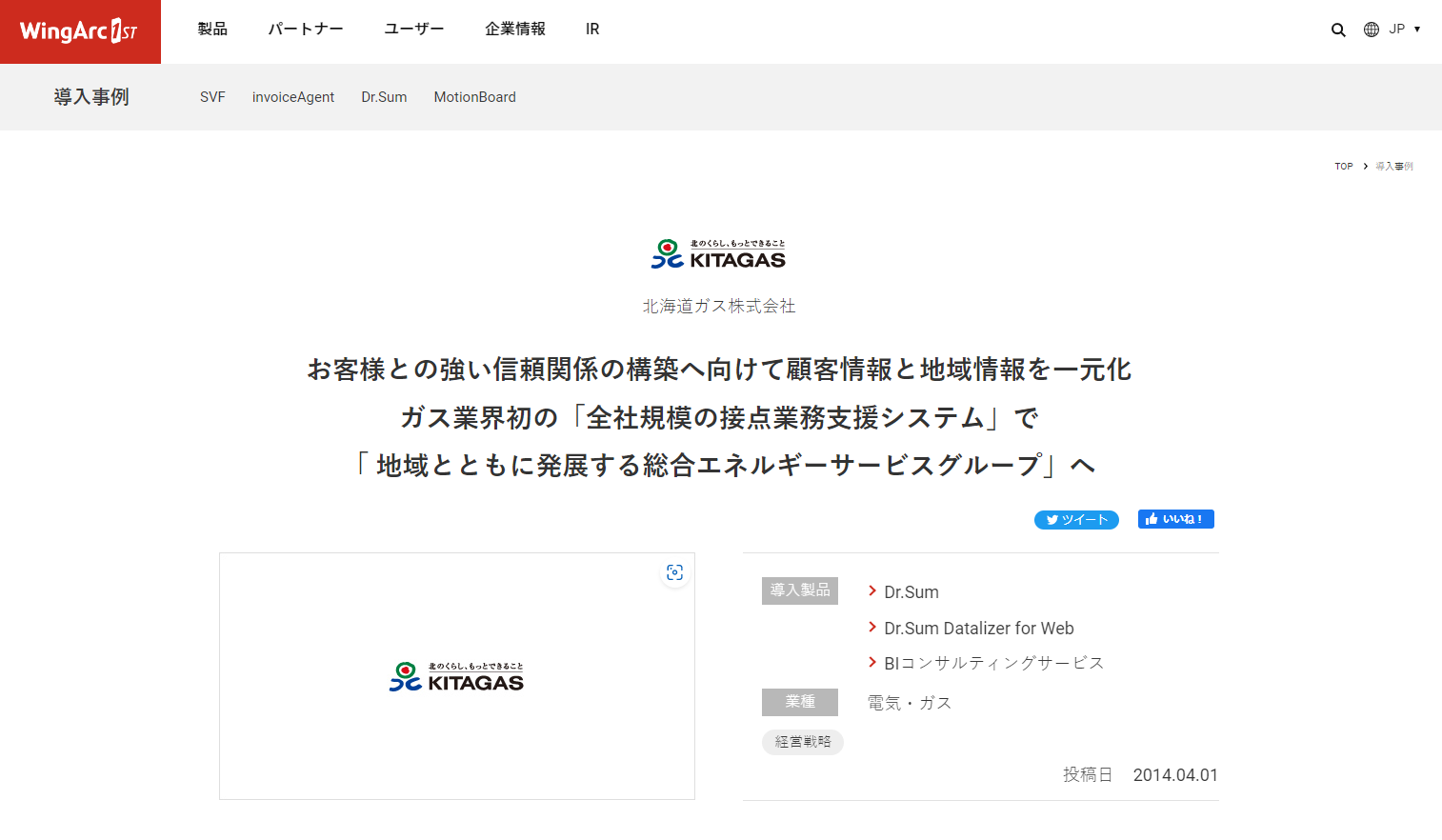「BIツール」の製品比較表
※税込と表記されている場合を除き、全て税抜価格を記載しています
-
- 製品名
- 料金プラン
- プラン名金額
- 無料トライアル
- 最低利用期間
- 基本的な機能
-
- ノーコード可
- テンプレートコードの組込み可
- 共同分析可
- 広告の最適化
- AI自動分析
- 現状のリアルタイム把握
- 行動サポート
- モバイルアプリあり
- モバイル端末対応
- 国内メーカー
- 自社システム連携
- kintone連携
- 帳票出力システム連携
- サービス資料
- 無料ダウンロード
- ソフト種別
- 推奨環境
- サポート
-
-
-
- 初期費用 要相談 備考
- セットアップ+開始時の構築支援(オンボーディングプログラム)の料金です。
- データ基盤プラン 要相談
- オールインワンプラン 要相談
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 料金 要相談
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- Power BI Pro 1,250円/月額/ユーザー 備考
- ライブ ダッシュボードおよびレポートでデータをビジュアル化し、組織全体でインサイトを共有するための、最新のセルフサービス分析機能を個々のユーザーにライセンス付与します。
- Power BI Premium 2,500円/月額/ユーザー 備考
- 各ユーザーにライセンスを付与して、高度な AI によるインサイト取得の促進、ビッグ データのセルフサービス データ準備の導入、エンタープライズ規模のデータ管理とアクセスの簡素化を実現します。
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト オンプレミス型ソフト
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 要相談 要相談
- 制限なし
-
-
-
- なし
- なし
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- クラウド版Standard MotionBoard Cloud 30,000円/月額 備考
- 10ユーザーあたりの金額です。
- クラウド版Standard MotionBoard Cloud for Salesforce 45,000円/月額 備考
- 10ユーザーあたりの金額です。
- クラウド版Professional MotionBoard Cloud 60,000円/月額 備考
- 10ユーザーあたりの金額です。
- クラウド版Professional MotionBoard Cloud for Salesforce 75,000円/月額 備考
- 10ユーザーあたりの金額です。
- クラウド版loT MotionBoard Cloud MotionBoard Cloud 90,000円/月額 備考
- 10ユーザーあたりの金額です。
- クラウド版loT MotionBoard Cloud for Salesforce 105,000円/月額 備考
- 10ユーザーあたりの金額です。
- オンプレミス版 サブスクリプション ライセ MotionBoardンス 80,600円~/月額
- オンプレミス版 サブスクリプション ライセ MotionBoard for Dr.Sum 60,500円~/月額
- オンプレミス版 パーペチュアル ライセンス[買い切り] MotionBoard 2,400,000円~
- オンプレミス版 パーペチュアル ライセンス[買い切り] 1,800,000円~
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト オンプレミス型ソフト
- なし
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 要相談 要相談
- 制限なし
-
-
-
- なし
- なし
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談 備考
- 動作環境、利用人数により提供内容が異なります。詳しくは、軽技Webホームページからお問い合せ下さい。
- 軽技Web Version7 Standard License 1,980,000円~/年間 備考
- Webサーバ1台に対するライセンスとなります。複数のハードウェアシステムでの利用、複数のオペレーティングシステムでの利用については、同等数の軽技Webライセンスが必要になります。また、複数の仮想オペレーティングシステム環境下で利用する場合、環境の数と同等数の軽技Webライセンスが必要となります。接続するデータベースの数に制限はございません。
- サポート 297,000円~/年間
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト オンプレミス型ソフト
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- GIAS 要相談 備考
- ハイスペックなツールだとしても社内構築するリソースもノウハウも限られており、気軽に試してみたい方向けのトライアル用パッケージです。
- Sisense Analytics 要相談 備考
- 一般的な社内利用向けにデータを格納するcloudDB、仮想空間、高度なAI、膨大なテンプレートとコネクターをフルに活用頂けるパッケージです。
- Embed Analytics 要相談 備考
- 業務へのより深い組み込みを行えます。Sisense Analyticsの全機能に加え、iFrameやJavaScriptを使用してデータでマネタイズを行う為のパッケージです。
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト オンプレミス型ソフト
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ Windowsアプリ iOSアプリ Androidアプリ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- 無料プラン 0円 備考
- ユーザー数は2人、1万行までのデータが作成可能です。
- ベーシックプラン 3,600円/月額 (年間払い2,880円/月額) 備考
- ユーザー数は2人分の価格です。50万行までのデータが作成可能です。無料プランの機能に加え、250以上のデータコネクター、AI搭載の「Zia」などを利用でき、リアルタイムでのデータ分析なども可能です。
- スタンダードプラン 7,200円/月額 (年間払い5,760円/月額) 備考
- ユーザー数は5人分の価格です。100万行までのデータが作成可能です。ベーシックプランの機能すべてに加え、状況を感知するデータアラートの設定やデータのバックアップ予約の設定することなどが可能になります。
- プレミアムプラン 17,400円/月額 (年間払い13,800円/月額) 備考
- ユーザー数は15人分の価格です。500万行までのデータが作成可能です。スタンダードプランの機能すべてに加え、独自のロゴを使用したZoho Analyticsのリブランディングやレポートとダッシュボードの限定公開のURLを生成することなどが可能になります。
- エンタープライズプラン 69,000円/月額 (年間払い54,600円/月額) 備考
- ユーザー数は50人分の価格です。5,000万行までのデータが作成可能です。プレミアムプランの機能すべてに加え、5倍の処理速度へシフト、無料で1つの分析ポータルのご提供ができ、Webチャットによるサポートが利用可能になります。
- カスタムプラン 要相談 備考
- 行、ユーザー、カスタムパッケージがもっと必要な場合は、お問い合わせページからご連絡いただければ、お客さまのご希望に合わせた見積りを準備いたします。
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト オンプレミス型ソフト
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ iOSアプリ Androidアプリ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- 料金プラン 要相談 備考
- 基本的にはオンプレイで、機能とサーバー数と同時アクセスユーザ数によって金額が変わります。詳しい情報はFineReportのHPにてお問い合わせください。
- 制限なし
-
-
-
- オンプレミス型ソフト パッケージ型ソフト
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ iOSアプリ Androidアプリ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談 備考
- サーバーライセンス型の価格体系となっており、データ量やユーザー数増加による追加コストの心配なくご利用いただくことができます。価格については、企業サイトからお問い合わせください。
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト オンプレミス型ソフト
- PCブラウザ Windowsアプリ iOSアプリ Androidアプリ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ iOSアプリ Androidアプリ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 最低利用期間の制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 最低利用期間の制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ iOSアプリ Androidアプリ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 最低利用期間の制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト オンプレミス型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- クラウド版 30,000円〜/月額 備考
- スマートスタートしたい方向けです。10ユーザーから利用可能で、ユーザー数によって金額は変わります。別途初期費用がかかります。
- サブスクリプション ライセンス 60,500円〜/月額 備考
- 社内ネットワーク内での運用を望まれる方です。初年度は保守料も含まれます。
- パーペチュアル ライセンス [買い切り] 1,800,000円〜/年額 備考
- 社内ネットワーク内での運用を望まれる方です。年単位での契約プランです。
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト オンプレミス型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 無料
- 利用料金 無料
- Looker Studio Pro $7/月額 備考
- 1ユーザーあたりの金額です。最低ユーザーID数が250IDになるので、最低月額料金は$1,750になります。
契約ユーザーID数が1,000IDを超えた場合は1ユーザーあたり$6となります。
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
価格や製品機能など、見やすい一覧表から、気になる製品をまとめてチェック!