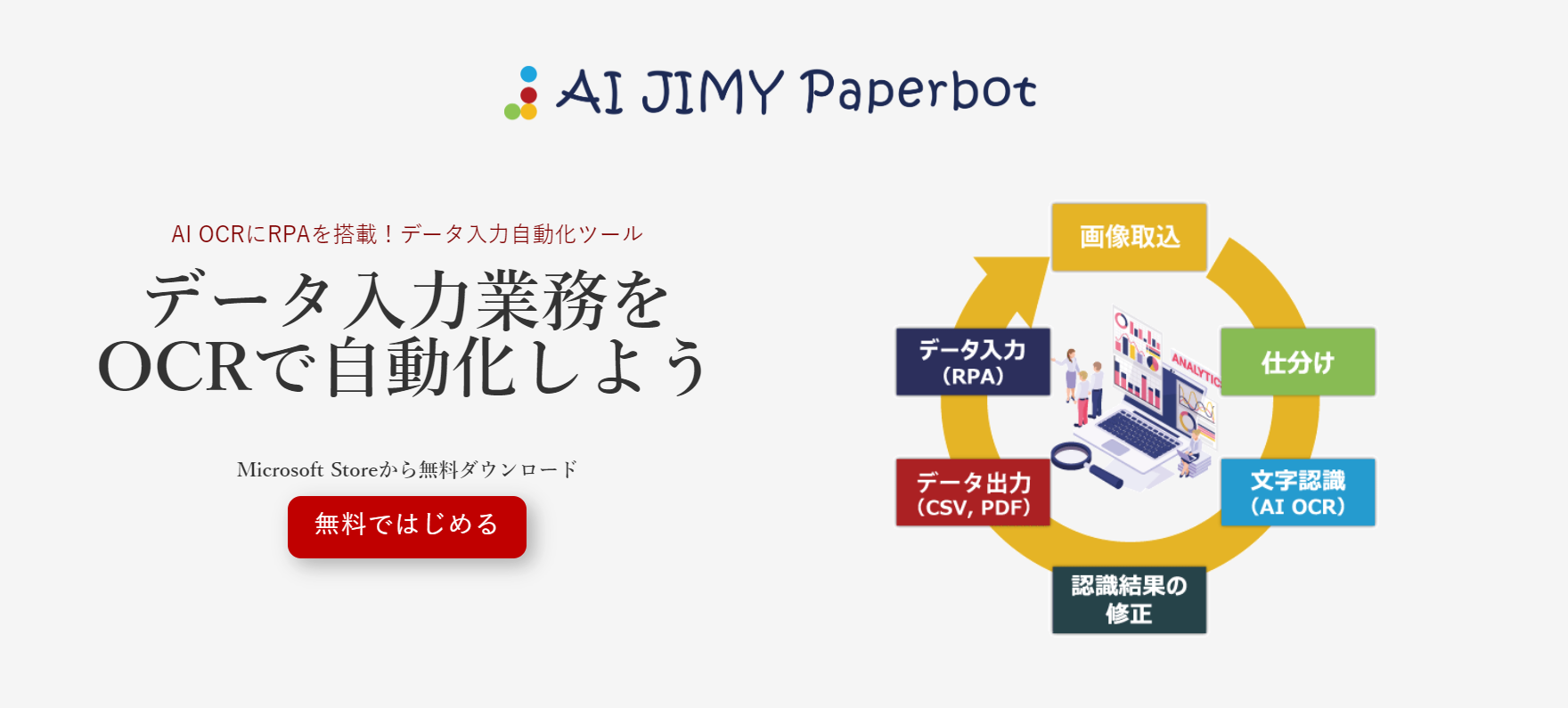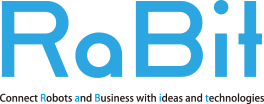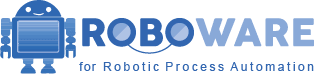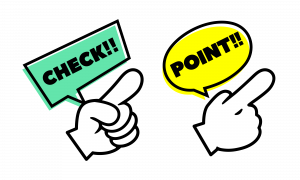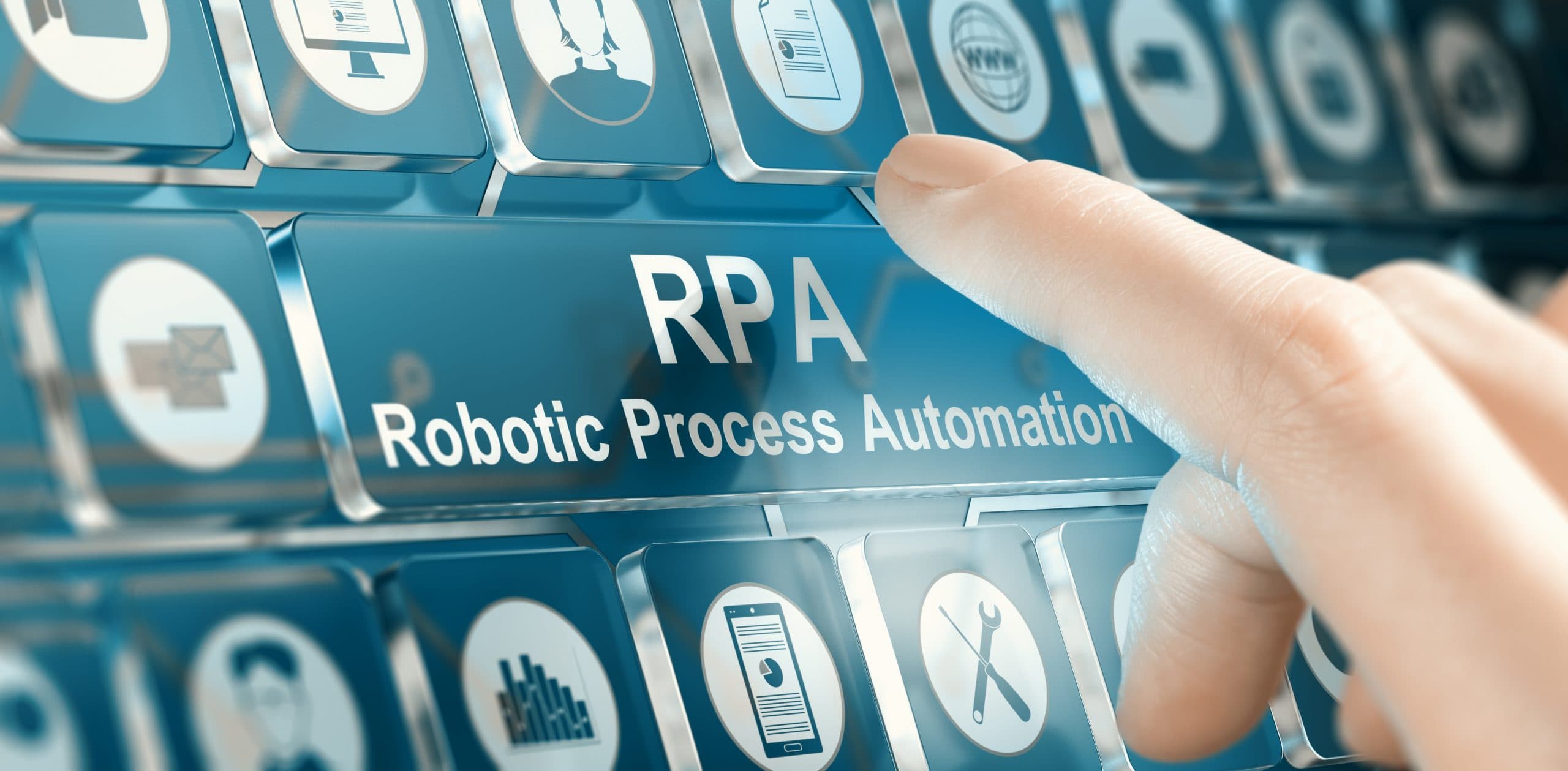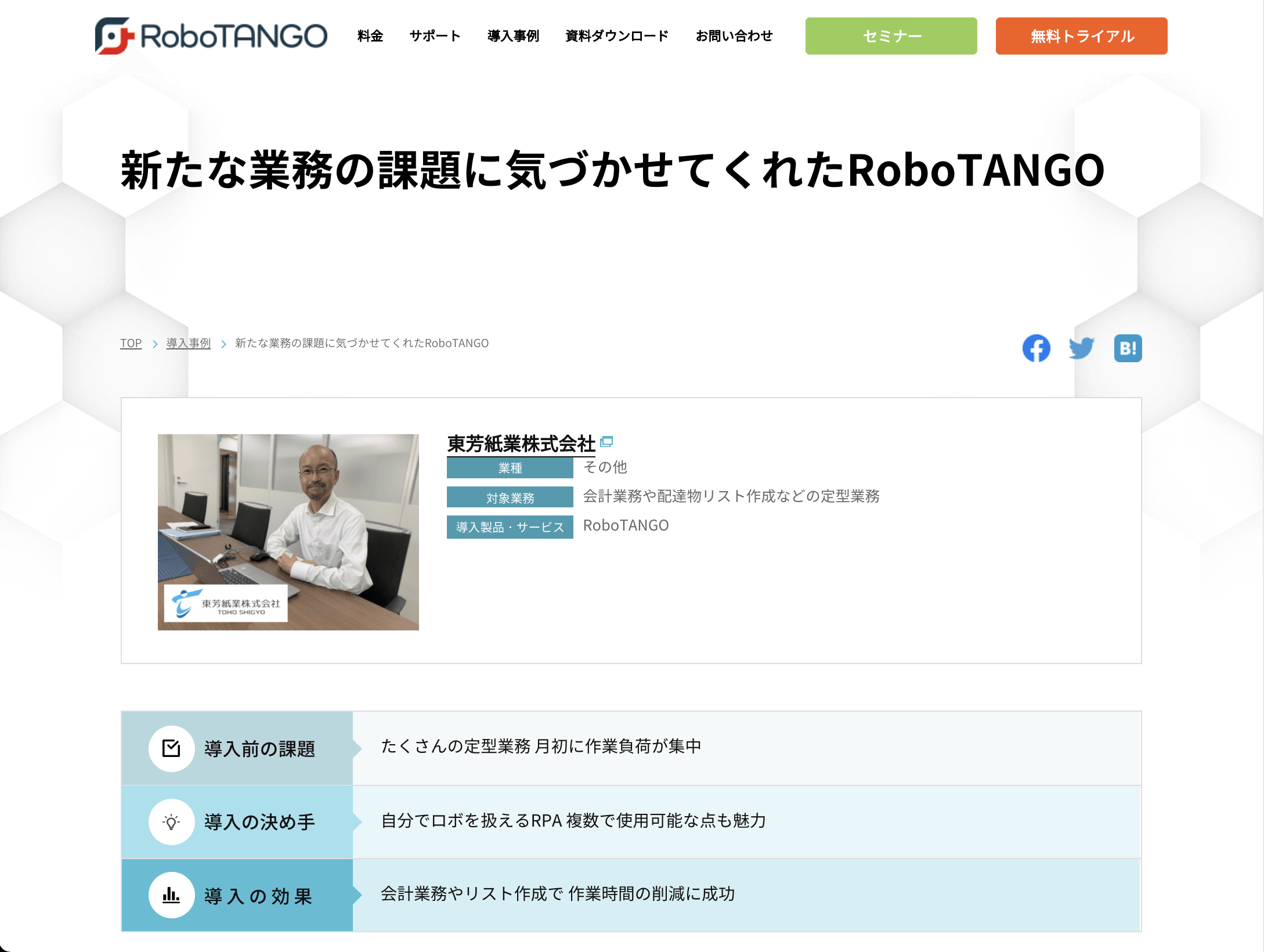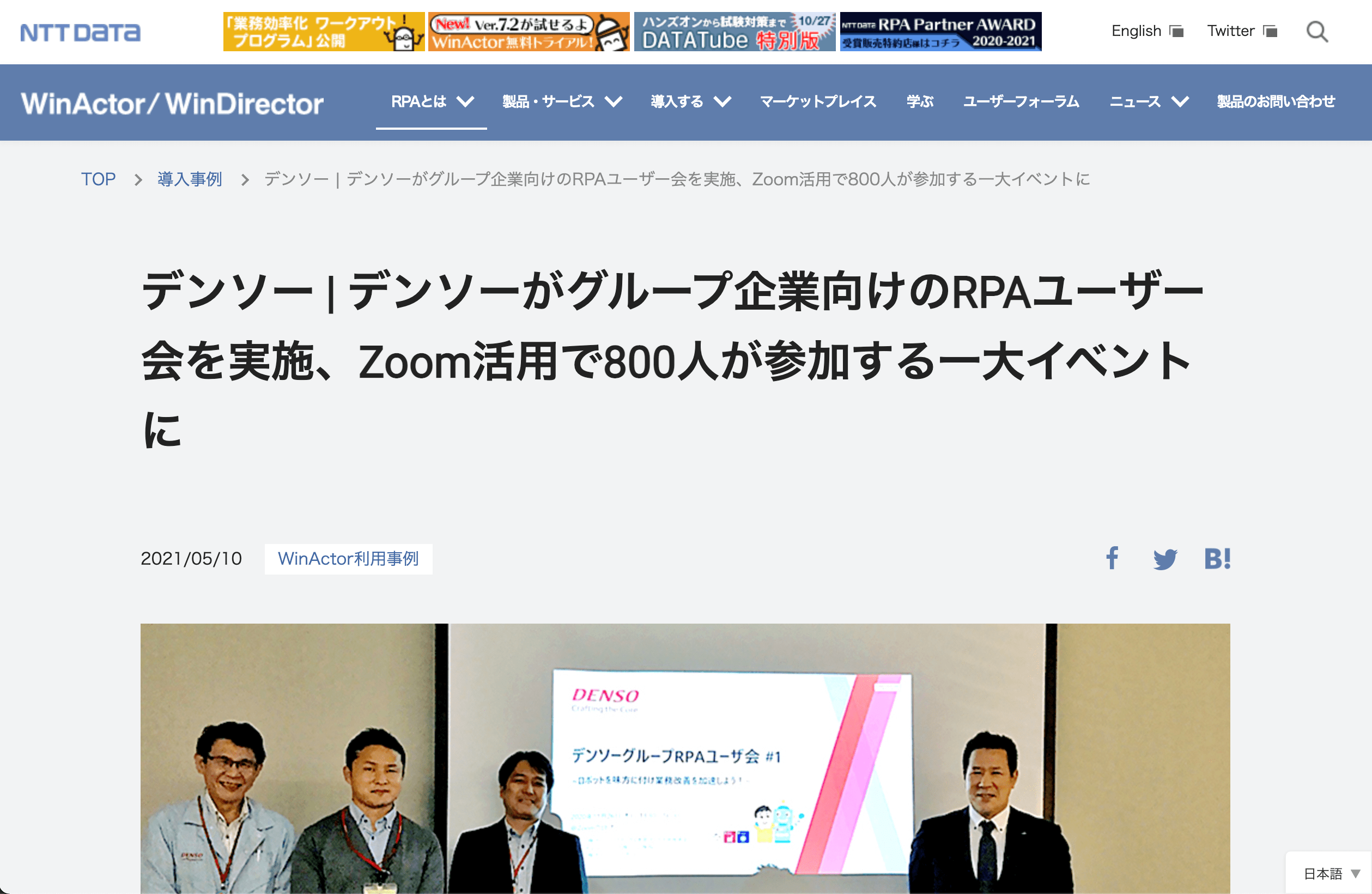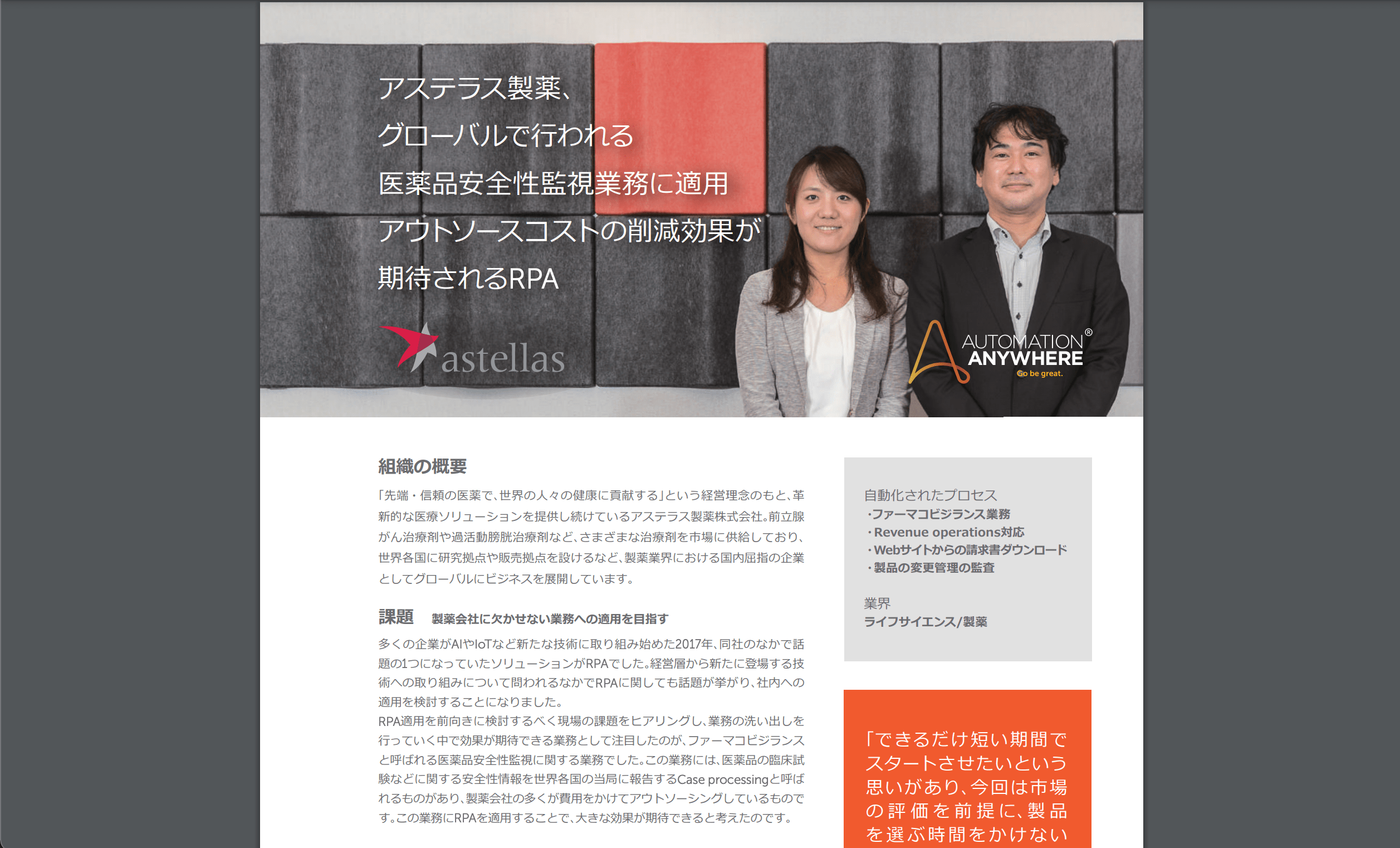「RPAツール」の製品比較表
※税込と表記されている場合を除き、全て税抜価格を記載しています
-
- 製品名
- 料金プラン
- プラン名金額
- 無料トライアル
- 最低利用期間
- 基本的な機能
-
- 自動化業務の設定
- スケジュール設定
- データの転記作業
- 紙資料の電子化
- テキストのチェック
- エラー処理
- メール送信
- メールのファイル保存
- PDF変換
- スクレイピング
- データ集計
- タスクレポート
- サービス資料
- 無料ダウンロード
- ソフト種別
- 推奨環境
- サポート
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- Trial 0円 備考
- 試してみたい方向け
・月間契約→14日間無料
・AI OCR(上限枚数)→30枚
・AI帳票仕分け→無制限
・AI類似変換→無制限
・RPA→〇 - Starter 120,000円/年間 (1ヵ月あたり1万円 ) 備考
- コストを抑えたい方向け
・月間契約→12,000円/月額
・AI OCR(上限枚数)→100枚/月
・AI帳票仕分け→無制限
・AI類似変換→無制限
・RPA→✕(制限あり) - Standard 600,000円/年間 (1ヵ月あたり5万円 ) 備考
- 一般的なプラン
・月間契約→60,000円/月額
・AI OCR(上限枚数)→2000枚/月
・AI帳票仕分け→無制限
・AI類似変換→無制限
・RPA→〇 - Pro 1,800,000/年間 (1ヵ月あたり15万円 ) 備考
- 処理枚数が多い方向け
・月間契約→180,000円/月額
・AI OCR(上限枚数)→10000枚/月
・AI帳票仕分け→無制限
・AI類似変換→無制限
・RPA→〇
- 制限なし
-
-
-
- オンプレミス型ソフト
- Windowsアプリ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- OCEVISTAS mini 年額90万円~
- OCEVISTAS BasicRobo 年額720万円~(月額60万円~) 備考
- RPA導入にあたり、企画、導入、運用の各フェーズに対応するサービスについては個別見積にて対応いたします。
- OCEVISTAS mini for 自治体 年間60万円~
- 一年間
-
-
-
- クラウド型ソフト オンプレミス型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 60,000円 備考
- 初期費用には以下が含まれています。
・ご意向ヒアリング
・要件定義
・ロボット開発
・導入 - 月額利用料 9,500円/月額 備考
- 1つのロボット作業について、月額9,500円がかかります。 利用者のロボット作業数の算出については、初回の業務ヒアリング時に確認できます。
- 制限なし
-
-
-
- オンプレミス型ソフト
- Windowsアプリ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 要相談 要相談
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- NEC Software Robot Solution 120,000円/月額
- NEC Software Robot Solution 実行専用 40,000円/月額
- その他要お問い合わせ その他要お問い合わせ
- 1か月
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 月額基本料 82500円(税込)
- オプション(導入支援) 22000円(税込)
- その他 要お問い合わせ
- 制限なし
-
-
-
- なし
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 ‐ 備考
- お問い合わせください。
- BizRobo! mini 900,000円/年間
- BizRobo! Lite 1,200,000円/年間 備考
- 初期費用30万円かかります。
- BizRobo! Lite+ 1,800,000円/年間 備考
- 初期費用30万円かかります。
- BizRobo! Basic 7,200,000円/年間
- 1年間
-
-
-
- オンプレミス型ソフト パッケージ型ソフト
- Windowsアプリ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- WinActor フル機能版ライセンス 908,000円/年間
- WinActor 実行版ライセンス 248,000円/年間
- 有償トライアルサービス (60日間) 190,000円
- 制限なし
-
-
-
- パッケージ型ソフト
- Windowsアプリ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- フリー 無料 備考
- 個人向け、一回実行あたり最大1万レコード導出可能、抽出ページ数制限なし、端末台数制限なし。
- スタンダード $75/月額 備考
- チーム向け、フリーのすべての機能に加えます。100タスクの同時保存、クラウド抽出(6台同時利用)、100種類以上のスターターテンプレート、基本APIアクセス。
- プロフェッショナル $208/月額 備考
- 中規模の組織向け、スタンダードのすべての機能に加えます。250タスクの同時保存、クラウド抽出(20台同時利用)、高度APIアクセス、クラウド自動バックアップ、ワークフローチェック & 1対1トレーニング。
- エンタープライズ ニーズに応じてカスタマイズ可能 備考
- 大規模、複雑な組織向け、プロフェッショナルのすべての機能に加えます。750タスクの同時保存、クラウド抽出(40台同時利用)、機能拡張、専任のサクセスマネージャー。
- データサービス $399~ 備考
- フルカスタマイズ 、整理・標準化しデータを提供します 。 24時間年中無休のモニタリング
PoC試作サービスをご提供 、単発プロジェクトに最適
法的・GDPR対応
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト パッケージ型ソフト
- Windowsアプリ Macアプリ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 1,000,000円
- オープン価格 2,500,000円 備考
- パートナー契約の場合は安くなる可能性があります。
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- Windowsアプリ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 基本プラン 50,000円/月額 備考
- 初期費用100,000円かかります。
- リモレクライト 80,000円/月額 備考
- 初期費用150,000円かかります。ロボ作成のサポートを受けられます。月1コマのオンラインレクチャーを受講可能です。
- リモレク スタンダード 100,000円/月額 備考
- 初期費用150,000円かかります。作成したいロボがたくさんある方におすすめです。月2コマのオンラインレクチャーを受講可能です。
- リモレク アドバンス 150,000円/月額 備考
- 初期費用200,000円かかります。早急に業務にRPAを定着させたい方におすすめです。月4コマのオンラインレクチャーを受講可能です。
- 1ヵ月
-
-
-
- オンプレミス型ソフト
- Windowsアプリ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- Autoジョブ名人 開発版 1年間ライセンス 600,000円
- Autoジョブ名人開発版 5年間ライセンス 2,700,000円
- Autoジョブ名人実行版 1年間ライセンス 180,000円
- Autoジョブ名人実行版 5年間ライセンス 810,000円
- 制限なし
-
-
-
- パッケージ型ソフト
- Windowsアプリ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- ベーシックパック 要相談 備考
- 同時アクセス数10人のサーバ型。本格導入する方向けです。
- ライトパック 要相談 備考
- 同時アクセス数1人のデスクトップ型。スモールスタートに。
- 制限なし
-
-
-
- オンプレミス型ソフト パッケージ型ソフト
- PCブラウザ Windowsアプリ Macアプリ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- 別途お問い合わせ
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト オンプレミス型ソフト
- Windowsアプリ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- ケースマネジメントエディション $97~$0.47/ケースから 備考
- ケース単位はサービスリクエスト1件あたりの料金です。
- エンタープライス $165~$0.80/ケースから
- デジタルカスタマー用エディション $260から$1.26/ケースから
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- Windowsアプリ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- 最小構成 1080,000円/年間
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト オンプレミス型ソフト
- Windowsアプリ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- 1ライセンス 1,200,000円/年間
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト オンプレミス型ソフト
- Windowsアプリ
- 電話 / メール / チャット /
-
価格や製品機能など、見やすい一覧表から、気になる製品をまとめてチェック!