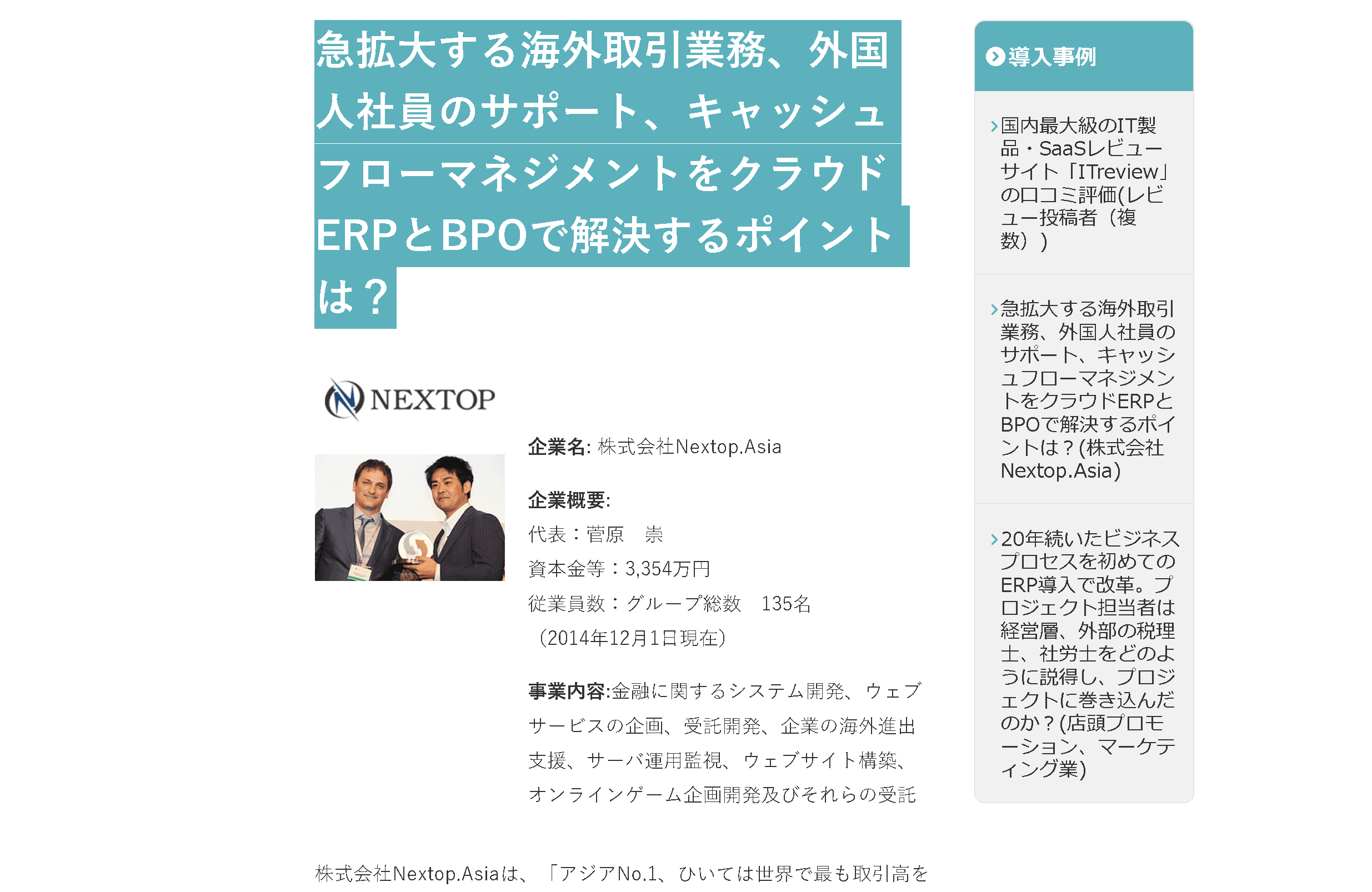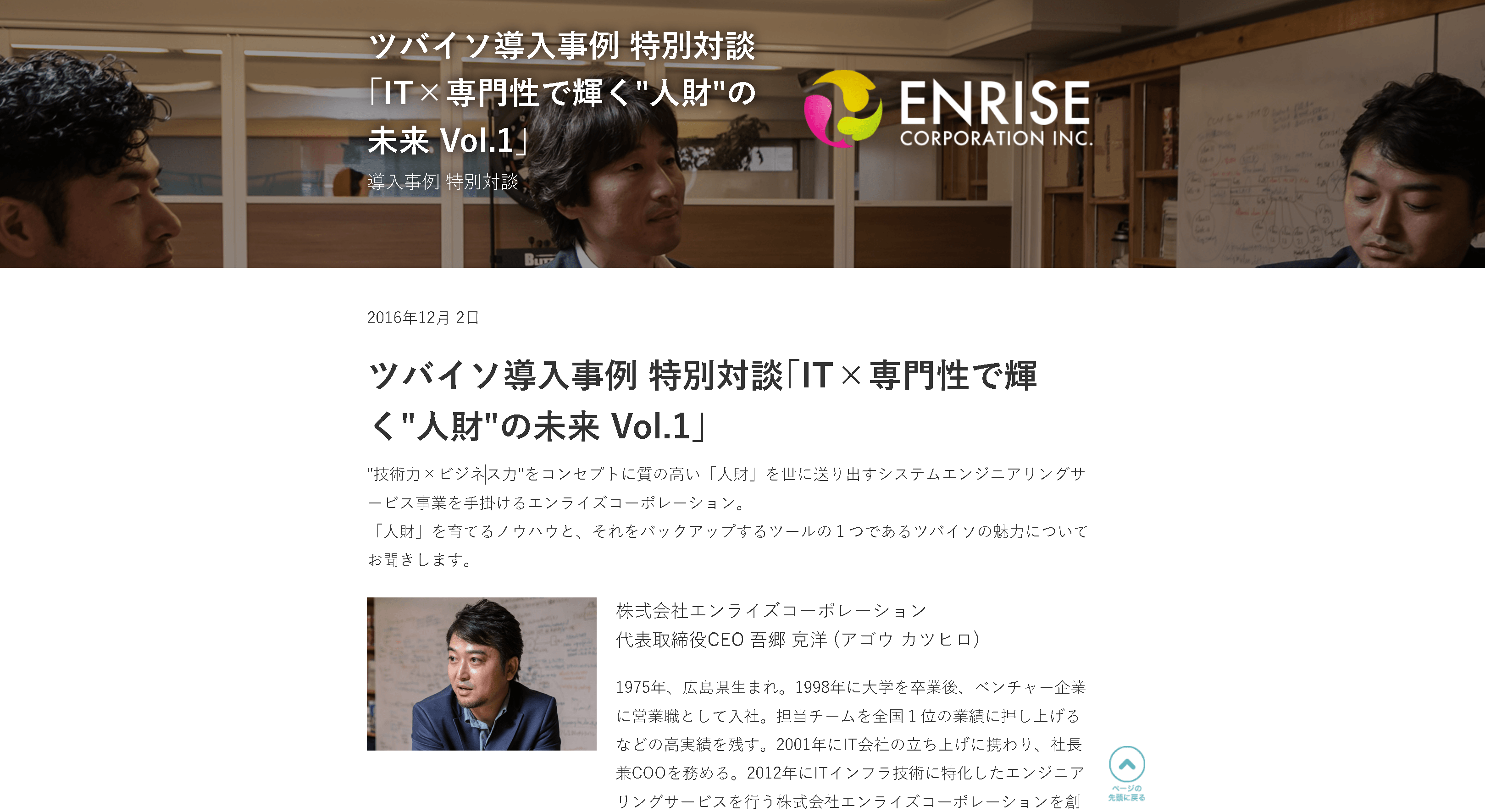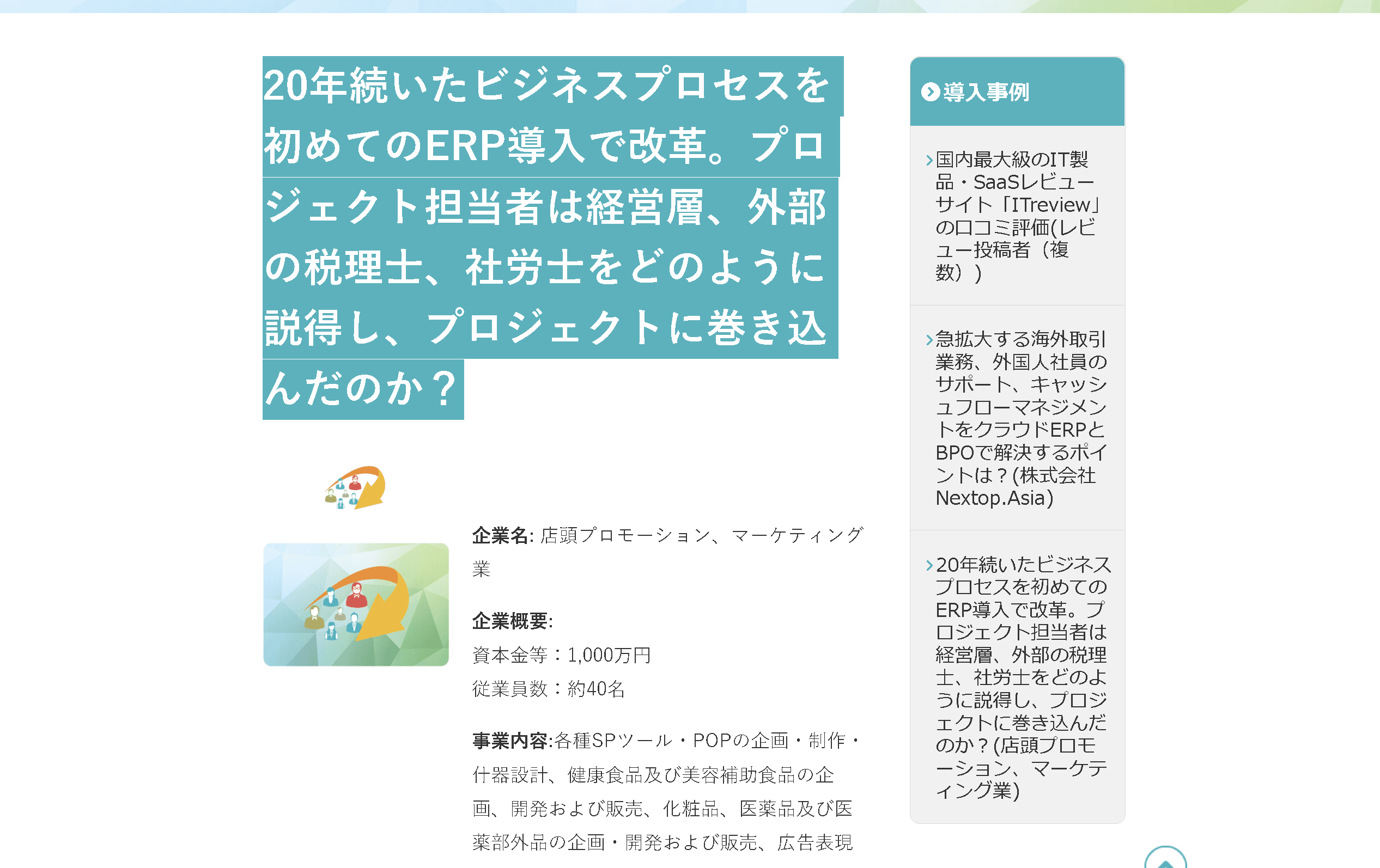「ERP」の製品比較表
※税込と表記されている場合を除き、全て税抜価格を記載しています
-
- 製品名
- 料金プラン
- プラン名金額
- 無料トライアル
- 最低利用期間
- 基本的な機能
-
- ワークフロー管理
- 集計機能
- データ連携
- 支出管理
- プロキュアメント
- 経理・会計管理
- レポート機能
- 財務管理
- 人事管理
- 倉庫管理
- 受注・調達管理
- 生産管理
- サプライチェーン管理
- 債権・債務管理
- 販売・顧客管理
- ライブラリ機能
- 決算機能
- 帳簿機能
- 金融機関連携
- グループ経営管理
- サービス資料
- 無料ダウンロード
- ソフト種別
- 推奨環境
- サポート
-
-
-
- 初期費用 0円
- 料金 4万円~/月額
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- タレント・マネジメント 要相談 備考
- 準備中
- エンタープライズ・リソース・プランニング 要相談
- プロフェッショナル・サービス・オートメーション 要相談
- コーポレート・パフォーマンス・マネジメント 要相談 備考
- 準備中
- 30日
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 要相談 要相談
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト オンプレミス型ソフト
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ Windowsアプリ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 要相談 要相談
- 1か月
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- Business Central Essentials ¥7,610
- Business Central Premium ¥10,870
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト オンプレミス型ソフト
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ Windowsアプリ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 要相談 要相談
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト オンプレミス型ソフト パッケージ型ソフト
- Windowsアプリ Macアプリ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 要相談 要相談
- 45日
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 会計 + 人事労務 エンタープライズ 要相談
- 制限なし
-
-
-
- クラウド型ソフト
- PCブラウザ Androidアプリ
- 電話 / メール / チャット /
-
価格や製品機能など、見やすい一覧表から、気になる製品をまとめてチェック!