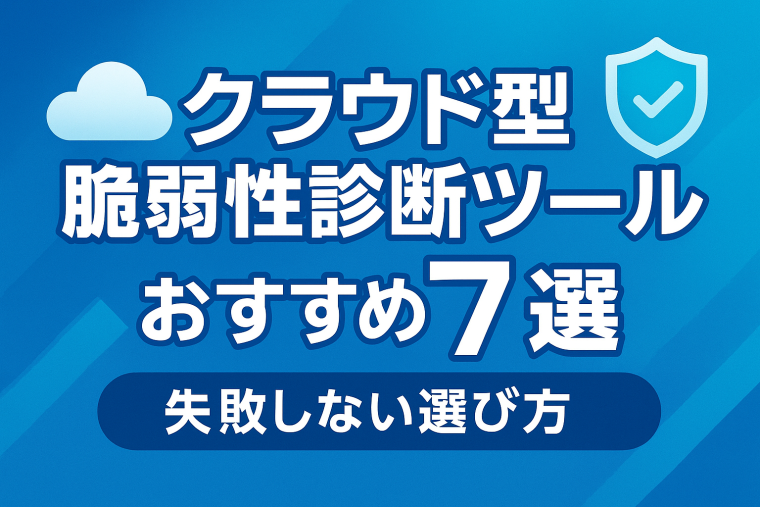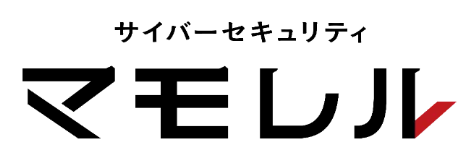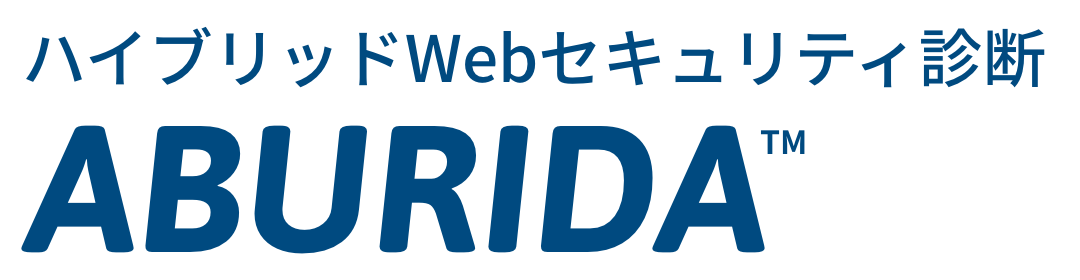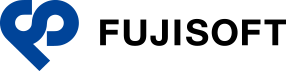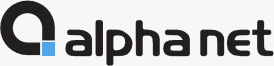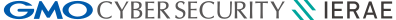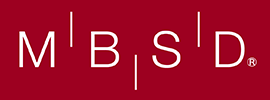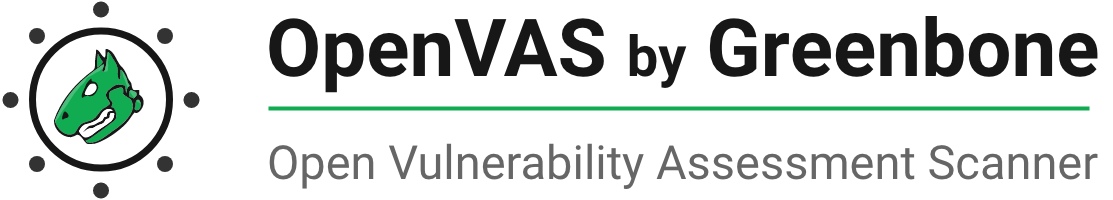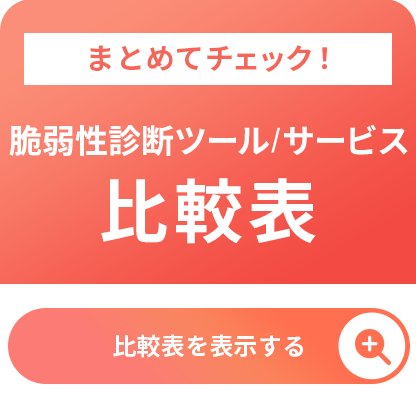「脆弱性診断ツール/サービス」の製品比較表
※税込と表記されている場合を除き、全て税抜価格を記載しています
-
- 製品名
- 注目ポイント
- 料金プラン
- プラン名金額
- 無料トライアル
- 最低利用期間
- 製品名
- 基本的な機能
-
- ドメイン設定
- SQLインジェクション
- サーバ設定
- X-Content-Type-Optionsヘッダの未設定
- URL設定
- アプリケーションエラーの開示
- オートコンプリート機能有効化
- ヘッダインジェクション
- オープンリダイレクタ
- クロスサイトスクリプティング
- HttpOnly属性が付与されていないCookieの利用
- グラスボックス診断
- クラウド診断
- プラットフォーム診断
- スマホアプリ(iOS・Android)診断
- Webアプリケーション診断
- デスクトップアプリ診断
- SSL設定
- X-Frame-Optionsヘッダの未設定
- 製品名
- サービス資料
- 無料ダウンロード
- ソフト種別
- 推奨環境
- サポート
-
- 守りは鉄壁 世界基準
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- マモレル
-
-
- マモレル
-
-

- Software type
- なし
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- クラウドのリスク、まとめて可視化
-
-
- 初期費用 無償
- 月額利用料 50,000円
- Free trial
- Minimum usage period
- 1年間
- クラウドパトロール
-
-
- クラウドパトロール
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- Webの守りと、万一の保険
-
-
- 初期費用 10万円
- 利用料金 45,000円/月額 備考
- ※3カ月のアウトバウンドデータ量が0.5TBまで
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- BLUE Sphere
-
-
- BLUE Sphere
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- 大事な操作、置くだけで見守り
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- セキュリティ診断サービス(株式会社ト…
-
-
- セキュリティ診断サービス(株式会社ト…
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- 丸投げしない、プロの目
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- DIT Security
-
-
- DIT Security
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- 世界の目で、見つける「穴」
-
-
- 初期費用 無料
- 月額費用 無料~
- 手数料 ホワイトハッカーへの報奨金の20% 備考
- 成果報酬型でご提供しております。
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- IssueHunt バグバウンティ
-
-
- IssueHunt バグバウンティ
-
-

- Software type
- なし
- Recommended environment
- PCブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- AIとヒトで、誤検知なし
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- ImmuniWeb
-
-
- ImmuniWeb
-
- Software type
- なし
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- 見つけて、直すまでご支援
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談 備考
- 予算に応じてLight・Standard・Advancedの3つのコースがあります。
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- セキュリティ診断サービス(NECソリ…
-
-
- セキュリティ診断サービス(NECソリ…
-
- Software type
- なし
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- 診断と「学ぶ」セキュリティ
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- セキュリティ診断サービス(株式会社F…
-
-
- セキュリティ診断サービス(株式会社F…
-
- Software type
- なし
- Recommended environment
- PCブラウザ Windowsアプリ Macアプリ iOSアプリ Androidアプリ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- プロの目配り、堅実な診断
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- セキュリティ診断サービス(株式会社N…
-
-
- セキュリティ診断サービス(株式会社N…
-
- Software type
- なし
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- 「誰でも、すぐ」のAI診断
-
-
- One Shotプラン お見積り 備考
- まずは1サイト診断したい方
- Businessプラン お見積り 備考
- 診断を内製化したい方
- Free trial
- Minimum usage period
- 15日
- AeyeScan
-
-
- AeyeScan
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- 「野良端末」も漏れなく診断
-
-
- プロフェッショナル 85,000円 備考
- ドメイン数:1~9個
- プロフェッショナル 118,400円 備考
- ドメイン数:100~199個
- プロフェッショナル 160,000円 備考
- ドメイン数:1000~2000個
- エキスパート 85,000円 備考
- ドメイン数:1~9個
- エキスパート 118,400円 備考
- ドメイン数:100~199個
- エキスパート 160,000円 備考
- ドメイン数:1000~2000個
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- AEGIS-EW(イージスEW)
-
-
- AEGIS-EW(イージスEW)
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- サイトの守り、すぐお任せ
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- 利用料金 0円 備考
- オープンソースのソフトウェアです。
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- OWASP ZAP
-
-
- OWASP ZAP
-
- Software type
- パッケージ型ソフト
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- Wチェックと、無料再診断
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- お試しプラン 90,000円(税込) 備考
- 1社1回限りです。3リクエストまで。無料の再診断がありますが、診断結果が「危険度Medium」以上の項目のみとなります。
- スタンダードプラン 440,000円(税込) 備考
- 10リクエストまで。無料の再診断がありますが、診断結果が「危険度Medium」以上の項目のみとなります。
- ボリュームプラン 1,408,000円(税込) 備考
- 50リクエストまで。無料の再診断がありますが、診断結果が「危険度Medium」以上の項目のみとなります。
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- ABURIDA
-
-
- ABURIDA
-
- Software type
- なし
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- メーカー品質の、確かな目
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- エクスプレス診断 400,000円 備考
- Webアプリケーション診断は、10リクエストまたは6APIまでです。報告会実施の場合別途10万円/回が必要です。再診断は無償です。
- エキスパート診断 1,280,000円 備考
- Webアプリケーション診断は、50リクエストまたは25APIまでです。報告会実施の場合別途15万円/回が必要です。再診断は無償です。
- プラットフォーム診断 250,000円 備考
- プラットフォーム診断は、3 IPまたは3FQDNまでです。報告会実施の場合別途15万円/回が必要です。再診断は無償です。
- エクスプレス診断 +プラットフォーム診断 550,000円 備考
- Webアプリケーション診断は、10リクエストまたは6APIまでです。プラットフォーム診断は、3 IPまたは3FQDNまでです。報告会実施の場合別途10万円/回が必要です。再診断は無償です。
- エキスパート診断 +プラットフォーム診断 1,430,000円 備考
- Webアプリケーション診断は、50リクエストまたは25APIまでです。プラットフォーム診断は、3 IPまたは3FQDNまでです。報告会実施の場合別途15万円/回が必要です。再診断は無償です。
- ペネトレーションテスト 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- 脆弱性診断サービス(株式会社セキュア…
-
-
- 脆弱性診断サービス(株式会社セキュア…
-
- Software type
- なし
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- プロの診断を、自社で実現
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- デベロッパーライセンス 要相談 備考
- 自社で開発もしくは運営するWebアプリケーションの診断に利用する場合のライセンスです。各販売代理店から購入できます。
- オーディターライセンス 要相談 備考
- Vexを利用した脆弱性検査サービスを提供する場合には、こちらの契約が必要です。
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- Vex
-
-
- Vex
-
- Software type
- パッケージ型ソフト
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- ムダを省いた、プロの診断
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- 新規 300,000円 備考
- 期間限定で99,000円~にて提供の場合もあります。診断方法は遠隔で、診断対象は25ページまでです。
- フォローアップ診断 80,000円 備考
- 再診断メニューです。本診断のレポート提出後、20日以内までの依頼を対象とします。診断方法は遠隔で、診断対象は該当箇所だけです。
- 個別対応(ReCoVASプロ) 500,000円~ 備考
- 内容は要相談です。
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- ReCoVAS
-
-
- ReCoVAS
-
- Software type
- なし
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- ホワイトハッカーの確かな目
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- プラン 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- セキュリティ診断サービス(株式会社日…
-
-
- セキュリティ診断サービス(株式会社日…
-
- Software type
- なし
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- 隠れた裏口、見つけます
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- プラン 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- バックドア検証サービス
-
-
- バックドア検証サービス
-
- Software type
- なし
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- ハッカー目線で守りを固める
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- Webアプリケーション診断(手動) 240,000円~ 備考
- 1リクエストで、報告書を含みます。
- スマホWebAPI診断 250,000円~ 備考
- 1リクエスト当たりの料金で、(報告書を含みます。Androidのみの対応となります。
- おまかせプラン 要相談 備考
- 予算等に合わせて対象数を決定いただき、その数を上限にエンジニアが診断対象を選定し、診断を行うサービスです。
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- セキュリティ診断サービス(株式会社ア…
-
-
- セキュリティ診断サービス(株式会社ア…
-
- Software type
- なし
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- nessus essentials $0 備考
- 教育関係者や、サイバーセキュリティのキャリアを始めようとしている学生、個人に理想的なサービスです。 IP アドレスを 16 個までスキャン可能です。
- nessus professional $3,729/年額 備考
- コンサルタント、ペンテスター、セキュリティ担当者向けのサービスです。サブスクリプションでスキャナー単位のライセンスです。
- Free trial
- Minimum usage period
- 1年
- Nessus
-
-
- Nessus
-
- Software type
- パッケージ型ソフト
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- 通信の裏側を丸ごと可視化
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- プラン1 $6,995/年額 備考
- Burp Suite Enterprise EditionのStarterプラン。自動化されたスケーラブルなWeb脆弱性スキャンを可能にします。5の同時スキャンができます。
- プラン2 $ 14,480/年額 備考
- Burp Suite Enterprise EditionのGrowプラン。自動化されたスケーラブルなWeb脆弱性スキャンを可能にします。20の同時スキャンができます。
- プラン3 $ 29,450~/年額 備考
- Burp Suite Enterprise EditionのAccelerateプラン。自動化されたスケーラブルなWeb脆弱性スキャンを可能にします。50以上の同時スキャンができます。
- プラン4 $ 399/年額 備考
- Burp Suite Professionalです。主要なWebセキュリティおよび侵入テストツールキットです。
- Free trial
- Minimum usage period
- 1年
- Burp Suite
-
-
- Burp Suite
-
- Software type
- パッケージ型ソフト
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- URL登録だけで安心診断
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- 無料診断 0円 備考
- 診断回数1回、リスク件数のみ表示です。
- ライトプラン 10,000円/月額 備考
- 1ドメインあたりの料金で、診断ページ数 は500ページ以下です。毎日診断実施可能で、リスク件数、発生している脆弱性の内容・対策方法の案内があります。
- スタンダードプラン 17,000円/月額 備考
- 1ドメインあたりの料金で、診断ページ数 は1,000ページ以下です。毎日診断実施可能で、リスク件数、発生している脆弱性の内容・対策方法の案内があります。
- ビジネスプラン 24,000円/月額 備考
- 1ドメインあたりの料金で、診断ページ数 は1,500ページ以下です。毎日診断実施可能で、リスク件数、発生している脆弱性の内容・対策方法の案内があります。
- エンタープライズプラン 要相談 備考
- 診断ページ数 は1,501ページ以上です。毎日診断実施可能で、リスク件数、発生している脆弱性の内容・対策方法の案内があります。
- Free trial
- Minimum usage period
- 最低利用期間は1年間(有料版)
- WEBセキュリティ診断くん
-
-
- WEBセキュリティ診断くん
-
- Software type
- パッケージ型ソフト
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- 実績技術で穴を防ぐ
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- プラン 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- セキュリティ脆弱性診断サービス(株式…
-
-
- セキュリティ脆弱性診断サービス(株式…
-
- Software type
- なし
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- 毎日チェックで安心可視
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- 要相談 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- SCT SECURE クラウドスキャ…
-
-
- SCT SECURE クラウドスキャ…
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- 攻撃視点で安心設計
-
-
- 初期費用 要相談
- 料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- Webアプリケーション診断(GMOサ…
-
-
- Webアプリケーション診断(GMOサ…
-
- Software type
- なし
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- 全ページ診断定額制
-
-
- AIクイック・ツール診断 FQDNあたり25万円 備考
- 3か月以内の再診断付き
- AIリモート脆弱性診断 FQDNあたり98万円 備考
- 3か月以内の再診断付き
- モバイルアプリ診断 脆弱性診断:パッケージあたり78万円/OS
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- 脆弱性診断(株式会社レイ・イージス・…
-
-
- 脆弱性診断(株式会社レイ・イージス・…
-
- Software type
- なし
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- 熟練技術で安心設計
-
-
- 初期費用 要相談
- 要相談 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- Webアプリケーション診断(三井物産…
-
-
- Webアプリケーション診断(三井物産…
-
- Software type
- なし
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- 開発期にセキュリティ備え
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- ベーシックプラン 49,800円/月額 備考
- 1アプリケーションあたりの料金。手軽に続けられる高コストパフォーマンスプランです。
- Free trial
- Minimum usage period
- 1年
- komabato
-
-
- komabato
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- 純国産の自動診断
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- プラン 300,000円 備考
- 1ライセンス1FQDNの診断の料金です。ページ数制限はありません。
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- Web Doctor
-
-
- Web Doctor
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- エージェント不要で脆弱見える化
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- Vuls OSS 0円 備考
- 脆弱性をスキャンします。
- FutureVuls standard 4,000円/月額 備考
- 脆弱性を管理します。1台の料金です。
- 複数システムの脆弱性を横断管理 要相談 備考
- 複数システムの脆弱性を横断管理します。最小100台からのプランです。
- Free trial
- Minimum usage period
- 1ヵ月
- Vuls
-
-
- Vuls
-
- Software type
- パッケージ型ソフト
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- 手軽に弱点を可視化
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- プラン 0円 備考
- オープンソースのソフトウェアです。Greenboneのクラウドサービスなどの料金はお問い合わせください。
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- OpenVAS
-
-
- OpenVAS
-
- Software type
- パッケージ型ソフト
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- 全方位視点で守る安心
-
-
- 初期費用 要相談 備考
- 問合わせの後個別見積
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- NRI SECURE
-
-
- NRI SECURE
-
- Software type
- なし
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
価格や製品機能など、見やすい一覧表から、気になる製品をまとめてチェック!