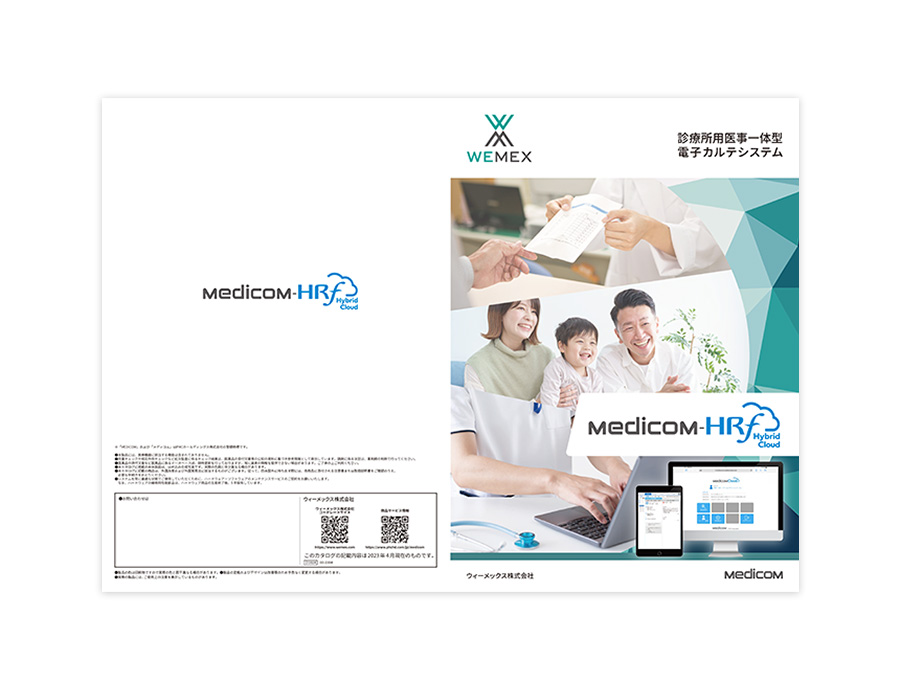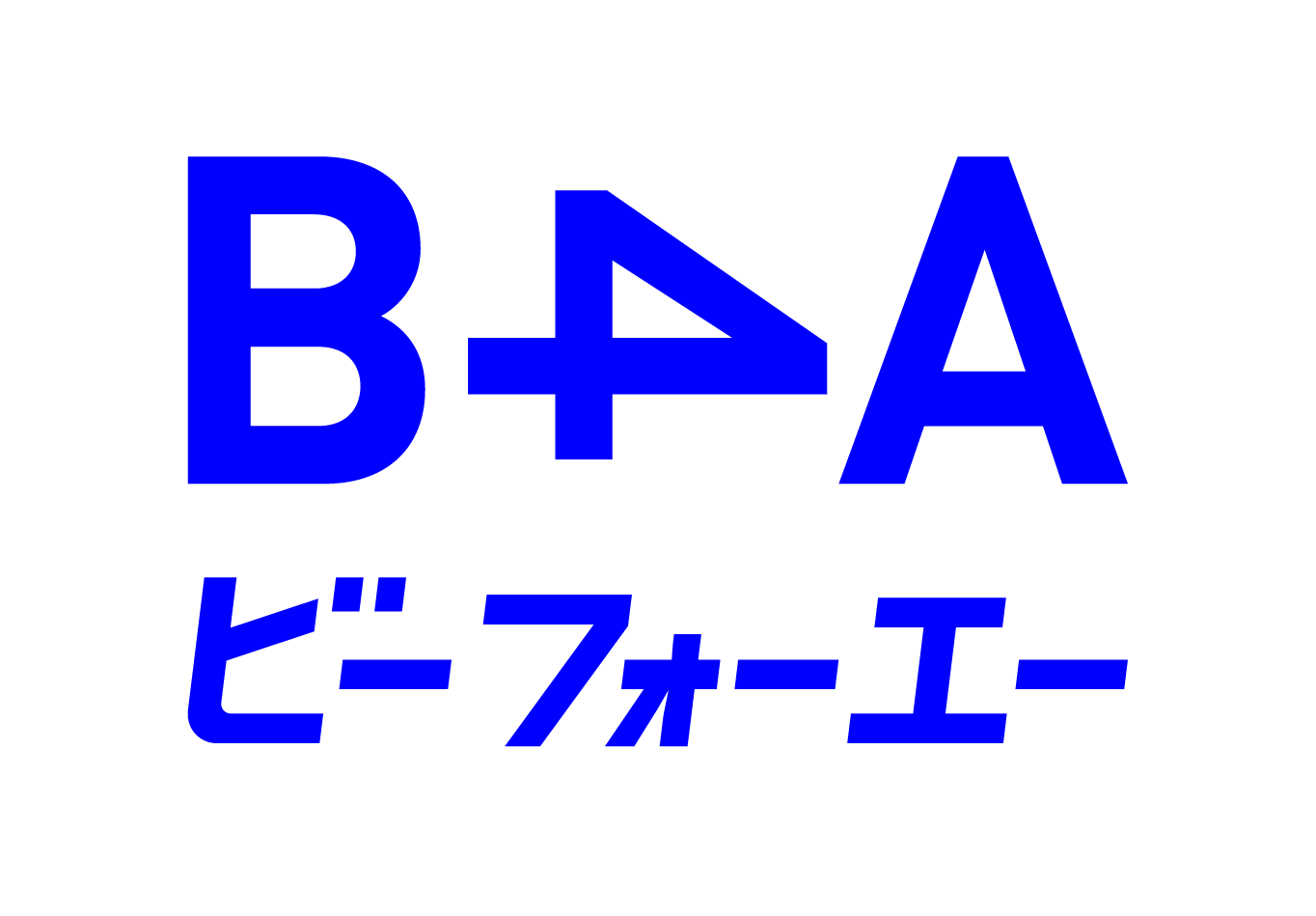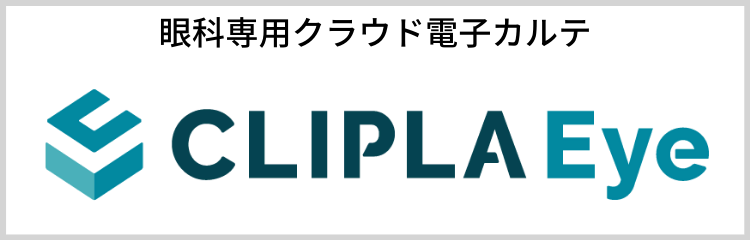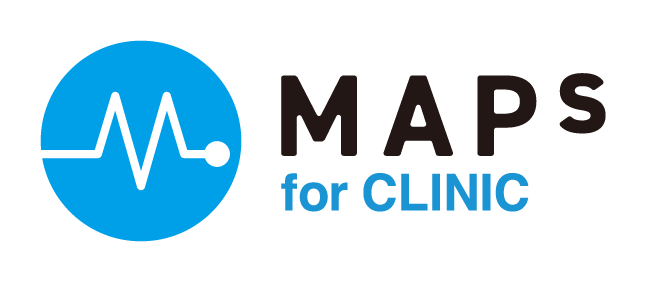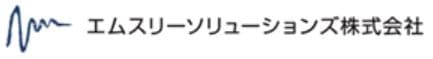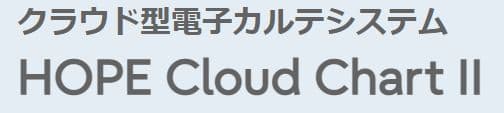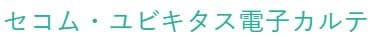電子カルテが普及しない理由とは?現状の普及率や解決方法、導入事例を解説
最終更新日:2023/07/27
<a href = "https://digi-mado.jp/article/62298/" class = "digimado-widget" data-id = "62298" data-post-type = "post" data-home-url = "https://digi-mado.jp" target = "_blank"></a>
<script src = "https://digi-mado.jp/wp-content/themes/digi-mado/js/iframe-widget.js"></script>


『デジタル化の窓口』は、この国のデジタル課題「2025年の崖」に備えるため2022年にサービスをスタートしました。1,500以上のIT製品、4,000以上の導入事例を掲載し、特長・選び方を分かりやすく整理して解説することで、自社に最適な製品・サービスを見つけるお手伝いをする紹介サービスです。
目次
この記事では、電子カルテが普及しない理由に迫ります。セキュリティ上の懸念やプライバシー問題、導入コストの負担、医療現場のデジタル化に対する抵抗感、システムの相互運用性の課題、利便性と使い勝手の向上が求められている要因を具体的に掘り下げ、解決方法としての具体的なアプローチも提案しています。これらの課題への対応により、電子カルテの普及率向上が期待され、未来の医療システムの持続可能性にも寄与することでしょう。
「電子カルテ」の製品比較表
※税込と表記されている場合を除き、全て税抜価格を記載しています
-
- 製品名
- 料金プラン
- プラン名金額
- 無料トライアル
- 最低利用期間
- 製品名
- 基本的な機能
-
- 適応・禁忌チェック
- 手書き入力
- 院内検査項目管理
- 文書管理
- カルテ編集
- レセプト対応
- プロブレム記録
- データ連携
- 実施歴参照機能
- 検査結果ビューアー
- 処方監査
- バイタル管理
- ToDoリスト
- 処置行為自動学習
- ケアプラン作成
- マルチデバイス対応
- 院内連絡
- 診療システム切替
- 予約機能
- 訪問スケジュール管理
- 診療・投薬履歴管理
- 製品名
- サービス資料
- 無料ダウンロード
- ソフト種別
- 推奨環境
- サポート
-
-
-
- 初期費用/更新費用 0円
- 月額費用 お問い合わせ
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- カロネード
-
-
- カロネード
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円
- Acronis Cyber Protect Standard ~ 9,500円 備考
- 中小規模の環境向けのデータ保護とサイバーセキュリティ
- Acronis Cyber Protect Advanced ~ 13,900円 備考
- 大規模なIT環境向けの高度なデータ保護とサイバーセキュリティ
- Acronis Cyber Protect – Backup Advanced ~11,600円 備考
- 大規模なIT環境向けの高度なデータ保護
- Free trial
- Minimum usage period
- 1年
- Acronis Cyber Prot…
-
-
- Acronis Cyber Prot…
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- Zaitak Karte
-
-
- Zaitak Karte
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 3,300円(税込)/月額 備考
- 標準サービスのみ
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- MIC WEB SERVICE
-
-
- MIC WEB SERVICE
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- CLIPLA Luna
-
-
- CLIPLA Luna
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 500,000円
- 利用料金 40,000 円/月額
- Free trial
- Minimum usage period
- 1年
- Dentis
-
-
- Dentis
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 400,000円~
- 利用料金 22,000円~/月額
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- Warokuクリニックカルテ
-
-
- Warokuクリニックカルテ
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 最低利用期間制限なし
- Alpha
-
-
- Alpha
-
- Software type
- オンプレミス型ソフト
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- Claio(クライオ)眼科パッケージ…
-
-
- Claio(クライオ)眼科パッケージ…
-
- Software type
- パッケージ型ソフト
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- IMAGEnet eカルテ v5クラ…
-
-
- IMAGEnet eカルテ v5クラ…
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- CLIPLA Eye
-
-
- CLIPLA Eye
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ Windowsアプリ Macアプリ iOSアプリ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- Henry
-
-
- Henry
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- Medicom-CKⅡ
-
-
- Medicom-CKⅡ
-
- Software type
- クラウド型ソフト オンプレミス型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円
- 1接続 20,000円/月額 備考
- 追加1接続当たり
5,000円/月額
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- MAPs for CLINIC
-
-
- MAPs for CLINIC
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 利用期間の制限なし
- CLINICSカルテ
-
-
- CLINICSカルテ
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 30,000円 備考
- coming-soonへの登録に初期費用が掛かります。(複数店一括契約の割引あり)
- KARTEフリー 0円 / 月 備考
- coming-soonへの登録が必須で別途月額が掛かります。「ライト」13,000円/月、「スタンダート」21,000円/月
- KARTEプラス 3,000円 / 月 備考
- coming-soonへの登録が必須で別途月額が掛かります。「ライト」13,000円/月、「スタンダート」21,000円/月
- KARTEエンタープライズ 10,000円 / 月 備考
- coming-soonへの登録が必須で別途月額が掛かります。「ライト」13,000円/月、「スタンダート」21,000円/月
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- coming-soon KARTE
-
-
- coming-soon KARTE
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- iOSアプリ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 要相談 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- 電子カルテシステムTOSMEC Av…
-
-
- 電子カルテシステムTOSMEC Av…
-
- Software type
- オンプレミス型ソフト
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- HAYATE NEO
-
-
- HAYATE NEO
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 0円
- ORCA連動型プラン 11,800円~/月額
- レセコン一体型プラン 24,800円~/月額
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- エムスリーデジカル
-
-
- エムスリーデジカル
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 200,000円 〜
- 基本プラン 12,000円 / 月額
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- CLIUS
-
-
- CLIUS
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 要相談 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- HOPE LifeMark-MX
-
-
- HOPE LifeMark-MX
-
- Software type
- なし
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 要相談 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- HOPE Cloud Chart I…
-
-
- HOPE Cloud Chart I…
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 要相談 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- HOPE LifeMark-HX
-
-
- HOPE LifeMark-HX
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- blanc
-
-
- blanc
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 要相談 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- SUPER Clinic
-
-
- SUPER Clinic
-
- Software type
- オンプレミス型ソフト
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 200,000円(税別)
- 月額費用 50,000円/月額(税別) 備考
- 基本5ユーザー
- アカウント追加 2,000円/月額(税別)
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- モバカルネット
-
-
- モバカルネット
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 2,200円 備考
- 工事
- 基本料金(端末1台利用時) 20,900円/月額/ID
- 追加IPアドレス利用料 3,300円/月額/追加1端末
- フレッツ光 初期費用 要相談
- フレッツ光 月額費用 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- Bizひかりクラウド Future …
-
-
- Bizひかりクラウド Future …
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- 電子カルテシステム ER
-
-
- 電子カルテシステム ER
-
- Software type
- オンプレミス型ソフト
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- MegaOakHR
-
-
- MegaOakHR
-
- Software type
- オンプレミス型ソフト
- Recommended environment
- Windowsアプリ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- i-MEDIC電子カルテシステム
-
-
- i-MEDIC電子カルテシステム
-
- Software type
- オンプレミス型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- RACCO
-
-
- RACCO
-
- Software type
- なし
- Recommended environment
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- ProSeedSV
-
-
- ProSeedSV
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- Windowsアプリ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- Open-Karte
-
-
- Open-Karte
-
- Software type
- オンプレミス型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- Open-Karte AD
-
-
- Open-Karte AD
-
- Software type
- オンプレミス型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- Open-Karte Cloud
-
-
- Open-Karte Cloud
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 要相談 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- Hi-SEED Cloud
-
-
- Hi-SEED Cloud
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 要相談 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- Hi-SEED W3 EX
-
-
- Hi-SEED W3 EX
-
- Software type
- オンプレミス型ソフト
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- 初期費用 要相談
- 料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- セコム・ユビキタス電子カルテ
-
-
- セコム・ユビキタス電子カルテ
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
-
-
- きりんカルテ システム利用料(初期費用) 無料 備考
- 初期費用
- WebORCA 初期設定費用 100,000円~ 備考
- 初期費用
- WebORCA 導入サポート費用 300,000円~ 備考
- 初期費用
- きりんカルテ システム利用料 無料 備考
- 月額利用料
- きりんカルテ チャットサポート費用 無料 備考
- 月額利用料
- WebORCA 保守・サポート費用 22,800円~ 備考
- 月額利用料
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- きりんカルテ
-
-
- きりんカルテ
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
価格や製品機能など、見やすい一覧表から、気になる製品をまとめてチェック!
電子カルテの普及率の現状
現在の電子カルテ普及率とその変化
電子カルテのシェアや普及率については、医療現場のデジタル化の進展に伴い、年々拡大している傾向にあります。厚生労働省によると、2020年度時点で、医療機関における電子カルテの普及率は一般病院で57.2%、一般診療所においては49.9%となっています。
病床規模別の普及率では、400床以上は91.2%、200~399床は74.8%、200床未満が48.8%となっています。また、電子カルテのシェアについてもシステム提供会社ごとに異なりますが、複数の大手システム提供会社が存在し、競争が激化している状況です。今後も、デジタル化の進展に伴い、電子カルテのシェアや普及率は拡大していくことが予想されます。
電子カルテ普及が進まない地域や業界の特徴
一部の地域や業界では、電子カルテの導入が進まないケースが見られます。普及が遅れる理由として、地域ごとの規制や文化的要因、特定の業界の特有の課題などが考えられます。成功している地域や業界の事例も参考にしながら、普及の障壁を理解しましょう。
既存の普及促進策の評価と課題
過去に試みられた電子カルテの普及促進策を振り返り、それらの成果と課題を検証します。普及率向上に寄与した施策や成功例に焦点を当て、今後の取り組みに生かすべき要素を洗い出しましょう。
普及率向上への必要性とメリット
電子カルテの普及率向上がなぜ重要なのか、そのメリットを詳しく解説します。効率化、情報共有、医療品質の向上など、普及によって得られる具体的な利点を具体例を交えて説明し、読者の理解を深めます。
電子カルテが普及しない理由
セキュリティ上の懸念とプライバシー問題
医療情報のデジタル化に伴い、情報漏洩やハッキングのリスクが懸念されます。読者の心配を理解し、現在のセキュリティ対策とプライバシー保護に注力した技術の進展について詳細に説明します。また、専門機関による監査や認証制度の重要性も強調しましょう。
コストや導入負担の問題
電子カルテの導入には高額な初期費用や運用コストがかかるため、多くの医療機関が導入に踏み切りにくいという課題があります。コスト削減策や助成金制度、クラウドサービスの活用など、導入負担を軽減する方法について具体的な対策を示します。
医療現場のデジタル化に対する抵抗感
電子カルテの導入には、従来の紙ベースのカルテとの切り替えに伴う抵抗感があります。導入段階でのトレーニングやサポート体制の重要性を強調し、スムーズな移行をサポートするための取り組みを提案します。
システムの相互運用性の課題
異なる医療機関や施設で使用されている電子カルテのシステムが相互に連携できないと、情報共有が難しくなります。標準化の重要性を説明し、データの共有が円滑に行える仕組みづくりが必要であることを述べます。
電子カルテの利便性と使い勝手の向上が必要
電子カルテの利便性や使い勝手が不十分だと、医療従事者の満足度が低下し、導入が進まない原因となります。ユーザーインターフェースの改善やフィードバックを反映する仕組みを導入することで、利便性向上に向けた取り組みを提案します。
電子カルテ普及のための解決方法
セキュリティ対策とプライバシー保護の強化
電子カルテのセキュリティを高めるために、最新の暗号化技術やアクセス制御の導入を推奨します。また、患者の個人情報を適切に管理するプライバシーポリシーの策定や従業員の教育も重要です。
導入コストや負担を軽減する支援策
各医療機関が電子カルテを導入しやすくするために、政府や業界団体による補助金制度やローンプログラムを活用することを提案します。また、導入時のトレーニングやカスタマーサポートを提供して、スムーズな移行をサポートします。
デジタル化への理解を促進する啓発活動
電子カルテのメリットや普及の重要性を広く理解してもらうために、啓発活動を展開します。ワークショップやセミナーを開催し、成功事例や利点を具体的に紹介することで、医療関係者の理解を深めます。
標準化と相互運用性の推進
業界標準を用いた電子カルテの構築や、相互運用性を高める取り組みを行います。データの共有や連携がスムーズに行われることで、医療連携の質を向上させます。
ユーザー中心のデザインと使いやすさの向上
医療従事者の意見を取り入れたユーザー中心のデザインを行い、電子カルテの使い勝手を改善します。タブレット端末の導入やカスタマイズ機能の充実により、使いやすさを追求します。
海外事例から学ぶ電子カルテ普及の成功例
先進国の電子カルテ普及事情とその取り組み
先進国における電子カルテの普及事情を調査し、成功している国々の取り組みを解説します。デンマークやエストニアの電子カルテ制度における成果や特徴について具体的に紹介します。
成功した普及事例からの教訓
海外の成功事例から得られる教訓を整理し、日本の状況に応用できる点を明確にします。成功要因として、政策の強力な推進、ユーザーとの協力、セキュリティ対策への投資などを挙げ、具体的な実践方法を示します。
日本における普及に応用できる要素
海外の事例を元に、日本の医療現場に適用できる具体的な要素を洗い出します。特に、日本の文化や規制に合ったアプローチや、地域の特性を踏まえたカスタマイズが重要であることを強調します。
未来へ向けての展望
テクノロジーの進化と電子カルテの可能性
テクノロジーの進化は絶え間なく進んでおり、人工知能やビッグデータの活用など、電子カルテが持つ可能性は広がっています。これらの技術を活用して、より高度な診断支援や個別化医療が実現する展望を述べます。
人間とテクノロジーの調和を目指す
電子カルテの普及によって、医療現場における人間とテクノロジーの調和が求められます。医療従事者と患者の信頼関係を大切にしつつ、デジタル化の利点を最大限に生かす方法を考えます。
電子カルテ普及の社会的意義と期待される効果
電子カルテの普及は医療現場だけでなく、社会全体にも重要な影響を及ぼします。医療データの蓄積と分析により、疾病の早期発見や流行の把握など、公衆衛生の向上が期待されます。その社会的意義や効果について具体的に説明します。
持続可能な医療システム構築への役割
電子カルテの普及は、医療システム全体の持続可能性にも関わります。医療リソースの効率的な活用や過剰な検査の削減など、電子カルテが果たすべき役割について考察します。
読者に役立つ電子カルテ情報の提供
実践的な導入ガイドライン
電子カルテを導入する際のステップやポイントを分かりやすく解説します。具体的な手順やチェックリストを示し、スムーズな導入に役立つ情報を提供します。
有益な電子カルテ関連サービスの紹介
電子カルテ導入に際して、サポートサービスや専門企業の活用が役立ちます。優良なサービスプロバイダーや導入成功事例を紹介し、読者の選択をサポートします。
今後の動向を知るための情報源
電子カルテ技術は進化し続けています。最新の動向を把握するために、信頼性のある情報源や学会などの活用方法を紹介します。情報収集の重要性を強調し、読者が常に最新情報を追いかける姿勢を促します。
内容の振り返り
電子カルテ普及の課題と可能性
電子カルテの普及には様々な課題がありますが、その可能性も大きいことを再確認します。課題を克服し、普及が進むことで医療現場の質を向上させることができるという点を強調します。
読者が実践できるアクションプラン
読者に対して、具体的なアクションプランを提案します。セミナーへの参加や専門書籍の読書、導入計画の立案など、普及をサポートする方法を示します。
未来の医療に向けた展望
電子カルテが持つ可能性に対して、未来の医療システムに向けた展望を述べます。テクノロジーの進化と医療従事者の専門知識を組み合わせることで、より高度な医療が実現できるという展望を描きます。
まとめ
この記事では、電子カルテが普及しない理由について詳しく解説してきました。セキュリティ上の懸念やプライバシー問題、導入コストの負担、医療現場のデジタル化に対する抵抗感、システムの相互運用性の課題、利便性と使い勝手の向上が求められていることが分かりました。
それに対し、セキュリティ対策とプライバシー保護の強化、導入コストや負担の軽減、ユーザー中心のデザイン、啓発活動などの解決方法が提案されています。さらに、海外事例から学ぶ成功例を参考にし、日本における普及に応用できる要素も洗い出されています。
これらの取り組みが進むことで、電子カルテの普及率が向上し、医療現場の効率化や情報共有が円滑に行われることが期待されます。未来に向けてはテクノロジーの進化によりさらなる可能性が広がり、人間とテクノロジーの調和を目指した持続可能な医療システムの構築に貢献することが重要です。
電子カルテの普及に向けて、これらの課題と可能性を理解し、読者自身がアクションプランを立てる一助となれば幸いです。それにより、より質の高い医療サービスが広く提供され、社会全体の健康と福祉に貢献することが期待されます。
<a href = "https://digi-mado.jp/article/62298/" class = "digimado-widget" data-id = "62298" data-post-type = "post" data-home-url = "https://digi-mado.jp" target = "_blank"></a>
<script src = "https://digi-mado.jp/wp-content/themes/digi-mado/js/iframe-widget.js"></script>
おすすめ比較一覧から、
最適な製品をみつける
カテゴリーから、IT製品の比較検索ができます。
1599件の製品から、ソフトウェア・ビジネスツール・クラウドサービス・SaaSなどをご紹介します。
(無料) 掲載希望のお問い合わせ