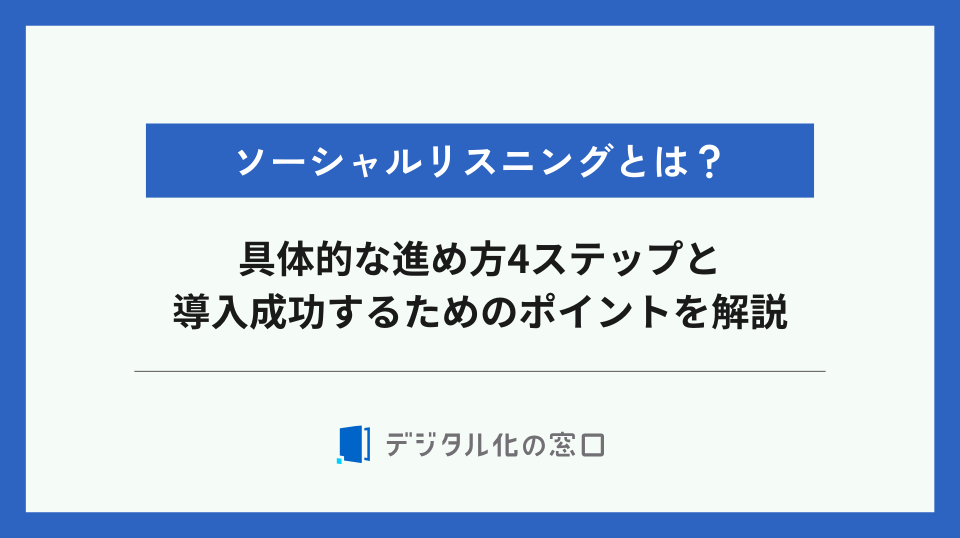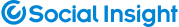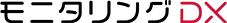「ソーシャルリスニングツール」の製品比較表
※税込と表記されている場合を除き、全て税抜価格を記載しています
-
- 製品名
- 注目ポイント
- 料金プラン
- プラン名金額
- 無料トライアル
- 最低利用期間
- 製品名
- 基本的な機能
-
- 評判分析
- 感情判定
- 国内メーカー
- インスタントウィン機能
- リツイートランキング
- デイリートピックメール
- インフルエンサー調査
- 関連語マップ
- 投稿予約
- 新語抽出
- Excel出力
- 判定候補ワードの自動抽出
- カンバセーション
- 口コミ推移
- 活動傾向分析
- 炎上の事前検知
- 拡散プロセス分析
- CSVデータ出力
- ポジネガ分析
- 多言語対応
- 製品名
- サービス資料
- 無料ダウンロード
- ソフト種別
- 推奨環境
- サポート
-
- 全媒体を一括分析
-
-
- Free 0円
- Starter 6,000円/月
- Professional 60,000円/月
- Enterprise 144,000円/月
- Free trial
- Minimum usage period
- 利用期間の最低制限なし
- NEX-RAY
-
-
- NEX-RAY
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- 口コミ管理をもっと楽に
-
-
- 初期費用 要相談
- 料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- HOSHITORN
-
-
- HOSHITORN
-
- Software type
- なし
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- 感情を見える化するAI
-
-
- 初期費用 要相談
- 料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- KAIZODE
-
-
- KAIZODE
-
- Software type
- なし
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- 投稿管理をスマートに
-
-
- 初期費用 要相談
- ビジネス版 要相談
- エンタープライズ版 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- Social Insight
-
-
- Social Insight
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- SNSの今を丸ごと解析
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- プラン 10,000円~/月額
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- Tofu Analytics
-
-
- Tofu Analytics
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- 世界が選ぶ信頼分析
-
-
- 初期費用 要相談
- プラン 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- Brandwatch
-
-
- Brandwatch
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- AI精度99%分析
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- プラン 93,500円(税込)~/月額 備考
- 料金は利用キーワード数や対応内容により異なります。
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- モニタリングDX
-
-
- モニタリングDX
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- 5億件の声を可視化
-
-
- 初期費用 要相談
- プラン 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- Meltwater
-
-
- Meltwater
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- 炎上兆候を先読みAI
-
-
- 初期費用 要相談
- プラン 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- Talkwalker
-
-
- Talkwalker
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- 多彩機能で360度分析
-
-
- 初期費用 要相談
- プラン 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- NetBase
-
-
- NetBase
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- 競合も見えるSNS分析
-
-
- 初期費用 0円 備考
- 初期費用は発生しません。
- プラン 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- Insight Intelligen…
-
-
- Insight Intelligen…
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- 炎上兆候を1秒検知
-
-
- 初期費用 100,000円
- 基本プラン 150,000円/月額 備考
- ブログ・Q&Aサイトデータインポートが可能で、Twitterキーワード収集条件がつけられます。
- Twitterプラン 190,000円/月額 備考
- 基本プラン内容に加え、Twitter過去データ検索が可能です。
- リスクモニタリング プラン 210,000円/月額 備考
- Twitterプラン内容に加え、2ちゃんねるのデータもモニタリング可能です。
- クロスメディア プラン 380,000円/月額 備考
- リスクモニタリング プラン内容に加え、WebニュースやTVデータのモニタリングも可能です。
- Free trial
- Minimum usage period
- 6ヵ月
- Boom Research
-
-
- Boom Research
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- 1分で状況を把握
-
-
- 初期費用 要相談
- プラン 月額88,000円~(税込) 備考
- 小規模事業者から大企業事業者まで利用できます。
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- Buzz Finder
-
-
- Buzz Finder
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
価格や製品機能など、見やすい一覧表から、気になる製品をまとめてチェック!