BPaaSとは?BPOとの違いや導入成功に向けたステップガイドを紹介
最終更新日:2025/03/31
<a href = "https://digi-mado.jp/article/97530/" class = "digimado-widget" data-id = "97530" data-post-type = "post" data-home-url = "https://digi-mado.jp" target = "_blank"></a>
<script src = "https://digi-mado.jp/wp-content/themes/digi-mado/js/iframe-widget.js"></script>
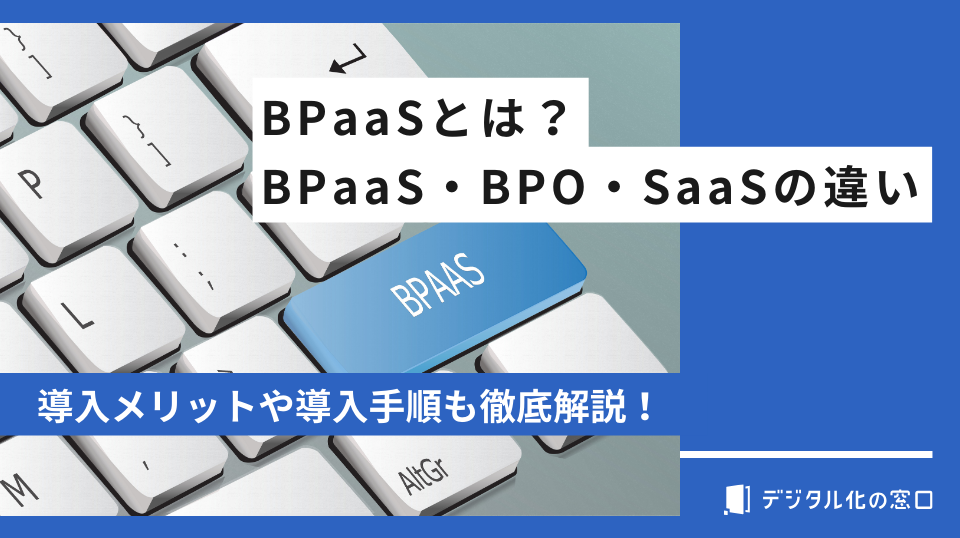

『デジタル化の窓口』は、この国のデジタル課題「2025年の崖」に備えるため2022年にサービスをスタートしました。1,500以上のIT製品、4,000以上の導入事例を掲載し、特長・選び方を分かりやすく整理して解説することで、自社に最適な製品・サービスを見つけるお手伝いをする紹介サービスです。
目次
バックオフィス業務の効率化は、自社の生産性向上やコスト削減に寄与します。しかし、バックオフィス業務は煩雑な作業が多く、人的リソース不足を課題とする企業も珍しくありません。BPaaSはクラウド上で外部委託できるサービスで、DX推進を実現するうえでも注目されています。
本記事では、BPaaSとは何か、BPOやSaaSとの違いを解説します。活用できる業務の具体例や導入するメリット・デメリットも紹介するので、BPaaSの導入を検討している方は参考にしてください。
BPaaSとは
BPaaS(ビーパース)とはBusiness Process as a Serviceの略称で、クラウド上で業務プロセスを提供するサービスのことです。企業の業務を外部委託するアウトソーシングの一種となるBPOと、ネットワーク経由でサービスを利用できるSaaSを組み合わせたサービス形態がBPaaSになります。
BPaaSはバックオフィスに関する業務を外部委託できるだけでなく、データやノウハウを蓄積できる点が特徴です。幅広い業界の業務効率化やDX推進を図れるため、BPaaSは注目を集めています。
BPaaS・BPO・SaaSの違い
ここでは、BPaaS・BPO・SaaSの違いを紹介します。
混在しがちなサービスとなるBPOやSaaSとBPaaSの相違点が知りたい方は、参考にしてください。
BPaaSとBPOの違い
BPaaSとBPOでは、業務プロセスの進め方に違いがあります。主な違いは、以下の通りです。
| BPaaS | BPO | |
| サービス内容 | 企業がクラウド上で業務プロセスを外部委託するサービスモデル | 企業が業務プロセスを外部委託するアウトソーシングの一種 |
| サービス対象 | 特定の業務だけでなく、システムやアプリケーションの運用など業務プロセス全体を外部委託できる | 給与計算やデータ入力など、特定の業務を外部委託できる |
| 導入から運用まで | システム導入から業務運営や実行まで業務プロセス全体を外部に委託 | 業務の実行のみ外部に委託 |
BPaaSは特定の業務のみを委託できるBPOと異なり、経理や人事、営業支援など幅広い業務プロセスを外部に委託できます。カバー可能な業務範囲の幅が広いため、企業は柔軟な運用を実現できるでしょう。
BPaaSとSaaSの違い
BPaaSとSaaSでは、提供するサービス内容に違いがあります。主な違いは、以下の通りです。
| BPaaS | SaaS | |
| サービス内容 | 企業がクラウド上で業務プロセスを外部委託するサービスモデル | クラウド上でソフトウェアを利用するサービス |
| サービス対象 | 特定の業務だけでなく、システムやアプリケーションの運用などSaaSを活用して業務プロセス全体を外部に委託できる | アプリケーションやOSなど目的に応じたソフトウェア |
| 導入から運用まで | SaaSの導入から 業務運営まで業務プロセス全体を外部に委託 | インターネット経由でソフトを利用し、企業が運用を行う |
SaaSはCRM(顧客関係管理)や会計ツールなど特定の業務を支援するツールで、業務を行うのはユーザーとなる企業です。企業は業務効率化に向けて、自社でSaaSを上手く使いこなす必要があります。
対して、BPaaSではSaaSの利用を得意とする事業者に委託できるため、業務の効率化とコスト削減の両方を実現可能です。
BPaaSを活用できる業務の具体例
BPaaSは、人事や経理、営業など幅広い業務で活用できます。
ここでは、BPaaSを活用できる業務の具体例を紹介するので、導入を検討している方は参考にしてください。
人事管理業務
人事管理は、従業員一人ひとりの基本情報や人事評価、勤怠データなどを管理する業務です。従業員が適切な評価を受けるためには、正確なデータを記録する必要があるため、業務負担の大きい分野になります。
BPaaSで委託できる主な人事管理業務は、以下の通りです。
- 勤怠管理
- 人事評価の管理
- 福利厚生管理
BPaaSの導入は、給与計算や勤怠管理をリアルタイムで更新できるだけでなく、従業員のデータを一元管理できます。また、BPaaSではシステム導入から業務委託が可能なため、データの連携やセットアップの負担を解消できます。
給与計算・経理業務
給与計算や経理は正確さが求められるだけでなく、経費計算や税務申告など煩雑な作業が多い業務です。税金に関する法改正には迅速に対応するスキルが必要なため、専門的な知識が欠かせない分野になります。
BPaaSで委託できる主な給与計算・経理業務は、以下の通りです。
- 月次給与計算
- 経費計算
- 税務申告
- 請求書作成
- 支払処理
- 監査対応
給与計算や経理業務にBPaaSを活用することで、毎月発生する業務のリソースを削減できます。また、SaaSはクラウド上でソフトウェアを運用しているため、自動アップデートが行われることから税制や法改正にも素早く対応できます。
給与計算や経理業務の人的リソースが課題の企業は、BPaaSの導入により法的リスクを軽減し、正確性の高い業務運営を実現できるでしょう。
販売業務
受注管理や在庫管理、顧客への請求書発行などを行う販売業務も、BPaaSの活用により効率的な顧客対応を実現できます。BPaaSで委託できる主な販売業務は、以下の通りです。
- 顧客管理
- 見積書・請求書発行
- 受注・出荷処理
- 契約管理
- 売上データの分析
BPaaSでは顧客情報や取引履歴などがクラウド上で一元管理できるため、メンバー間で共有できます。効率的に手続きや顧客管理が可能となることから、企業はデータをもとに営業戦略が立てられます。
カスタマーサービス業務
カスタマーサービスは、顧客との接点が多いため、顧客満足度向上や関係構築など重要な役割を担う業務です。しかし、カスタマーサービス業務は多岐にわたり、人的リソースの負担が大きいだけでなくサービス品質に差が生じやすいデメリットが生じます。
BPaaSで委託できる主なカスタマーサービス業務は、以下の通りです。
- 顧客問い合わせ対応
- 多言語対応
- 顧客満足度調査
- チャットボットやAIを活用したサポート
- 問い合わせ内容の振り分け
BPaaSでは高度な技術も利用できるため、AIチャットボットや遠隔サポートなど、最新技術を搭載したカスタマーサービスの導入も可能です。コスト削減・品質向上を実現できるため、顧客の信頼獲得や自社のブランド力強化が期待できるでしょう。
IT運用業務
IT運用はトラブルが発生した際に専門知識が求められるだけでなく、リソースが割かれやすい業務です。また、システムトラブルは企業の業務やサービスに影響を与えるため、早期発見に向けて監視する必要があります。
BPaaSで委託できる主なIT運用業務は、以下の通りです。
- ヘルプデスクの対応
- システム監視
- ソフトウェアのバージョン管理
- IT資産の管理
- セキュリティ対策
BPaaSの導入は、トラブルシューティングや日常管理によるリソースの負担を軽減できます。また、ITの専門知識がなくても高度なITサービスを利用できるため、企業変革に寄与します。
マーケティング業務
マーケティングは競合他社との差別化を図り、自社成長を促すために重要な業務です。しかし、マーケティングへの理解が不十分だったり、リソース不足で継続できなかったりといった課題を抱える企業も珍しくありません。
BPaaSで委託できる主なマーケティング業務は、以下の通りです。
- 広告運用
- マーケティングツールの一元管理
- メールマーケティングの自動化
BPaaSでは社内リソースを確保する必要がなく、顧客との接点を増やせる機会を設けられるため、生産性向上が期待できます。また、マーケティング担当者はコア業務に集中できるため、戦略的なマーケティング活動を実施できるでしょう。
BPaaSを導入する3つのメリット
ここでは、BPaaSを導入するメリットを紹介します。
具体的な利点を以下で解説するので、BPaaSの導入により企業が得られる効果を知りたい方は参考にしてください。
1.業務の効率化を図れる
BPaaSを導入するメリットは、業務担当者の時間とリソースを削減できる点です。BPaaSでは業務プロセス全体を外部に委託できるため、担当者は利益創出に直結する業務に集中しやすい環境を作れます。
担当者がコア業務に集中することで、生産性の向上が期待できます。また、BPaaSではクラウド上にデータが集約されており、メンバー内で共有しやすい点が特徴です。スムーズな業務運営が可能となり、利益率の向上が見込めます。
2.コスト削減が期待できる
BPaaSの活用は、人材雇用や社内教育のコスト負担を軽減できます。サービスの多くは従量課金制や月額課金制となっており、企業はリソースを柔軟に確保できるためです。
例えば、年末が繁忙期となる年末調整の時期のみリソースを増やすといった利用方法も、BPaaSでは可能です。
また、BPaaSを導入すると企業は自社でサービスを開発しなくて済むため、初期費用を抑えやすいメリットがあります。BPaaSは柔軟さが特徴で効率良く運用できることから、コストを削減しつつ質の高いサービスを提供できます。
3.ノウハウを蓄積できる
BPaaSではデータの蓄積が可能なため、内製化へ向けて人材の教育や環境の整備ができます。クラウド上で業務プロセスを管理できることから、社内での共有が容易なためです。
BPOでは、業務を外部に委託するためノウハウを蓄積できないデメリットが生じます。しかし、BPaaSでは蓄積されるデータを有効活用し、ノウハウを蓄積できます。企業は中長期的に事業者に依存するリスクを回避できるため、業務の標準化が期待できるでしょう。
BPaaSを導入する3つのデメリット
ここでは、BPaaSを導入するデメリットを紹介します。
注意点を以下で解説するので、BPaaSを導入するうえで事前に把握しておくべき点が知りたい方は参考にしてください。
1.セキュリティリスクが懸念される
BPaaSを導入するデメリットは、個人情報や機密情報の流出が懸念される点です。SaaSを組み合わせたサービスとなるBPaaSでは、クラウド上で業務プロセスやデータを管理します。
セキュリティ対策が不十分だと、サイバー攻撃や内部不正により企業のデータが流出するリスクが生じます。万が一情報漏洩があった場合、企業に大きな影響を及ぼすため、BPaaSを導入する際は注意が必要です。
セキュリティ対策を行っているBPaaSのサービスがほとんどですが、万が一のリスクを防ぐためにもどのような対策を講じているのか確認することが大切です。
2.カスタマイズが限定される
BPaaSでは、自社に合わせたカスタマイズが難しいというデメリットが生じます。サービスが標準化されているため、自社の課題となる業務のすべてに対応してもらえるわけではありません。
標準機能では対応できず、追加費用がかかってしまいコストが高くなったり、業務負担が増えたりして費用対効果を得られないケースも考えられます。BPaaSは業務プロセスを自社で回す場合と比べて柔軟性が低い可能性もあるため、検討する際はどこまで対応できるか確認しておきましょう。
3.システムトラブル発生時に業務が中断する恐れがある
システムトラブルが発生した際、解決に至らず自社の業務が中断する可能性があります。BPaaSでは、ネットワーク経由でサービスを利用するSaaSを活用して業務を行うためです。
万が一、BPaaS事業者側でシステム障害や業務トラブルが発生すると、復旧するまで自社の業務が中断する恐れがあります。BPaaSを導入するときはトラブルが発生した際、自社の業務に支障が出ないよう対策を検討することが大切です。
BPaaSの導入が適している企業の特徴
ここでは、BPaaSの導入が適している企業の特徴を紹介します。
以下でポイントを解説するので、BPaaSを導入するべきかお悩みの方は参考にしてください。
IT業務に関する人材確保ができていない企業
BPaaSではIT業務を委託できるため、エンジニアを確保できていない企業におすすめです。企業はDX推進に伴い、ITに関する専門知識を持つ人材の確保が必要になります。
しかし、なかには人材の確保ができておらず、DXに取り組めていない企業も珍しくありません。
BPaaSでは人材を自社で確保しなくても高度なITサービスを利用できるため、エンジニアを採用する必要がないほか、教育体制を整えなくて済みます。ITリソースの投入にお悩みの企業は、BPaaSへの委託を検討しましょう。
DX化を推進したい企業
社内のDX推進には、BPaaSが役立ちます。BPaaSでは、SaaSの活用を得意とする事業者に業務プロセスを委託できるためです。
業務プロセスの自動化やデータの可視化が可能となり、DX化推進を加速させられます。BPaaSではAIや社内管理システムなどを用いて業務を進められるため、自社の価値や競争優位性の創出につなげられるでしょう。社内にDXに関する知見を持つ人材がいない企業は、BPaaSの活用がおすすめです。
海外進出を行っている企業
グローバル展開が進んでいる企業には、BPaaSの導入が適しています。BPaaSでは地域によって異なる法律や規制、文化に対応できるサポートを提供しているため、適切なコンプライアンス対応とリスク管理が可能です。
また、クラウド上で業務を管理できるBPaaSでは、各地域のプロバイダーや専門知識を持つ人材と連携できます。BPaaSでは文化的な違いに対応できるため、国外にサービスを展開している企業でもスムーズに業務を進められるでしょう。
BPaaS導入成功へ向けたステップガイド
企業はBPaaSの導入を成功させられるよう、ポイント別に検討していくことが大切です。
ここでは、BPaaS導入成功へ向けたステップを紹介するので、費用対効果を得たい方は参考にしてください。
1.自社の課題と導入目的を明確にする
まずは、BPaaSを導入する目的を明確にする必要があります。導入目的を明確にするには、自社の業務プロセスを可視化し、課題を洗い出すことが大切です。
自社の課題を明確にする際は、業務プロセスが効率化できていなかったり、コストがかかっていたりする点を挙げます。
課題をもとに自社が達成したい具体的な成果を設定すると、導入目的が明確になり、BPaaSの効果を最大化できるでしょう。
2.導入へ向けて社内体制を整える
BPaaSを導入する際は、ベンダーと連携して業務を進めていくために専任のチームを設置する必要があります。万が一トラブルが発生した場合の対処法やベンダーとの責任範囲などを明確にしておくことで、スムーズな運用を実現できるためです。
従業員がサービスの仕組みを理解できるよう、ワークショップや研修などを実施することも導入時のポイントです。企業は長期間BPaaSを提供する事業者に依存しないためにも、蓄積されたデータをもとに内製化できる体制を整えておきましょう。
3.導入目的に合ったBPaaSを選ぶ
課題や導入目的、社内体制を整えたあとは利用するBPaaSを選定します。BPaaSはサービスによって特徴や取り組みが異なるため、委託できる業務範囲やSaaSの使い勝手などから自社に適したものを選ぶことが大切です。
選定する際は、実績や導入事例を確認して自社の課題を解決できるか判断します。成果が期待できる実績を持っているか、BPaaSを提供する事業者の公式サイトをチェックして、自社に適したサービスを選びましょう。
4.試験運用を実施する
導入時は試験運用を実施し、自社に適しているか判断します。BPaaSは導入後に効果が得られなかったとしても、ほかの事業者に変更するまでに時間を要するためです。
導入成功には、中長期的に利用できるBPaaS事業者を選ぶ必要があります。試験運用時のチェックポイントは、以下の通りです。
- 作業時間は短縮できているか
- 使い勝手は良いか
- トラブル発生時にスムーズに対処できるか など
試験運用時は、トラブルが発生した際のワークフローを検討しておくことが大切です。
5.継続的に運用データを分析する
BPaaSの導入をゴールにするのではなく、自社が目的とする成果を得られているか、定期的にデータを分析しましょう。定期的なデータ分析を怠ると費用対効果を得られない可能性があるため、分析結果から設定の変更や追加機能の導入などを検討することが大切です。
また、BPaaSの導入では業務効率化だけでなく、デジタル化で蓄積したデータを活用して業務改善を図ることも重要なポイントになります。BPaaSの導入効果が最大化できるよう、PDCAを回しながら改善を重ね、スムーズな運用を目指しましょう。
BPaaSを選ぶ際のポイント
BPaaSを検討する際は効果を得られるよう、自社に適したサービスを選定することが重要です。
以下でBPaaSを選ぶ際のチェックポイントを紹介するので、参考にしてください。
自社が目的とする業務に特化しているか
BPaaSは対応できる業務が異なり、特化している分野もさまざまです。導入する際は自社業務とマッチしたサービスを選ぶことで、自社の課題を解決し効果の最大化を図れます。
BPaaSを選定する際は導入事例やサービス内容を確認したうえで、どのような業務に対応可能かチェックしましょう。また、最新のテクノロジーに精通しているかも選定時のポイントです。サービスを比較するときは、自社が目的とする業務に特化しているか確認しましょう。
セキュリティ対策は一定水準を満たしているか
BPaaSでは個人情報や機密情報を取り扱う場合があるため、セキュリティ対策が万全なサービスを選ぶことが大切です。万が一情報が漏洩すると、企業に影響を及ぼすリスクが生じます。
セキュリティ対策でチェックすべきポイントは、以下の通りです。
- プライバシーマークやISMS認証を取得しているか
- 二段階認証やIP制限など独自のセキュリティを設定できるか
- 不正アクセス対策を講じているか
サービスを比較する際は、提供する事業者にセキュリティ対策について説明を求め、十分な回答を得られるかチェックしましょう。
業務範囲と業務量は適しているか
BPaaSの業務範囲と業務量はサービスによって異なるため、自社のニーズに適しているか確認しましょう。業務プロセスが複雑な場合、業務範囲や業務量が適切でないと効率化が図れない可能性があるためです。
また、繁忙期や閑散期など業務量の変動に応じて柔軟な対応が可能かチェックすることもポイントになります。BPaaSを選ぶ際は費用対効果を得られるか、業務範囲と業務量について確認しておくことが重要です。
BPaaSの導入事例
ここでは、BPaaSの導入事例を紹介します。
| 業界 | サービス名 | 導入前の課題 | 導入効果 |
| 情報・通信会社 | Chatwork アシスタント |
|
|
| 建設会社 | ANDPAD請求管理 |
|
|
いずれの企業もBPaaSを活用することで、業務効率化につながり課題を解決できました。ヒューマンエラーが減り、業務品質の向上にもつながった事例といえるでしょう。
まとめ
BPaaSはBPOとSaaSを組み合わせたサービス形態で、業務プロセス全体を委託できるため業務効率化や生産性向上が期待できます。ただし、提供する事業者によって特化する業務が異なるため、選定時には注意が必要です。
BPaaSの導入効果を高めるためには、対応業務の範囲や業務量、セキュリティ対策などを確認し、最適なプランを選ぶ必要があります。自社の課題に適したBPaaSを選ぶことで、コア業務に集中できるようになり、企業成長に寄与します。
本記事では、BPaaSの概要からBPOとの違い、利用するメリット・デメリットを解説しました。活用できる業務の具体例や導入事例を参考に、自社に適したプランを利用して業務品質の向上を図りましょう。
<a href = "https://digi-mado.jp/article/97530/" class = "digimado-widget" data-id = "97530" data-post-type = "post" data-home-url = "https://digi-mado.jp" target = "_blank"></a>
<script src = "https://digi-mado.jp/wp-content/themes/digi-mado/js/iframe-widget.js"></script>


